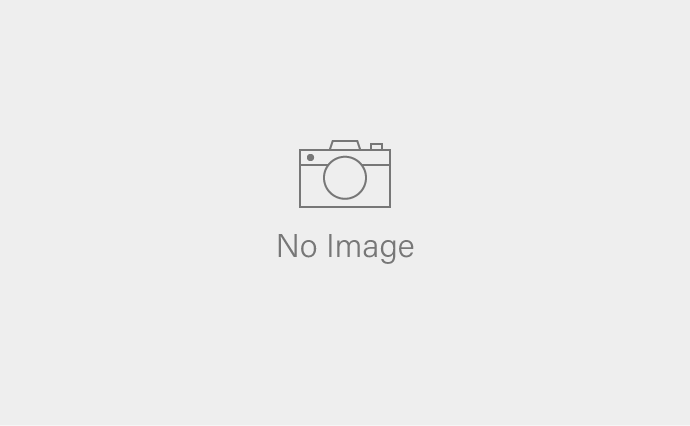2025年3月20日 直原裕naohara hiroshi
前回、「日本書紀」には多くの編纂上の謎があると述べました。今回はその内のひとつ、卑弥呼にも邪馬台国にも言及がないことについて、その理由を考えます。
1 「魏志倭人伝」の中の卑弥呼
中国の正史のひとつで魏蜀呉の三国時代を描いた「三国志」は、3世紀末に成立した。「魏書」、「蜀書」及び「呉書」からなる。「魏志倭人伝」は、この「魏書」の中の「烏丸鮮卑東夷伝」に含まれる「倭人」部分を指す。著者の陳寿(233?~297?)は、蜀に仕えたのち晋に出仕した。晋王朝は魏王朝から禅譲を受けて成立したので、陳寿は「三国志」において魏の正統性を主張したとされている。
「魏志倭人伝」には、卑弥呼や邪馬台国について、概略、以下の内容が書かれている。
・帯方郡から邪馬台国までの行程と途中の国々、邪馬台国の位置(後述)
・邪馬台国を中心とする倭国の統治の仕組み
・邪馬台国の北、南、東及び東南の国々
・倭人の風体(入れ墨など)と風俗(葬式の様子など)、物産
・倭国の歴史(男王の時代、大乱、女王卑弥呼の共立と弟の補佐)。卑弥呼の人物像(「鬼道に事え、能く衆を惑わす」)
・卑弥呼の魏への朝貢。魏皇帝から卑弥呼への「親魏倭王」叙爵と金印・紫綬等の授与
参考に、この部分の原文と訳(藤堂明保他訳)を示すと次の通り。
汝所在踰遠、乃遣使貢獻。是汝之忠孝、我甚哀汝。今以汝爲親魏倭王、假金印紫綬。(汝の住むところは海山を越えて遠く、それでも使いをよこして貢献しようというのは、汝の真心であり、余は非常に汝を健気に思う。さて汝を親魏倭王として、金印・紫綬を与えよう。)
・倭の女王卑弥呼と狗奴国との対立
・卑弥呼の死と塚の築造。倭国の混乱と宗女台与による安定回復
記述によると、倭国の使者が帯方郡、さらには魏の都洛陽を訪れただけでなく、少なくとも2回、正始元年(240)と正始八年(247)の後、帯方郡の使者が実際に倭国に派遣され邪馬台国を訪れた。陳寿は、使者の報告に基づく原資料(三国時代の歴史家魚豢が記した「魏略」。その殆どは散逸した。)をベースにして「魏志倭人伝」を書いた。魏の正統性の主張というバイアスが掛かっていることに注意を要するが、3世紀の倭国の様子を知りうる唯一の文字資料だ。
卑弥呼は、倭国内においては、「鬼道に事え」、「王と為りて自り以来、見ゆること有る者少なし」であり、「男弟が治国を佐け」ていた。一方、対外関係においては、魏がそれまで帯方郡を支配していた公孫氏を238年に討伐すると、速やかに魏に遣使した。また、240年に狗奴国との対立が深まると、帯方郡太守に報告し、その権威を紛争解決に利用した。
この点に関し石母田正は、卑弥呼には、国内においては未開社会に顕著なシャーマン的女王の顔があり、対外関係においては外交に主体的に対処する開明的な「親魏倭王」の顔があると指摘している。「魏志倭人伝」には、3世紀前半の東アジア世界における倭国の姿が、鮮やかに描かれている。
2 「書紀」の中の「魏志倭人伝」
「書紀」には、卑弥呼や邪馬台国が全く出てこない。言及がない。
しかし、「書紀」編纂者は「魏志倭人伝」を読んでいた。それどころか「魏志倭人伝」を引用している。「書紀」神功皇后紀に次のようにある。
三十九年。この年は、太歳己未である。〔『魏志』は、「明帝景初三年六月、倭の女王、大夫難斗(升か)米等を遣わして郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。太守鄧(劉か)夏、吏を遣わし、将て送りて、京都に詣らしむ」といっている。〕
四十年。〔『魏志』は、「正始元年、建忠校尉梯携(儁か)等を遣わして、詔書・印綬を奉りて、倭国に詣らしむ」といっている。〕
四十三年。〔『魏志』は、「正始四年、倭王、また使大夫伊声音(耆か)・掖耶約(狗か)等八人を遣わして上献す」といっている。〕
(「日本書紀」、井上光貞監訳)
「書紀」編纂者は、「魏志倭人伝」を読み卑弥呼について知っているが、卑弥呼を天皇家の先祖とは考えなかった。邪馬台国をヤマト王権の始まりとも考えなかった。このことに関して吉村武彦は次のように論じている。
『書紀』編者は、「魏志倭人伝」を通じて卑弥呼の知識を持っていた。しかし、「書紀」の古い時期の天皇は男性であり、女性はいない。そのため、卑弥呼を神功皇后に比定せざるをえなかった。このように無理に比定したので、卑弥呼の境遇とは大きく乖離してしまった。その理由としては、ヤマト王権にまつわる伝承に卑弥呼が含まれていなかったから、と考えることが妥当であろう。
(吉村『ヤマト王権』p.53)
卑弥呼は、天皇家に伝承されてきた皇統譜に属していなかったということだろう。しかしそれなら無視すればよいし、あるいははっきり否定すればよかった。「書紀」編纂者は、そうではなく、「魏志倭人伝」に書かれている卑弥呼は神功皇后のことだと言っている。これはどういうことなのだろうか。
3 邪馬台国の位置
ここで所謂邪馬台国論争、邪馬台国はどこにあったのかという議論に関わらざるを得ない。もし、邪馬台国が九州にあったとしたら、「書紀」編纂者は、果たして卑弥呼は神功皇后のことだと書いただろうか、と考えてみよう。そうは書かないのではないか。卑弥呼を天皇家の先祖と考えていない「書紀」編纂者としては、邪馬台国は当時九州にあった卑弥呼の国であり、その後ヤマト王権に服属したと書いたのではないだろうか。そうは書かなかったということは、邪馬台国は畿内にあったという見通しを私は持つのだが、この点は暫く保留にしようと思う。
ここで改めて「魏志倭人伝」の該当部分を読んでみよう。「魏志倭人伝」は、帯方郡から邪馬台国までの行程を記述している。帯方郡から奴国までは地図7の通り。
帯方郡→(循海岸水行七千余里)狗邪韓国→(度一海千余里)対馬国→(南渡一海千余里)一支国(壱岐)→(渡一海千余里)末盧国(松浦)→(東南陸行五百里)伊都国(糸島)→(東南百里)奴国(博多)
とされている。奴国から東行百里で不弥国とあるが、不弥国の位置は不明である。
不弥国から先は行程の書き方が変わり、
不弥国→(南水行二十日)投馬国(不明)→(南水行二十日、陸行一月)邪馬台国
とされている。この読み方、解釈の仕方で、畿内説と九州説その他が、江戸時代の新井白石以来さまざまに論じられてきた。未だ決着はついていない。
別の角度からの見方もある。中国史の岡田英弘や渡邉義浩は、当時の魏の立場に立って「魏志倭人伝」の行程の記述を解釈している。229年に、魏は蜀を牽制して、洛陽から西方一万六千三百七十里にある大月氏(クシャーナ朝)の王波調ヴァースデ―ヴァを「親魏大月氏王」に叙した。「明帝紀」にこうある。
癸卯,大月氏王波調遣使奉獻,以調為親魏大月氏王。
(「魏書」巻3「明帝紀」 『中國哲學書電子化計劃』より)
その十年後の239年に、魏は呉を牽制して、倭の女王卑弥呼を「親魏倭王」に叙した。先に引用した卑弥呼叙爵の文と上の文を見比べると、同じ構文であることが分かる。魏は、対呉戦略上の必要から倭の女王を叙爵したわけだが、それは儒教の統治思想に基づくものでもあった。倭の女王国の存する方角とそこまでの距離は、洛陽から東南一万七千里でなくてはならなかった(地図8)。中国皇帝の徳が西方同様に東南にも及んでいなければならなかったからだ。
岡田・渡邉のこの説は、私にはとても説得力があるように思える。確かに、「魏志倭人伝」に、「会稽・東冶の東」(洛陽から見ると東南)、「帯方郡より女王国に至るまで一万二千余里」(洛陽から帯方郡までの五千里を足すと一万七千里になる。)とある。陳寿の記述のバイアスとはこういうことなのだろう。この見方に立てば、「魏志倭人伝」の行程の記述をどうこう斟酌しても意味はないということになる。不弥国から先の方角と距離の記述は辻褄合わせなのだから。
この見方に立つと、「魏志倭人伝」の記述からは、邪馬台国の日本列島内での位置は分からないということになる。結局、邪馬台国の位置は、決定的な考古学的発見がなされなければ決着しないと思われる。
(次回に続く)