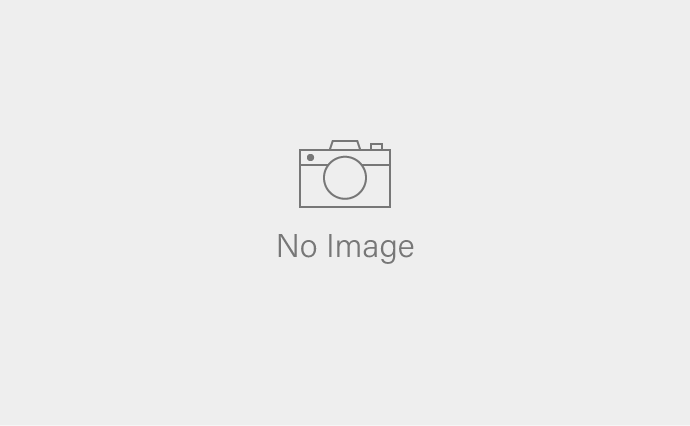2025年3月23日 直原裕naohara hiroshi
4 7世紀の人達が考えた邪馬台国
邪馬台国がどこにあったかは分からない。しかし、7世紀の人達が邪馬台国はどこにあったと思っていたかということについては、史料がある。「隋書」だ。隋使裴世清が608年に来朝し、小墾田宮で聖徳太子が出迎えたことは本ブログ第4回で紹介した。「隋書」に次のようにある。
魏の時、中国に訳通す[通訳を伴い来朝した]。(中略)其の国境は、東西五ヵ月の行、南北三ヵ月の行にして、各の海に至る。其の地勢、東は高く西は下し。邪摩堆に都す。則ち『魏志』に謂う所の邪馬台なる者也。
(中略)
明年[小野妹子が朝貢した大業三年の翌年608年]、上[煬帝]、文林郎裴清を遣わして倭国に使いせしむ。百済を度り、行きて竹島に至り、南に耽羅国[済州島]を望み、都斯麻国の、はるかに大海の中に在るを経。又東して、一支国に至り、又竹斯国に至り、又東して秦王国[不明]に至る。(中略)又十余国を経て、海岸に達す。竹斯国自り以東、皆倭に附庸たり。
倭王、小徳阿輩台を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ。後十日、又大礼哥多毗[額田部連比羅夫]を遣わし、二百余騎を従え郊労せしむ。既にして彼の都に至るに、其の王、清と相見て、大いに悦びて、(以下略)
(「隋書」、藤堂明保他訳)
帯方郡の使者が邪馬台国を訪れてから、隋使裴世清が小墾田宮を訪れるまで、360年経っている。その間中国の正使は倭国を訪れていない。裴世清は、派遣される前に「魏志倭人伝」を読み、基礎知識を得て準備しただろう。その裴世清が、自分の訪れた小墾田宮のある大和地域を、かつて卑弥呼が君臨していた邪馬台国の地であると、何の疑問も持たずに思った。裴世清の報告をもとに「隋書」(636年に成立)を書いた唐の歴史家魏徴も、邪馬台国のあった場所を、当然のごとく今倭国の都のある大和地域であると考えた。
「隋書」の記述から読み取れるのはこういうことだろう。7世紀の中国人は、邪馬台国は大和地域にあったと考えていたと。であれば、「隋書」を読んだ「書紀」編纂者も、邪馬台国は大和地域にあったと考えたに違いない。
5 「書紀」に卑弥呼も邪馬台国も登場しない理由
いよいよ本題だ。
「書紀」編纂者は、皇統に属さない卑弥呼の君臨する邪馬台国が、かつてこの大和の地に存在したと認識した。
一方、「書紀」編纂者は、聖徳太子の描いた建国の枠組を踏襲して、日本は推古九年から1,260年前に初代天皇が建国し、以後歴代天皇が万世一系で統治してきた国であるという歴史を記述することを、天武天皇に求められていた。
「書紀」編纂者にとって、卑弥呼も邪馬台国もあってはならない存在だったのだと思われる。建国の枠組を崩してしまうから。しかし卑弥呼も邪馬台国も無視することはできない。単純に否定することもできない。中国の史書に書いてあるから。
ここで「書紀」は何のために書かれたのか、確認しておこう。それは、何よりも中国皇帝に対して、日本が中国と同じだけ太古から、中国とは異なる正統性根拠をもって存在していること、中国と対等の関係にあることを主張するためだった。本ブログ第5回で述べた太子のビジョンだ。天武天皇とその勅命を受けた「書紀」編纂者は、太子のビジョンを受け継ぎ、それを「書紀」の中で実現しようとした。
そこで「書紀」編纂者は、中国皇帝に対して、中国史書に書かれている卑弥呼は、仲哀天皇の皇后であり応神天皇の母である息長足姫(神功皇后)のことだと主張することにしたわけだ。中国史書において、邪馬台国連合が倭国を統治していたとされる3世紀前半においても、天皇家が倭国を統治していたことにするために。
資料11をご覧いただきたい。これは、本ブログ第6回の資料10「『日本書紀』の枠組」に卑弥呼関連の事績を書き入れたものだ。「書紀」が引用した「百済記」に記載されていたと思われる百済肖古王からの七支刀献上、及び肖古王、貴須王、枕流王の薨去の記事も記入した。これを見ると、明らかに、卑弥呼と台与の記事は特例扱いとなっている。卑弥呼と台与は、建国の枠組による歴史引き延ばしの対象外とされた。中国史書に記載されているため、史実の年代のまま「書紀」に記載されている。卑弥呼と台与を神功皇后のことにするためだ。こうして「書紀」編纂者は建国の枠組を守った。
(出典)
・陳寿「三国志」(3C末)
・「魏書」巻30「烏丸鮮卑東夷伝」の「倭人」 藤堂明保他訳『倭国伝』(講談社学術文庫)
・「魏書」巻3 「明帝紀」 『中國哲學書電子化計劃』(ネット)
・魏徴「隋書」(本紀・列伝 636)
・巻81列伝第46「東夷」の「倭国」 藤堂明保他訳『倭国伝』(講談社学術文庫)
(参考文献)
・石母田正『日本の古代国家』(岩波文庫、原著は1971)
・吉村武彦『ヤマト王権』(岩波新書、2010)
・岡田英弘『日本史の誕生』(ちくま文庫、原著は1994)
・渡邉義浩『魏志倭人伝の謎を解く』(中公新書、2012)