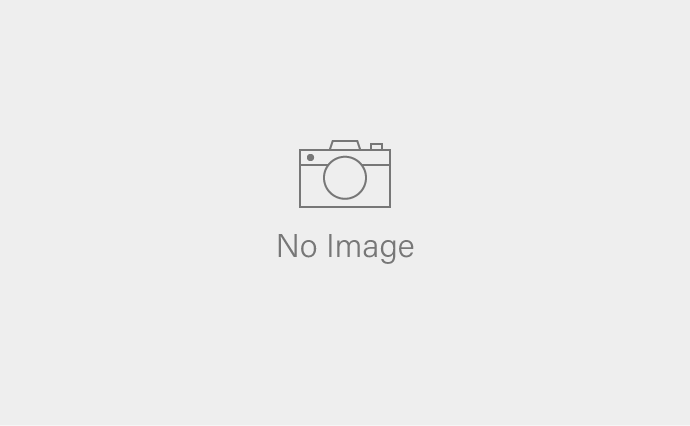2025年7月5日 直原裕naohara hiroshi
「日本書紀」を読むとたくさんの疑問、それも編纂上の理由から生じたと思われる多くの疑問が湧いてきます。本ブログ第6回に書いたとおりです。それらを解明することによって、「書紀」編纂者が採用した編纂方針はどのようなものであったのか考えていこうと思います。今回取り上げるのは出雲。ヤマト王権が国土平定を進める過程で、当時独自の勢力を有していた出雲の平定も行ったはずなのに、「書紀」編纂者はこれを神代の時代の国譲りとして描いています。なぜなのでしょうか。
1 大国主の国譲り
「書紀」神代第九段本文は、前後半別れていて、前半は葦原中国の平定(大国主から見れば国譲り)の話、後半は天孫降臨の話となっている。前半部分を要約すると次のとおりだ。
皇祖の高皇産霊尊は瓊瓊杵尊を格別に可愛がり、葦原中国の君主にしようと思った。そこで、その地にいる邪神を平らげるため、天穂日命を送った。しかし天穂日命は大己貴神*に阿り復命しなかった。このため、子の大背飯三熊之大人(武日照、建比良鳥)を送ったがこちらも戻らなかった。次に送った天稚彦も復命しなかったので、雉を送って様子を探らせた。天稚彦はこの雉を射殺した。その矢が高天原に飛んできたので、高皇産霊尊はこの矢を投げ返したところ、天稚彦に命中して死んだ。次いで高皇産霊神から指名された経津主神と武甕槌神は、出雲国の五十田狭の小汀(出雲市の稲佐の浜。写真8)に天降り、十握剣を逆さに突き立てその切っ先にあぐらをかいて坐って、大己貴神に国を譲るか問うた。大己貴神は自分の子に尋ねてから答えると返答した。大己貴神が子の事代主神に意見を聞いたところ、事代主神は国を献上するよう進言して退去した。そこで大己貴神は、国を平定した時に用いた広矛(統治権の象徴)を二神に授け、「私も国を譲って退去する。天孫はこの矛で無事に国を治めることができるだろう」と言って隠れた。二神は服従しない神々を誅殺して復命した。
神話というと、太陽や海、地の神同士の争いや恋愛の物語を普通想像するが、ここに描かれている話は全く異なる。政治臭が漂う。それは、争いの当事者が、一方は天界の神だが、他方は神と言いながら出雲という具体の土地の統治者だからだ。
さて、*のところで、高皇産霊尊が葦原中国に送った最初の使者である天穂日命は、大己貴神に取り込まれてしまったとある。なぜここで大己貴神が突然登場するのだろうか。「書紀」本文のこの部分の前に当る第八段本文末尾に、八岐大蛇を退治した素戔嗚尊が奇稲田姫と出雲の清地(「古事記」では須賀。島根県大原郡)で結婚し、大己貴神が生まれたとある。大己貴神は出てくるものの、それだけ読んで第九段本文に進むと、この場面でなぜ大己貴神が出てきたのか分からない。しかし直前に置かれた第八段一書第六に、大己貴命が少彦名命と協力して国作りをしたと書いてある。つまり、国作りをし葦原中国を治めている大国主神に対して、高皇産霊尊が国譲りをさせようと使者を送ったということだ。
「書紀」は、本文だけを読み継いでいくと話の脈絡が分からない。一書も併せて読んで初めて筋道が通るように編纂されている。
これに対して「古事記」は、大穴牟遅神が、八十神や須佐男命から課された数々の試練を乗り越えた後、国作りを行って大国主になったとしている。それに続けて国譲りの話が書かれているので、分かり易い。「書紀」と「古事記」の編纂方針の違いが、こうした所に現れている。
話を元に戻そう。この物語は、高皇産霊尊が皇祖とされ、大己貴神が出雲の神であることからすると、ヤマト王権と出雲の間に起こった歴史的事実を、神代の出来事として描いたものと考えてよいだろう。なぜそうしたのだろうか。
「書紀」によると、崇神天皇は、北陸、東海、西道、丹波にいわゆる四道将軍を派遣し、服従しなければ討伐するよう命じた。景行天皇は九州に親征し、土蜘蛛を誅殺し、熊襲を討伐した。日本武尊は熊襲と蝦夷を征討した。雄略天皇は吉備氏を討伐した。継体天皇は筑紫の磐井を平定した。これらはそのまま歴史的事実として記述されている。なぜ出雲だけ扱いが別なのだろうか。
まず、上に引用した国譲り神話の内容を検討しよう。国譲りを描いた物語は、この本文の他に、後で取り上げるふたつの一書と「古事記」がある。これまでの専門家の方々の研究によると、それらの中でこの「書紀」本文バージョン(国譲り神話①としよう。)が、いくつか後世の潤色は見られるものの、出来たのが最も古いとされている。留意点を挙げると、
- 大国主神に国譲りをさせる使者を送ったのは高皇産霊尊であった(後のバージョンでは、天照大神が使者を送ったとされている)。
- 高皇産霊尊は、初めから瓊瓊杵尊を葦原中国の君主にしようと思っていた(後のバージョンでは、天照大神と素戔嗚尊の誓約で生まれた天忍穂耳尊を降臨させようとしていたが、瓊瓊杵尊が生まれたので瓊瓊杵尊を降臨させたとしている)。瓊瓊杵尊(稲穂がよく実った様を想像させ、いかにも弥生時代的な名前だ)は、天皇家の始祖であるという伝承があったのだと思われる。
- 国を譲る相手である瓊瓊杵尊が天上から降ることを前提としている。つまり、天孫降臨神話は既に成立していた。
- 高皇産霊尊は国譲りを求める使者を何度も送ったが、いずれも大国主神に取り込まれてしまった。最終的にはあからさまに武力で脅して国譲りを受け入れさせた。現実の出雲平定は、それだけ交渉が難航し、その末に力ずくでなされたということだろう。
- 大国主神が高皇産霊尊の使者に広矛を差し出した。出雲の統治者がヤマト王権に対し、服従の証としてその統治のシンボルを差し出した事実があったのだろう。
- 出雲には最後まで国譲りに応じない神もいて、武甕槌神らに誅殺された。出雲平定に当り、実際に武力行使も一部にはあったということだろう。
- 杵築大社造営の話は出てこない(後のバージョンでは、国譲り交渉において杵築大社の造営が取引の条件として出てくる)。現実の出雲平定は最終的には力ずくでなされ、平定の後に、杵築大社が造営されたということだろう。
- この国譲り神話①は、天孫降臨神話が出来て以降で、まだヤマト王権が杵築大社造営を行っていない段階で成立したと考えられる。
2 出雲平定の記録
「記紀」において、出雲平定・国譲りは神代のこととされたが、「記紀」人代にもそれを窺わせる記述がいくつかある。列挙すると以下のとおりだ(「書紀」は井上光貞監訳の、「古事記」は武田祐吉訳の要約)。
天皇が群臣に、出雲大神の宮に収納してある、武日照命が天上より持ってきた神宝を見たいと言ったので、武諸隅を派遣した。神宝を管理していた出雲臣の遠祖出雲振根は筑紫国に出掛けており、留守を預かっていた弟の飯入根が神宝を献上した。戻った振根はこれを恨み、止屋(出雲市塩冶町)の淵で飯入根を騙して殺した。甘美韓日狭(振根のもうひとりの弟)と飯入根の子の鸕濡渟からこの件の報告を受けた朝廷は、吉備津彦と武渟河別*を出雲に派遣して振根を殺した。出雲臣らは畏まって暫くの間大神を祭らなかった。すると丹波の小児に託宣があったため、勅して大神を祭らせた。
*吉備津彦と武渟河別は、崇神十年に崇神天皇が派遣した四道将軍のうちの二人。吉備津彦は西道に、武渟河別は東海に派遣された。
天皇が物部十千根大連に、しばしば出雲に使者を送り神宝を検校させようとしたが不首尾だったので、自ら行けと命じた。十千根は検校して委細奏上した。そこで、十千根に神宝を掌らしめた。
天皇に、「我が宮を天皇の御舎のように修理すれば、御子(本牟智和気*)は物を言うだろう」との出雲の大神の祟り(託宣)があった。そこで曙立王と菟上王を付けて御子を出雲国に派遣し、出雲の大神を拝ませた。肥の河(斐伊川)の仮宮で、出雲国造の祖の岐比佐都美が御子に御食を献じようとした時、御子は、「この河の下に見えるのは、葦原色許男の大神を斎く祭壇か」云々と問うた。御供の王たちはこれを聞き歓んで、天皇に報告した。天皇は、菟上王を出雲に引き返らせて、神宮を造らせた(写真9)。
*本牟智和気(「書紀」では誉津別)は垂仁天皇の皇子。大人になっても言葉を発しなかった。大空を鶴が鳴き渡ったのを聞いて、はじめて「あぎ」と言ったとされる。
倭建が、肥の河の畔で、出雲建を騙して殺した。
これらの記述から次の点を読み取ることができる(参考:森公章「出雲地域とヤマト王権」)。
- 「出雲大神の宮」つまりは杵築大社が、このとき既に存在していた。
- 出雲臣の遠祖が、杵築大社において、神代に武日照命が天界から持ってきたとされる神宝を管理していた。
- 出雲は筑紫とも交流をもっていた。
- 出雲には、ヤマト王権との関係をめぐり意見の対立があり、内部抗争が生じた。
- 内部抗争の際にヤマト王権と手を結んだ勢力があった。
- ヤマト王権と手を結んだ勢力により、出雲の統治のシンボルである神宝がヤマト王権に引き渡され、出雲のヤマト王権への服従が定まった。
- 内部抗争の結果、出雲臣の遠祖は討たれた。
- 内部抗争の平定に吉備勢力も介入した。
- ヤマト王権への服従後、暫くの間、出雲臣は大国主祭祀を停止した。
- 大国主の祟りが発生した。しかも丹波で発生した。
- ヤマト王権は、祟りの広がりを恐れ、出雲臣に大国主祭祀を再開させた。
- 出雲平定後も、出雲は完全にヤマト王権に従属したわけではなく、ヤマト王権との軋轢は続いた。
- 大国主の祟りが続いたため、ヤマト王権は杵築大社の造営を行った。
以上の流れを整理すると、
出雲の内部対立に乗じ、ヤマト王権が出雲を平定
大国主祭祀の停止
↓
祟り
↓
大国主祭祀の再開
↓
ヤマト王権と出雲の軋轢継続
↓
祟り
↓
ヤマト王権による杵築大社の造営
とまとめることができる。出雲平定後、大国主の祟り(と当時の人々が受け止めた天変地異や疫病などの諸現象)が起き、これを鎮めるためにヤマト王権は杵築大社の造営を行ったと考えられる。「記紀」は、出雲平定から杵築大社造営までを、崇神朝から景行朝の出来事として記述しているが、この後5で述べる考古学的事実などからすると、それは恐らく4世紀後半から6世紀前半のことだろう。
3 国造りと杵築大社の創建
2において、ヤマト王権が出雲平定を行う以前に、杵築大社は存在していたと述べた。出雲平定の意味を考えるため、このことについて少し触れておきたい。
ヤマト王権への服従後大国主祭祀を停止すると祟りがあった、祭祀を再開しても祟りが収まらなかった、そのためヤマト王権が杵築大社を造営したということは、それ以前に、国造りの指導者大国主への信仰が人々の間に定着していたのだろう。であれば、その祭祀の拠点として社殿が築かれていたと考えてもおかしくない。2で取り上げた「書紀」崇神六十年条以外に、それを裏付ける記述が「古事記」と「出雲国風土記」にある。次のとおりだ。
大穴牟遲(大国主)を八十神が山に連れていき、大樹の切り口に楔で割れ目を作り、その割れ目に入らせ、楔を抜いて挟んで殺した。御祖の命(母の神)がその木を割いて大穴牟遅を助け出し、紀伊の国に逃がした。八十神は追いかけ矢をつがえたが、大穴牟遅は木の俣から逃れた。御祖の命が「須佐之男命の根の堅州国に行けば、大神が議ってくれるでしょう」というので、大穴牟遅は須佐之男命の御所に行った。大穴牟遅を迎えた女の須勢理毘売は父に、「大変麗しい神が来ました」と申し上げた。そこで大神が出て見て、「これは葦原色許男の命だ」と言い、呼び入れて蛇の室に寝かせた。大穴牟遅は須勢理毘売から蛇の領巾を授けられ、これを使って助かった。翌日の夜は、呉公と蜂の室に入れられたが、呉公と蜂の領巾を授けられ助かった。次は、大野原に射られた鏑矢を取りに行かされ、火を点けられた。火に囲まれ出る所が分からずにいると、鼠が出てきて隠れ場所を教えてくれた。隠れていると火は焼け終わり、鼠が鏑矢をくわえて持ってきた。須勢理毘売も大神も大穴牟遅は死んだものと思っていたところに、大穴牟遅は現れその矢を奉った。大神は大穴牟遅を家に連れて行き、大室に入れ、頭の虱を取らせた。頭には呉公がたくさんいた。須勢理毘売から授けられた椋の木の実を食い破り、同じく授けられた赤土を口に含んで吐き出した。大神は、これを、呉公を食い破り吐き出しているものと思い、感心して寝てしまった。大穴牟遅は、大神の髪をたる木(屋根を支える材木)に結び、大岩で戸を塞いで、須勢理毘売を背負い、大神の太刀と弓矢、琴を持って逃げようとした。その時、琴が樹に触れて音を立てた。大神が気づき、室を引き倒したが、髪を解く間に二人は逃げてしまった。大神は黄泉比良坂まで追い、遥かに望んで、大穴牟遅に、「汝が持てる太刀と弓矢で庶兄弟を追い払い、大国主の神となり、宇都志国玉の神(国土の神霊)となって、須勢理毘売を嫡妻とし、宇迦の山(杵築大社の東北にある御﨑山)の山本に、底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて居れ」と言った。こうして国作りを始めた。
楯縫の郡。(中略)楯縫と名づけるわけは、神魂神がおっしゃったことには、「わたしの十分に足り整っている天の立派な御殿の縦横の規模が、千尋もあるたく縄を使い、桁梁を何回も何回もしっかり結んで、たくさん結び下げて造ってあるのと同じように、この天の尺度をもって、天の下をお造りになった大神の住む宮殿を、造ってさしあげなさい」とおっしゃって、御子の天御鳥命(他に見えない。)を楯部(楯を作るのを職掌とした部曲)として天から下しなさった。その時天御鳥命が天から退き下っていらして、大神の御殿の神器としての楯を作り始めなさった場所が、ここなのだ。それで、今にいたるまで、楯や矛を造って、尊い神々たちに奉っている。だから、楯縫という。
杵築の郷。(中略)八束水臣津野命が国を引きなさった後に、天の下をお造りになった大神の宮をお造り申し上げようとして、もろもろの神々たちが宮殿の場所に集まって地面を固め(きづき)なさった。だから、寸付という。神亀三年(726)、字を杵築と改めた。
これらの記述は、ヤマト王権と無関係に杵築大社が創建されたことを物語っている。ヤマト王権に平定される前に、出雲には杵築大社はあった。弥生時代からあったのではないか。ただし、これらの神話に銅鐸が出てこないことから、青銅器祭祀が終了した後のことと考えられる。
杵築大社が創建されるさらに前に、国造りがあったはずだ。③では、国引き神話への言及がある。国引き神話は、詳しくは「出雲国風土記」意宇郡の部に書かれている。新羅や北陸などの余った土地を、八束水臣津野臣(「古事記」において須佐之男命の四世孫であり、大国主神の祖父とされる淤美豆奴神に当る。)が綱をかけて引き寄せ、三瓶山と大山を杭にして繋ぎ留めた。それで島根半島の土地が出来たとする話だ。地質学の研究によると、縄文時代には島根半島と中国山地は古宍道湖で分断されていた。それが、三瓶山の噴火による土砂が神戸川によって運ばれ堆積し、約2,000年前に出雲平野が出来て繋がったとされる(「出雲市歴史文化基本構想」2017。出雲市ホームページより)。国引きの物語は、弥生人の記憶が神話化したものではないだろうか。
弥生人はこうして出来た出雲平野で、治水、干拓、灌漑を行い、湿地を農地化して耕し、水田稲作に取り組んだものと思われる(地図9)。争い事の調整を含め、多くの困難を伴ったことだろう。その過程は、「記紀」でも「出雲国風土記」でも極く断片的に記されるだけだが、一定のビジョンの下、長期間の計画的で統率のとれた集団作業が必要だったはずだ。
国造りとはその集団作業であり、大国主と少彦名は共同体におけるその指導者だったのだろう。何代にもわたり、何人もいたであろう指導者が、この二人に仮託され、物語が集約されたのかも知れない。大国主には、困難に打ち克つ粘り強さと、民を愛し民から愛される人柄が表現されている。少彦名には難題を切り抜ける知恵とユーモアがある。「記紀」、とりわけ「書紀」の本筋に描かれた天津神とその子孫にはなかなか見られない指導者像だ。
杵築大社は、共同体総出で成し遂げた国造りを記念するとともに、指導者大国主への感謝を込めて創建されたものと思われる。
2でまとめた流れの前に、
国造り
↓
杵築大社の創建
というプロセスがあった。
(次回に続く)