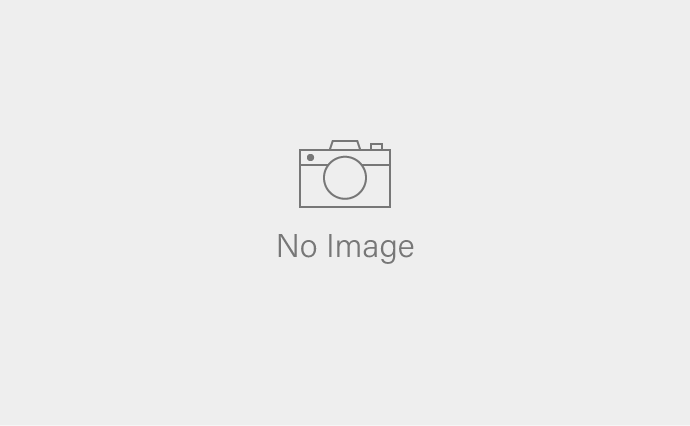2025年7月21日 直原裕naohara hiroshi
4 三輪山祭祀
ヤマト王権は、4世紀初め頃、奈良平野中央部東側に位置する三輪山の麓一帯を根拠地として成立した。以後多くの王がこの地に王宮を構えた。その三輪山の祭祀について、「記紀」にいくつか記述がある。ここでは、それらが出雲平定(大国主の国譲り)と関係はあるのか、あるとしてどのような関係があるのかを考えようと思う(写真10)。
まず「古事記」の神代。大国主が様々な試練を乗り越え(前回第9回ブログの3でその一部を紹介した。ひとつのビルドゥングス・ロマンだ)、さらに諸国を巡ってその地の姫を娶った話(出雲連邦とでも言えるような圏域を形成したということだろう)の後、国作りが語られる。
| 大国主が、御大(島根郡美保)の御前にいたときに、波の上から少名毘古那が現れた。それから二人でこの国を作り堅めた。その後、少名毘古那は常世の国に渡った。大国主は心憂く思って、「これからどの神と一緒にこの国を作ったらよいのか」と言った。この時、海上を照らして寄って来る神がいて、「私をよく祭れば、私が一緒に国を作ろう。そうしなければ国は成り難いだろう」と言った。大国主が「どのように祭ればよいか」と尋ねると、「私を倭の青垣の東の山の上に斎き祭れ」と答えた。これは御諸の山の上においでになる神である。 |
倭の御諸の山とは三輪山のことである。この物語は、大神神社の起源神話と言われている。
ともに国作りをしてきた少名毘古那が死に、これからどうやって国作りをするか大国主が出雲の海辺に立って悩んでいると、遠く離れた大和の三輪山の神が海上を照らして寄ってきて、大国主に助言し力づけたという内容である。出雲の神話としては、何とも無理のある筋書きではないだろうか。
三輪山の神を祭ることによって大国主の国作りが完成したとしている。ヤマト王権が、出雲の大国主より地元の三輪山の神の方が上である、大国主の国作りも最終的には三輪山の神のお陰であると言おうとしているように思われる。
三輪山の神の正体については何も述べていないが、明らかに大国主とは別神格とされている。
この物語はいつ頃できたのだろうか。ヤマト王権が成立したときには、大和の地でも大国主の国作り神話は広く知られていたはずだ。しかし大和の地では、それよりもっと古くから、三輪山は神奈備山として人々の信仰を集めていただろう。大和に人が住み始めた頃から、弥生時代どころか縄文時代から三輪山信仰はあったのではないだろうか。三輪山の神の正体が語られていないのは、名前の付いていない、人格神以前の自然神だからと思われる。大和の人々が、大国主の国作り神話にこの物語を付け加え、地元の三輪山信仰との関係を整理しようとしたのかも知れない。だとすると、この物語が成立したのは、ヤマト王権の成立後で、未だ出雲平定がなされていない段階ということになるだろう。
次は、①と同じく大己貴(大国主)の国作りを語る「書紀」神代第八段。本文ではなくて、一書第六にある。
| 大己貴が国を平定し五十狭狭の小汀(出雲郡稲佐の浜)にいたとき、海上から少彦名が現れた。それから二人で天下を経営した。また、療病の方法や、鳥獣昆虫の災異を禁厭で攘う方法を定めた。だから百姓(人民)は今に至るまで恩を受けているのである。大己貴から国作りの成果を問われた少彦名は、「できたところもあるし、できなかったところもある」と答えた。蓋し幽深い致(意味)がある。その後、少彦名は常世郷に去った。国の中のまだ出来上がっていないところを大己貴がひとりで廻って作り上げた。とうとう出雲国に至って「葦原中国はもともと荒れて広い国だ。盤石や草木にいたるまで狂暴である。しかしこの私が、これらをくだき伏せ従順にした」と揚言した。また、「いまこの国を作ったのは私ひとりだ。私と一緒にこの天下を作ることのできる者はいるだろうか」と言った。すると神々しい光が海を照らし、その中から忽然と浮かび上がってくる神がある。その神が、「私がいなかったら、どうしてお前ひとりでこの国を平定することができただろう。私がいたから大功をあげることができたのだ」と言った。大己貴は、「そういうお前は何者だ」と尋ねた。その神は、「私はお前の幸魂奇魂である」と言った(写真11)。大己貴は、「そのとおりだ。お前は私の幸魂奇魂である。今どこに住みたいか」と尋ねた。その神は答えて、「私は日本国の三諸山に住みたい」と言った。そこで大己貴は神宮を三諸に造営して、住まわせた。これが大三輪の神である。この神の御子は甘茂君たち、大三輪君たち、また姫蹈鞴五十鈴姫命である。これが神日本磐余彦火火出見天皇の后である。 |
少彦名の死後、大己貴が一人で国作りを完成させたとしている。
大己貴が国作りの完成を自負していると、神が海上からやってきて語りかけた。国作りを完成できたのは、自分の中にある幸魂奇魂のお陰であると。そのことに気づかされた大己貴は、自分の幸魂奇魂を三輪山に祭ったとしている。
幸魂奇魂とは、よく分からないが、魂の中に在る愛や知恵の霊力という意味だろうか。大神神社の起源神話であるとともに、何やら哲学的な話だ。
「古事記」の御諸山神話と似ているようで、大己貴の国造りが完了した後の話である点で異なる。さらに違うのは、大己貴の幸魂奇魂を三輪山に祭った、それが大三輪の神であるとしている点だ。つまり、大己貴と三輪山の神を同一神格としている。
大己貴の幸魂奇魂の求めで、大己貴が幸魂奇魂を三輪山に祭ったとしているが、祭った主体はヤマト王権だろう。ヤマト王権はなぜ大己貴を三輪山に祭ったのだろうか。それは、人民が恩恵を受けてきた大国主の故郷である出雲の国を、ヤマト王権が平定し、そのために起こった祟りを鎮めようとしたからではないだろうか。だとすれば、この物語は、ヤマト王権による出雲平定の後に、もとからあった「古事記」の御諸山神話を作り変えて出来上がったものと考えられる。さらに言えば、大国主が瓊瓊杵(ヤマト王権)に国譲りをしていれば大国主を三輪山に祭る必要はないと思われるので、この物語は国譲り神話ができる以前のものと考えてよいだろう。
甘茂(鴨)氏、大三輪氏、神日本磐余彦(神武)の后である姫蹈鞴五十鈴姫を、三輪山の神=大国主の系譜に位置づけている。
次は、「古事記」の人代(歴史時代)から。実際上ヤマト王権の初代の王と目される崇神の時代の物語として、三輪山祭祀が語られている。
| 疫病の蔓延を憂慮した天皇の夢に大物主神が現れ、「意富多多泥古に私を祭らせれば、神の気(祟り)が起こらず国も安平になるだろう」と言った。そこで意富多多泥古なる人を探し、河内の美努村で見つけ出した。天皇が「お前は誰の子か」と尋ねたところ、「大物主神が活玉依毘売を娶って生ませた子が櫛御方命、その子が飯肩巣見命、その子が建甕槌命、その子が私意富多多泥古である」と申した。そこで天皇はこの意富多多泥古を神主として御諸山に意富美和の大神をいつき祭った。疫病が息み、国家は安平いだ。 意富多多泥古が神の子と分かった所以は次のとおりである。活玉依毘売のもとに形姿威儀比無き壮夫が夜中に来て、共婚し住んでいるうちに幾何もないのに妊娠した。毘売の父母が怪しみその壮夫を知ろうとして、女に「赤土を床に散らし麻糸を針に貫いてその着物の裾に刺せ」と教えた。教えの通りにしたところ、朝になってみれば、針をつけた麻糸は、戸の鉤穴を通って出て、尋ね行くと、美和山に至り神の社に留まった。それで神の御子であると知ったのである。意富多多泥古命は、神の君、鴨の君の祖である。 |
この物語は、第一に崇神朝において意富多多泥古を神主として三輪山に大物主を祭るようになった謂われ、第二に意富多多泥古を大物主の子孫とする伝承、第三に神(三輪)氏、鴨氏の祖が意富多多泥古であることを記している。
大国主にも出雲にも全く触れていない。「古事記」では神代巻においても、上記①で述べたように、三輪山の神(大物主)を大国主とは別神格としている。従って、この物語は、大国主や出雲とは無関係と言ってよいと思われる。
次に、③と同じく人代における三輪山祭祀を語る「書紀」崇神紀を読む。
(七年条)
災害が頻発する原因を知ろうと、天皇は占いをした。すると倭迹迹日百襲姫命(崇神の大叔母)に神が乗り移り、「私を敬い祀れば平穏になるはずである。私は倭国の域内にいる神で、名を大物主神という」と言った。教えのとおりに祭祀をしたが、効き目はなかった。そこで天皇は沐浴斎戒して教えを乞うた。するとその夜の夢に一貴人が現れ、自ら大物主神と名乗り、「私の子の大田田根子に私を祀らせれば平穏になるはずである。また、海外の国も自ずと帰伏するに違いない」と言った。また、倭迹速神浅茅原目妙姫、大水口宿禰、伊勢の麻績君の三人が同じ夢を見て、「一貴人が現れ、大田田根子命を大物主大神の神主とし、市磯長尾市を倭大国魂神の神主とすれば、天下は太平になろうと言われた」と奏上した。そこで天皇は天下に布告して大田田根子を探し、茅渟県(和泉国一帯)の陶邑で見つけた。天皇は臨御し大田田根子に「誰の子か」と問うたところ、「父は大物主大神と申し、母は活玉依媛と申します」と答えた。天皇はこれを喜び、大田田根子を大物主大神の神主とし、長尾市を倭大国魂神の神主とし、さらに八十万の神々を祭り、天社・国社および神地・神戸を定めたところ、疫病は消滅し、五穀も稔った。
(八年条)
高橋邑(奈良市南部あるいは天理市北部)の人である活日を大神(大物主大神)の掌酒とした。
天皇は大田田根子に大神を祭らせた。この日に活日は自ら神酒を天皇に献じ、この神酒は倭の国を造られた大物主大神がお作りになった神酒であるという歌をよんで、神宮で宴会をした。天皇と諸大夫たちは、一晩味酒をのみ、宴会が終わると、朝になったら三輪の社殿の門を開いて帰ろうという歌をよんだ。そうして神宮の門を開いて帰った。大田田根子は三輪君たちの始祖である。
(十年条)
倭迹迹姫は大物主神の妻となった。その神は昼には現れず夜だけやってきたので、倭迹迹姫は「明朝にあなたの美しい容姿を見たい」と言った。大神はそれに答えて、「明朝にあなたの櫛笥に入っていよう。私の姿に驚かないでくれ」と言った。倭迹迹姫は朝になるのを待って櫛笥を見ると、美しい小さな蛇が入っていた。驚いて叫んだ。大神は恥辱を感じ、人の姿になって、「あなたは我慢できないで私に恥をかかせた。報復としてあなたに恥辱を加えるだろう」と言い、大空を舞って御諸山に登った。倭迹迹姫は後悔しながら急居した。そのとき箸が陰部に撞きささって薨じた。大市(桜井市北部)に葬った。だから時の人はその墓を名付けて箸墓という。この墓は、昼は人が作り、夜は神が作った(写真12)。
七年条は、大物主神が倭迹迹日百襲姫に乗り移り自分を祭れと告げたのでその通りにしたが効き目がなかった、次に大物主神が天皇他三人の夢に現れ子の大田田根子に自分を祭らせよなどと告げたので、その通りにしたところ天下は平穏になったという物語である。「古事記」では意富多多泥古を大物主の4世孫としていたが、こちらでは大田田根子を大物主の子としている。人代でありながら神代と繋がっている。「書紀」編纂者は、大田田根子を始祖とする三輪氏たちには、神性があり、神祇を職掌とする理由があると言いたいのだろう。
八年条は、杜氏の祖である活日の話。その活日がよんだ歌の中で、大物主を倭の国を造った神であるとしている。この「倭」が日本を指しているとすると、大物主とは大国主のことであり、大国主に感謝をささげていることになる。「書紀」は、神代第八段一書第六の冒頭で、大国主の別名を大物主としている(その他に、国作大己貴、葦原醜男、八千戈、大国玉、顕国玉を挙げている)。同じく一書第六では、上記②で述べたように、大己貴の幸魂奇魂を大三輪の神(大物主)としている。このように「書紀」の世界では、大物主は大国主と同一神格とされている。このことを前提にすると、「書紀」では、大物主を三輪山で祭るとは、大国主を祭っているのと同じということになる。そうすると七年条の物語は、崇神朝において災害が頻発し、ヤマト王権はこれを大国主の祟りと考え、祟りを鎮めるために大国主を三輪山に祭ったという意味になると考えられる。
尤も、活日の歌の中の「倭」が大和地方を指しているとすると、大和土着の神としての大物主への信仰がこの歌に表されていることになる。
十年条は、いわゆる箸墓伝説だ。大物主が女と交わり、蛇の姿になって三輪山に戻っていくというエピソードは「古事記」と共通している。しかし、その女が「古事記」では意富多多泥古の4代上の活玉依毘売であったのに対し、ここでは、崇神と同時代人で大叔母の倭迹迹日百襲姫となっている。七年条と同様、ここでも神代と人代が混交している。「書紀」編纂者は、倭迹迹日百襲姫の巫女性を際立たせるためにわざとそうしたのだろう。卑弥呼に擬したと思われる。
以上、「記紀」に描かれた三輪山祭祀の物語を読んできた。「古事記」①③からすると、ヤマト王権は、大和地方古来の神である大物主を三輪山で祭った、大国主の国作りも大和の大物主の力を得て完成したし、疫病の蔓延も大和の大物主を祭って鎮めることができたと考えたということになる。
一方、「書紀」②④からすると、ヤマト王権は、疫病が蔓延し災害が頻発するのは、出雲の大国主が祟っているためだと考え、大国主と同神格である大物主を三輪山に祭り、祟りを鎮めることができたと考えたということになる。
三輪山の神である大物主を、「書紀」は大国主と同一としているが、松前健は、もともとは出雲には関係のない、大和土着の神であったとしている(松前『出雲神話』p.153)。和田萃は、三輪山は4、5世紀には神奈備山として信仰され日神祭祀の祭場でもあったが、王権の東国進出に伴い三輪の神が軍神としての性格を持つようになり、さらに一旦三輪山祭祀が中断したのち6世紀中葉以降は、祟り神としての大物主を祭るようになったとしている(和田「三輪山祭祀の再検討」p.46)。
大物主はもともと大和地方の神であって大国主とは関係がなかったという説は説得力があるように思われる。「古事記」からもそのように読み取れる。とすると、「書紀」の世界では、出雲とは無関係で大和土着の神であった大物主を、わざわざ大国主と同じと見做していることになる。三輪山祭祀の意味が、土地の神への祈りから出雲の大国主への祈りに変えられている。なぜだろうか。出雲平定の祟りを鎮めるためであったと考えるのが妥当だろう。
(次回に続く)