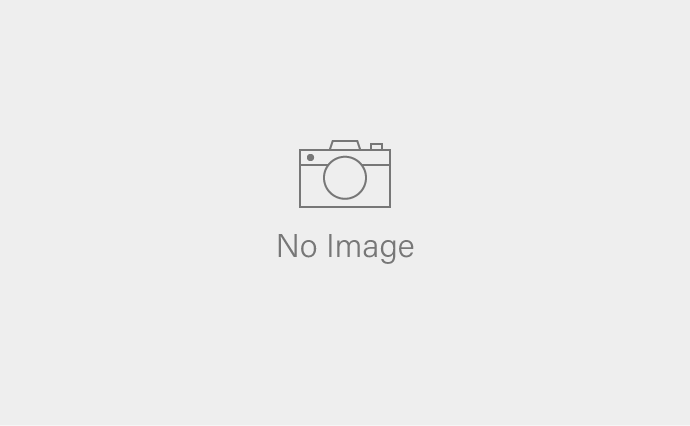2025年8月5日 直原裕naohara hiroshi
5 考古学的事実
前々回の1~3では、出雲における〈国造り→杵築大社の創建→ヤマト王権による出雲平定→祟り→ヤマト王権による大国主祭祀→祟り→ヤマト王権による杵築大社造営〉までの過程を、「記紀」と「出雲国風土記」の記述から追った。前回の4では、これと関係する大和における三輪山祭祀について、「記紀」の記述から考えた。ここではそれらを考古学的事実によって跡付けることができるか見てみる。
(1) 独自の文化形成と邪馬台国連合への参加
弥生時代中期末(1世紀前半)の山陰地域について、考古学の寺沢薫は、各地域の青銅製祭器の分析結果を踏まえ、近畿、北部九州、瀬戸内の勢力と一線を画した独自の社会を形成していたと論じている。そして出雲は他の地域に先立ち、いち早く青銅器祭祀を終えたとする。荒神谷での銅剣等の埋納を紀元前1世紀末、加茂岩倉での銅鐸埋納を後1世紀中頃と見ている(寺沢『王権誕生』p.188。埋納理由について寺沢は、前者は出雲の東部あるいは瀬戸内に対する呪禁、後者は後漢の冊封体制に入った北部九州に対する呪禁と推定しているが、その根拠が私には今一つよく分からなかった。)
出雲ではそれから100年もの間を置いて、2世紀から3世紀にかけて、四隅突出型墳丘墓と呼ばれる独自の王墓が築造されるようになる。後の令制国としての出雲国の西部に当たる出雲平野(出雲郡、神門郡)の西谷墳墓群、東部に当たる松江平野・安来平野(意宇郡)の仲仙寺墳墓群などが著名だ(写真13)。この形の墳墓は、山陰と北陸に広く分布しており、出雲を中心として、その政治的一体性の有無は不明だが、共通の文化圏が成立していたことが分かる。一般的には、北近畿にはないと言われているようだが、村井康彦はその著書『出雲と大和』において、丹波でも存在が確認されたとしている(p.60)。とすれば、日本海側一帯がひとつの圏域を成していたことになる。「古事記」神代に、大国主が諸国を巡りその地の姫を娶ったと記されている。四隅突出型墳丘墓の分布は、この話に対応していると考えてよいだろう。時代はもう「倭の大乱」と邪馬台国の時代だ。
「後漢書」は、後漢の桓帝・霊帝の治世の間、つまり146年~189年の間に、倭国で大乱があり、その後卑弥呼を王に共立し安定したとしている。7世紀になって編纂された「梁書」は、大乱の年代を絞り込んで、霊帝の光和年間178年~184年としている。いずれにせよ2世紀後半に倭国で大乱が起こり、2世紀末に邪馬台国連合が成立してその乱が終息した。
卑弥呼共立の主要な母体勢力は、早くから大陸文明の受け入れ窓口として発展し甕棺墓制や鏡・剣・玉の三点セット宝器を生み出した北部九州、瀬戸内海交通ルートをおさえ楯築墳丘墓や特殊器台・壺を作った吉備、朝鮮半島南部からの鉄供給ルートを確保した近畿(山尾幸久『新版 魏志倭人伝』による。ただ、考古学的な裏付けがあるのか良く分からなかった)、そして日本海交通ルートの拠点として四隅突出型墳丘墓を広めた出雲であったろう。纏向遺跡から出土した土器類や纏向型古墳の形状などから、邪馬台国連合はこれらの国の連合体であったと考えられる。卑弥呼は魏に朝貢使を送り、使者は魏の明帝から銅鏡を下賜された。それが三角縁神獣鏡と考えられ、邪馬台国連合参加国に配られた。出雲では、神原神社古墳(雲南市加茂町)から、景初三年(西暦239年)銘の三角縁神獣鏡が出土した(写真14)。出雲が邪馬台国連合に参加していたひとつの証と考えてよいと思われる。
ただし、「古事記」神代の根堅州国段や「出雲国風土記」に記された杵築大社創建を裏付ける考古学的事物は見つかっていない。
(2) ヤマト王権への抵抗と服従
「魏志倭人伝」によると、邪馬台国連合は、狗奴国(不詳)と対立する中、卑弥呼の死(248年頃)の後に一時乱れたが、宗女台与を王に立てて持ち直した。しかし、晋の武帝泰和二年(266年)の「倭人来献方物」という「晋書」の記録を最後に、邪馬台国連合は中国史書から消える。崩壊したのだろう。
御間城入彦五十瓊殖(崇神天皇)によって、大和地方三輪山の西南部を拠点として、現在の日本国に繋がるヤマト王権が成立したのは、4世紀初めと考えられる。宮内庁から崇神陵に治定されている行燈山古墳(天理市柳本町)の築造年代からの推定だ。「記紀」に神武東征の物語が記されているが、史実とは考えられない。邪馬台国連合崩壊から崇神即位まで、3世紀半ば過ぎから4世紀初めまでの間も、三輪山西南部で大型の前方後円墳の築造が続くからだ。戦乱の中で安定的に大規模土木工事が行われることはないだろう。ただし、崇神の出自も政権樹立のプロセスも実際のところ全く分かっていない。
ヤマト王権は、邪馬台国が始めた前方後円墳祭祀を踏襲した。当時、前方後円墳祭祀を支える信仰は、人々の心を強く捕えていて、ヤマト王権としてはこれを踏襲しないわけにはいかなかったのではないかと思われる。ヤマト王権は、勢力圏を広げるとともに当該地域の力に応じた大きさで前方後円墳を中心とした古墳を築造させた。都出比呂志(先月お亡くなりになりました。合掌)の言う「前方後円墳体制」だ。前方後円墳が築造されれば、その地域がヤマト王権の勢力圏に入ったことを示す。ヤマト王権との間で支配‐服従というほどの権力的関係が成立したとは思われないが、前方後円墳体制の中で明確な上下秩序が生まれただろう。
しかし出雲はなかなか前方後円墳を受け入れなかった。ヤマト王権としても無理やり直ちに出雲を勢力下に置こうとはしなかったようだ。「書紀」崇神十年条に、北陸、東海、西道、丹波に平定の将軍(四道将軍)を派遣したと記されているが、その対象に出雲は入っていない。山陰は丹波までで、その西には進んでいない。
出雲初の前方後円墳は大寺古墳だ(出雲市東林木町。写真15)。4世紀末築造と推定される。とすると、4世紀末頃、出雲はヤマト王権に平定されたと考えられる。出雲平定は、「記紀」神代では国譲りとして、「書紀」崇神六十年条では出雲振根の誅殺として描かれた。大寺古墳の築造は、これらを裏付けるひとつの考古学的な事実としてとらえることができるのではないだろうか。
(3) ヤマト王権による大国主祭祀
「書紀」崇神六十年条に、出雲平定後、出雲臣が大国主祭祀を停止すると祟りが起こった、このためヤマト王権は出雲臣に大国主祭祀の再開を命じたとあった。このことを示す考古学的事実はあるのだろうか。
出雲大社権宮司の千家和比古氏が次のように述べておられる。
「2000年の春、出雲大社境内の発掘調査で巨大柱による大型神殿遺構が出現し、世間の耳目は『高層神殿』に集中した。しかし他方で、刮目する新たな歴史情報を提供していた。四世紀後半の溝状遺構に伴う赤瑪瑙の勾玉・滑石の臼玉など祭祀的遺物の検出だ。刺激的なのは、古代国家揺籃期の畿内中央政権の発出による滑石製祭具の存在。四世紀後半という初現期の滑石製品を出土する祭祀遺跡は点的に極めて限定され、奈良県の三輪山祭祀遺跡、福岡県の沖ノ島祭祀遺跡、千葉県の小滝涼源寺遺跡が知られている。これらは国家経営上の拠点、海上交通の要路にあたり、国家経営に関わる枢要地で畿内から滑石製祭具が持ち込まれ祭祀が行われたようだ。境内出土の滑石製品もそうした祭祀痕跡となり、初期的祭祀に中央政権の関与が明瞭になった。小さい玉だが、意味するところは巨大柱に劣らず大きい」(千家「『出雲大社』の古代的断想」p.238)
出雲大社境内から、鎌倉時代の大社本殿の巨大な柱の一部が出土したことは私も知っていた。当時本殿の高さが48mあったことがそれでほぼ実証された。2020年に東京国立博物館で開催された展覧会で実物が展示されているのも見た。しかし、4世紀後半のものと見られる滑石の臼玉が同時に出土していたのは知らなかった。
大社町教育委員会の報告書「出雲大社境内遺跡」によると、鎌倉時代の大型本殿遺構が出土した拝殿北側の調査区の東端約50㎡の範囲で、古墳時代前期の遺物包含層が面的に検出された。そしてその中の幅80cmの溝の中から、「極めて重要な遺物が高い密度で」出土した。赤瑪瑙製勾玉1点と蛇紋岩製勾玉1点、滑石製臼玉12点、手捏ね土器1点である(同報告書p.88。資料12)。これらについて、同報告の考古学的所見をまとめた松尾充晶は、「臼玉の形態などから前期末ごろ〔4世紀後半〕に位置づけられる、祭祀用の遺物である」「現境内地における確実な祭祀行為の痕跡を、考古学的に実証しうる最初期の物証である」としている(同p.329)。ただし、これらがヤマト王権による祭祀の証拠であるとまでは言っていない。
大和地方に、ヤマト王権による大国主祭祀の痕跡はあるだろうか。前回ブログの4で述べた、大己貴(大国主)の幸魂奇魂の三輪山奉祭(「書紀」神代第八段一書第六)と、大田田根子による大物主(大国主)の三輪山奉祭(「書紀」崇神七年条)の痕跡だ。
三輪山の祭祀遺跡は、①山中の巨石群(辺津磐座、中津磐座、山頂の奥津磐座)、②大神神社拝殿裏の禁足地、③山ノ神遺跡、④狭井神社西方遺跡などがある(資料13(1)))。和田萃「三輪山祭祀の再検討」によると、この内②が最重要だが調査がなされておらず、全容が判明するのは③の山ノ神遺跡だけである。山ノ神遺跡の、1918年に発見されて以降の研究の歩みを、三沢朋美が「山ノ神遺跡の発見と古代遺跡」にまとめている。
この報告によると同遺跡は、大神神社の北、狭井神社の北東60mの地点、なぜか「出雲屋敷」と呼ばれる場所にある。同遺跡は発見当初古墳と思われたが、後に祭祀遺跡と判明した。銅製素文鏡、碧玉製勾玉、剣型鉄製品、滑石製臼玉、土製模造品、滑石製子持ち勾玉、須恵器など多数の祭祀遺物が出土している(資料13(2)はその一部)。これら遺物から、祭祀が行われた時期は、4C中葉~5C前半(銅製素文鏡、碧玉製勾玉、剣型鉄製品)と、5C後半~6C前半(土製模造品、滑石製子持ち勾玉、須恵器)の二つの時期と推測されている。
これらが、誰が何の目的で祀った遺物であるかについては、言及がない。遺物から直ちにそれを推定するのは難しい。ただ、出雲大社境内遺跡から出土し千家和比古氏が着目した滑石製臼玉が、ここでも遺物として見つかっていることに留意する必要がある。
和田萃によると、宗像沖ノ島の4C後半~5Cの遺跡からも滑石製臼玉が出土しており、ヤマト王権による祭祀跡と推定されている。4C後半というと、神功皇后と応神天皇の時代に当たる。神功皇后自身の実在性は疑わしいにしても、当時、ヤマト王権が朝鮮経営に乗り出し始めていたことは確かだ。沖ノ島は、北部九州から朝鮮半島に渡る経由地だった。この地で渡海の安全と朝鮮進出の成功を祈願したのだろう。
沖ノ島遺跡に照らすと、山ノ神遺跡出土の滑石製臼玉も同時期のヤマト王権による祭祀遺物と推定することが可能になる。そうだとすると、4C後半~5Cにヤマト王権は、出雲、宗像沖ノ島、三輪山の3か所で王権として祭祀を行っていたことになる。出雲では大国主の祟りを鎮めるため、宗像沖ノ島では朝鮮進出に成功するため、三輪山ではそれらすべての国家的願いを三輪山の神に祈ったと考えることができるのではないだろうか(地図10)。
(4) ヤマト王権による杵築大社の造営
ヤマト王権が大国主祭祀を始めても祟りは止まず、ヤマト王権は杵築大社を造営した。「古事記」の記述からはそう読み取れるのだが、これを裏付ける考古学的事実はあるのだろうか。
本ブログ第9回で、「古事記」垂仁天皇段の物言わぬ御子本牟智和気の逸話を紹介した。
垂仁天皇の夢に出雲の大神が現れ、「我が大宮を天皇の御舎のように修理めれば御子は言葉を発するだろう」と告げた。そこで天皇は本牟智和気を出雲に行かせ、大神を拝ませた。すると、斐伊川の川中に作った仮宮にて、アテンドしていた出雲国造の祖岐比佐都美に対し本牟智和気が、「この川下に青葉の山なせるは、山と見えて山にあらず、出雲の石くま〔「くま」は石偏に冋と書く漢字〕の曽の宮にいます葦原色許男〔大国主〕の大神を斎く大廷〔お祀りする斎場〕か」としゃべった。その報告を受け天皇は歓び、神宮を造らせたという話だ。
垂仁天皇は(と言っても、この話は実際にはずっと後代のことと考えられるが)どこに神宮を造らせたのだろうか。また、その前に大国主を祭っていた「石くまの曽の宮」はどこにあったのだろうか。
このことについて和田萃は、「石くまの曽の宮」とは、「岩陰の奥まったところの後方の宮」の意であり、杵築大社の現在の鎮座地と明らかに異なっているとして、斐伊川の当時の下流域(神門水海に注ぐ手前の神門郡塩冶郷)を挙げている(和田「出雲大社の成立」)。そうかも知れない。しかし一方で、「古事記」神代の根堅州国段で須佐男が大国主に向かって「宇迦の山の山本」(出雲郡宇賀郷の山の山裾)に宮を造れと叫んだこと、「書紀」神代の第九段一書第二で高皇産霊が「五十田狭の小汀」(稲佐の浜)にいる大国主に対し天日隅宮を造ってやろうと言ったことからすると、このときヤマト王権が造営した社殿はやはり現在地、「石くまの曽の宮」の場所はその背後の山の岩陰とも考えられるだろう。
出雲大社境内遺跡調査によって、(3)で紹介したように、4世紀後半の祭祀行為の跡は発見されたものの、当時の建物遺構が出たわけではない。これまでに発掘された最古の建物遺構は鎌倉時代のものだ。出雲大社境内も現在までのところ一部が調査されたに留まる。ヤマト王権による最初の大社造営地とそれ以前の大国主鎮座地が何処にあったかについては、出雲大社境内及び境内北側の山裾などが、今後本格的に調査されるのを待つ他ないようだ。
6 出雲臣系譜の形成
ヤマト王権が杵築大社を造営して以降は、杵築大社における大国主祭祀は出雲国造の仕事になっていく。それでは出雲国造に任じられる出雲臣の系譜は、どのようにして形成されたのだろうか。これを追うため、4世紀末以降7世紀前半、大化改新の前までの出雲の状況を、古墳を足掛かりにして見ることにする。資料14と地図11を参照されたい。
資料14に見るように、西部(主として出雲郡と神門郡)は円墳系、東部(主として意宇郡)は方墳系と異なる傾向がある。森公章「出雲地域とヤマト王権」の整理によると、西部地域では、出雲郡において4世紀末の大寺古墳以降、斐伊川下流域に築造された神庭岩船山古墳などヤマト王権との関係をうかがわせる伝承をもつ地に築造されるものが多かった。しかしその後出雲郡での古墳築造は衰退する。6世紀になると西部の中心は神門郡に移り、世紀中頃に大型の今市大念寺古墳が築造された。他方、東部地域の意宇郡では、5世紀中頃からその中心が安来平野から松江平野に移り、6世紀中頃に大型の山代二子塚古墳が築造された。
6世紀中頃の時点で、西部勢力と東部勢力は拮抗する状態にあった(写真16)。6世紀中頃というと、欽明天皇のもと地方統治制度の整備が進んだとされている。仁藤敦史「欽明期の王権と出雲」によると、ミヤケ制・国造制・部民制による内政の充実が図られ、これと並行して帝紀・旧辞の編纂を含めイデオロギー的な整備も行われた。
国造に任命するというのは、それまでまがりなりにも独立してその地域を治めていた豪族を、ヤマト王権がその統治を保証してやる一方で、ヤマト王権に服従させ、出仕やミヤケの設置などを受け入れさせることだろう。ヤマト王権は出雲地域において誰を出雲国造に任じただろうか。
6世紀中頃には既にヤマト王権によって杵築大社の造営がなされていたはずだ。それは、この頃に成立した帝紀・旧辞に、高皇産霊が大国主に対し国譲りの条件として「天日隅宮」の造営を提示した話が記されていたと考えられるからだ(「書紀」神代第九段一書第二。このことについては稿を改めて述べたい)。この話は、ヤマト王権が杵築大社を造営した事実を前提に成り立っている。
ヤマト王権にとって出雲国造に求める最重要の仕事は、杵築大社で祭祀を行い大国主の祟りを鎮めることだったはずだ。初めは杵築大社の所在地である出雲郡の族長である出雲氏に臣の姓を与え、出雲国造に任じたろう。出雲郡の勢力が弱まった6世紀中頃には、出雲氏と同族と言われる神門氏を出雲臣とし、出雲国造に任じて、杵築大社の祭祀を行わせたと思われる。
その後西部では古墳の築造は続くものの小型化し、勢力が弱まった。これに対して東部では、7世紀にかけて山代方墳など大型古墳の築造が続き、勢力維持が確認される。ヤマト王権は、東部の族長(注)に杵築大社の祭祀をさせることにし、出雲臣にした上で出雲国造に任じたと考えられる。
仁藤敦史によると、本来系譜を異にする西部と東部の氏族が、共通の祖として天穂日命の系譜を架上されて結合することになった。これを図示すると資料15のようになる。天穂日は、天照大神と素戔嗚尊の誓約によって、大王家の祖瓊瓊杵の父天忍穂耳と同時に生まれた神である。天神族のひとりだ。高天原神話は後に「記紀」において体系化が完成するが、帝紀・旧辞の段階でも一定の形は出来ていたものと思われる。その天穂日を祖神にしてもらうというのは、出雲東部の族長にとって、格別な栄誉だったはずだ。大王家と観念的に血族になるのだから。上で言及した「書紀」神代第九段一書第二に、高皇産霊が大国主に、「お前の祭祀をつかさどるのは天穂日命である」と言ったという話が出てくる。この一文も、東部の族長を出雲臣にするこの時に付け加えられたのだろう。
東部の族長は、西部の族長から出雲臣を引き継ぎ出雲国造となって杵築大社で大国主祭祀を行うというヤマト王権の求めに、それを重大な責務と認識しつつ、応じたことだろう。出雲臣の系譜が出来た。これにより、東部の族長は本拠地である意宇郡の熊野大社で祭祀を行う一方で、出雲国造として杵築大社で祭祀を行うことになった。ヤマト王権は、そうまでして杵築大社での大国主祭祀を続けようとした。国家的課題と位置付けていたからに違いない。
なお、本ブログ第9回で、出雲平定に関係する「記紀」の記述から、出雲内部に抗争があったと読み取れると述べた。この点について、かつて井上光貞が、東部の勢力がヤマト王権と結んで西部を平定したとの説を提起し、それ以降、西部内部の抗争に着目する説が出されるなど、専門家の方々の間で様々に論じられてきた。私はここでは、西部の内部及び東西関係において、事実として中心勢力の移動が見られることに基づいて、出雲臣系譜の成立過程を追った。内部の抗争とそれへのヤマト王権の関与が如何なるものであったかについては、今後考えていきたい。
(注)東部の族長 「書紀」仁徳即位前記に、屯田司をしていた出雲臣の祖として「淤宇(意宇)宿禰」の名前が出てくる。4C末~5C初めの頃に、東部の族長はヤマト王権に服属していたこと、出雲臣ではなかったことが分かる。
(本ブログ第9回~第11回の出典)
・「出雲国風土記」(733年、出雲国造兼意宇郡大領 出雲臣広嶋編纂)、荻原千鶴全訳注『出雲国風土記』講談社学術文庫
・「後漢書」(432年?、范曄著)巻85・東夷列伝、藤堂明保他訳『倭国伝』講談社学術文庫
・「魏志倭人伝」(3世紀末、陳寿著「三国志」より)、藤堂明保他訳、同上
・「晋書」(648年、房玄齢他著)帝紀第三世祖武帝、「中國哲學書電子化計劃」(ネット)より
・「梁書」(629年、姚思廉著)巻54列伝第48のうち東夷、「中國哲學書電子化計劃」(ネット)より
(本ブログ第9回~第11回の参考文献)
・松前健『出雲神話』講談社学術文庫、原著1976
・山尾幸久『新版 魏志倭人伝』講談社現代新書、1986
・森公章「出雲地域とヤマト王権」(『新版古代の日本4 中国・四国』角川書店、1992)
・和田萃「三輪山祭祀の再検討」「出雲大社の成立」(『日本古代の儀礼と祭祀・信仰 下』塙書房、1995)
・寺沢薫『王権誕生』講談社学術文庫、原著2000
・松尾充晶「考古学的所見のまとめ」(大社町教育委員会「出雲大社境内遺跡」(ネット)、2004)
・都出比呂志『古代国家はいつ成立したか』岩波新書、2011
・村井康彦『出雲と大和』岩波新書、2013
・仁藤敦史「欽明期の王権と出雲」(出雲古代史研究会『出雲古代史研究26』、2016)
・三沢朋未「山ノ神遺跡の発見と古代祭祀」(大神神社『大美和』第135号、2018)
・千家和比古「『出雲大社』の古代的断想」(吉村武彦他編『出雲・吉備・伊予』角川選書、2022)
(次回に続く)