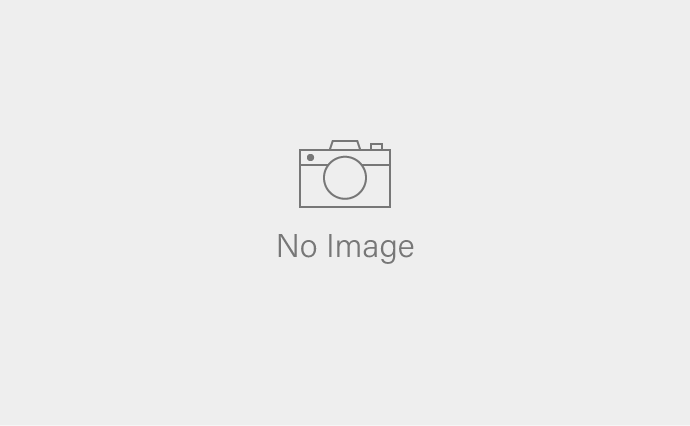2025年8月24日 直原裕naohara hiroshi
7 帝紀・旧辞編纂の時代
前回の6で、6世紀末から7世紀初めの頃以降、出雲東部意宇郡の族長が出雲臣とされ出雲国造に任じられて大国主祭祀を行うようになったと述べた。ここで少し時間を戻し、6世紀中頃に国譲り神話がどのような内容であったかを見ておこう。
(1) 欽明朝における史書と神話の整理
まず当時の史書編纂の動向から。「書紀」欽明二年(541)条に、欽明天皇の5人の妃とその所生の御子を説明したくだりがある。そこに、
「帝王本紀」にある多くの古い言い伝えは、撰集にあたる人がかわったり、後人が習い読むときにかってに改めたり、いくども伝写されているうちに錯乱を来たしたりして、前後の順序が失われ、兄弟がくいちがってしまっている。いま古今を考究し、真実の姿にもどした。
とある。「帝王本紀」なるものがあった。大王家の系図が以前から記録されてきており、この頃にその整理確認が行われていたのだ。これは、当時、後に帝紀・旧辞と呼ばれるようになる史書の編纂が始まっていたひとつの証拠と考えられている。
また、欽明十六年(555)条には、蘇我卿(稲目と思われる)の百済王子に対する発言として、
昔、天皇大泊瀬(雄略)の御世に、おまえの国は高麗(高句麗)に侵略され、累卵の危うきに到ったことがあった。その時天皇は、神祇伯に命じて、つつしんでその方策を神々からお受けになった。祝者(託宣を取り次ぐ神職)が神託として、「邦を建てた神をお招きし、滅びようとしている主の救援に赴くならば、必ず国家は鎮まり、人々も安らぐであろう」と告げたので、天皇は神をお招きして救援し、国家の安寧をえることができた。そもそももとをたずねると、邦を建てた神とは、天と地が割き分かれ、草木がまだものを言っているような時に、天から降って来て国家をお造りになった神である。聞くところによると、近頃おまえの国では祭祀をやめてしまっているというではないか。今後いままでの過失を悔い改め、神の宮を修理し、神の霊をお祭りすれば、国家は栄えよう。忘れないようにせよ。
とある。前年554年に、倭国に仏教を伝えた百済の聖明王が新羅軍に殺害されていた。そうした状況下での百済王子に対する言葉である。当時から80年ほど前、高句麗による百済攻撃で漢城が陥落し蓋鹵王が敗死した際に、時の雄略天皇が百済を支援した記録が朝廷に残っていたのだ。稲目の発言はそれに基づくものだ。ここには、後に「書紀」神代に描かれた天地開闢神話や天孫降臨神話の古い姿が見える。「邦を建てた神」とは高皇産霊のことだろうし、「神の宮」とは伊勢神宮のことだろう。雄略朝にそれらの神話と伊勢神宮が存在していたことを示している。それと同時に「書紀」のこの記述は、欽明朝時代の帝紀・旧辞編纂の中で、それまで代々伝わってきた宮廷神話の体系化が進められつつあったひとつの証拠と考えられている。
(2) 国譲り神話の更新
帝紀・旧辞編纂時代の国譲り神話に当たるのが、「書紀」神代第九段一書第二と考えられる(なぜそう考えられるかについては、稿を改めて述べたい)。国譲り神話②としよう。次のとおりだ。
天神(高皇産霊尊)は葦原中国平定のため経津主神と武甕槌神を派遣した。二神が、五十田狭の小汀に天降って大己貴神(大国主)にこの国を天神に献上するか問うた。すると、大己貴神は「私に従うために来たのではないか」と答えたため、天に返ってその旨報告した。高皇産霊尊は二神を出雲に返し遣わし、大己貴神に、「顕露のことは我が子孫に治めさせよう。おまえは幽界の神事をつかさどれ。おまえが今後住まう天日隅宮は余が作ってやろう。その敷地は千尋の規模で、宮殿は柱を高く太く、板は広く厚くしよう。御料田を供しよう。橋と天鳥船を作ってやろう。お前の祭祀を掌るのは天穂日命である」と勅した。大己貴神はこれを受け入れ永久に隠れた。経津主神は国内をめぐり、逆らう者は切り伏せた。帰順した首魁は大物主神と事代主神であった。この二神は八十万の神を集め引き連れて天に上り、忠誠を申し述べた。高皇産霊尊は大物主神に、「余の女の三穂津姫を娶せよう。八十万の神を率いて永久に皇孫を守り奉るがよい」と言い、地上に還り降らせた。そして紀国の忌部の祖先神である手置帆負神を作笠者と定めるなどし、太玉命(忌部の祖先神)に天孫に代わって大己貴神を祭らせた。また、天児屋命(中臣の祖先神)に太占(獣骨を焼いて出来たひび割れによる占い)の占法をもって仕えさせた。
以下の諸点に着目したい。
- 本ブログ第9回で取り上げた最も古いバージョンと思われる国譲り神話①(「書紀」神代第九段本文)には、初めに、葦原中国の邪神を平定するために、高皇産霊が天穂日、大背飯三熊之大人(武日照)、天稚彦を相次いで派遣したが上手く行かなかったという話があったが、ここにはそれがない。帝紀・旧辞編纂者(あるいは「書紀」編纂者)が、国譲り神話①と同じなので省略した、あるいは都合の悪い部分が含まれているので削除した(下記e.)と考えられる。経津主と武甕槌を送るところから始まっている。
- 大国主に国譲りを迫る主体は高皇産霊である。天照大神はまったく出てこない。この頃天界の主宰神はまだ高皇産霊だった。
- 国譲り神話①にはなかった杵築大社造営の話がここで出てくる。国譲りを渋る大国主に高皇産霊の方から、交換条件として、地上と幽界の統治の分担と、天日隅宮(杵築大社)の造営を提示し、大国主がこれを受け入れたとある。大国主の祟りを鎮めたいという、現実のヤマト王権側の立場の弱さが窺える。
- 高皇産霊が天日隅宮の造営を提示したという神話がこの時あったということは、現実に杵築大社の造営がヤマト王権によって既になされていたことを示すと考えてよいだろう。
- 天穂日が、国譲り神話①では、高皇産霊から邪神平定のため葦原中国に送られたにも拘わらず大国主に阿り復命しなかった使者として描かれていたが、ここでは、その描写がなくなり、高皇産霊から大国主の祭祀を命じられた神とされている。話の流れからすると、唐突感がある。これは、前回のブログで言及したように、6世紀末から7世紀初めの頃意宇郡の族長を出雲臣にし出雲国造に任じて大国主祭祀をさせるようにした時に、大国主に阿り復命しなかったという記述部分が削除され、大国主祭祀を命じられたという一文が付け加えられたためではないかと思われる。
- 大物主と事代主が地上の神々を率いて天に上り、忠誠を誓った。国譲り神話①には大物主は出て来なかった。三輪山で古くから行われていた大物主祭祀が、大国主の祟りを鎮める祭祀という意味を持つようになったので、大物主が国譲り神話に登場するようになったのだろう。また、事代主は、国譲り神話①では、高皇産霊の国譲り命令を聞き大国主に先んじて海中に退去してしまったのだが、ここでは大物主とともに天界に出向いて高皇産霊に忠誠を誓っている。高皇産霊に忠誠を誓うとは、天孫瓊瓊杵、引いては歴代天皇に忠誠を誓うということでもある。天孫への忠誠の誓いは、後述する出雲国造神賀詞の内容に繋がっていく。大物主と事代主が高皇産霊に忠誠を誓ったという話は、高皇産霊と大国主が統治の分担を決めた話からいささか逸脱しているように思える。以下に述べる「古事記」の国譲り神話③にもないことからすると、この話は、出雲国造による神賀詞奏上が始まって以降に、「書紀」編纂者によって付け加えられた可能性がある。
- 高皇産霊は大物主に自分の女を娶せた。神話上とはいえ天神族が大国主一族と血縁関係を結ぶまでして、大国主の祟りを鎮めようとした。ヤマト王権の危機感が窺える。
- 忌部と中臣の祖先神(手置帆負、太玉、天児屋)を登場させている。欽明朝において、この両氏が神事祭祀をつかさどる氏として重要な位置を占めるようになっていたことを物語っている。
8 大化改新後の出雲
(1) 律令制の導入と出雲国造の存置
7世紀に入ると大和朝廷は聖徳太子の時代だ。本ブログ第1~5回で取り上げたとおり、太子は仏教思想を根幹に据え、儒教に基づき天皇中心の律令体制の実現に向けて内政・外政の改革を開始した。太子は天神の子孫である天皇が万世一系で倭国を統治するという独自の統治の正統性原理を打ち立てたが、太子には神話の体系化を進める指向はなかったように思われる。太子が出雲とどう関わったか、記録からは見えない。
中国では618年に隋帝国が滅び、同年に唐が建国され更に強大な帝国として東アジアに出現した。唐に対峙して、朝鮮三国と倭国でほぼ同時期にそれぞれ体制変革が起こる。倭国では大化の改新だ。645年、中大兄皇子と中臣鎌足により蘇我本宗家が倒され(乙巳の変)、孝徳政権下、改新政策が実施された。「書紀」に記された諸政策がその通りに直ちに実施されたということではなく、この政策方針に基づいて最終的には文武朝の大宝律令(701)の頃までに段階的に実施された。それで漸く日本的な律令体制が成立したと考えられている。
改新政策の柱のひとつが、地方統治の方式を従来の国造制から国郡(大宝令以前は評)制に、部民制から公民制に改めることだった。各国に朝廷から統治責任者として国司(大宝令以前は惣領など)が派遣され、従来の国造は、祭祀権を失い、国司の下で地方行政官たる郡司(大宝令以前は評督)の職に就いた(吉村武彦『大化改新を考える』p.104参照)。
一般的にはこうなのだが、出雲では、国司が派遣され(写真17)その下で出雲臣は意宇郡司(郡領)に就くとともに、国造としても存置され祭祀権を保持した(いわゆる律令国造)。なぜか。大和朝廷からすると、出雲臣には杵築大社で大国主祭祀を継続してもらわないと困るからだろう。律令制導入に伴い国造が持っていた祭祀権を天皇に集中させたが、大国主祭祀に関してはそうはいかなかったということだ。
(2) 出雲国造への大社修造命令
「書紀」によると、斉明五年(659)、斉明天皇は出雲国造に命じて杵築大社を修造させた。文献上、年代の明確な杵築大社造営の記録としては、これが最古のものだ。原文では、
是歳、命出雲国造闕名修厳神之宮。
である(小字の「闕名」は、出雲国造の名は伝わらないの意)。この「神之宮」が何を指しているかについて、井上光貞は熊野大社だとした。これに対し、意宇郡を本拠とする出雲臣が熊野大社を修造するのは当たり前であって天皇が命ずるまでもない、天皇がわざわざ出雲国造に命じる以上その対象は杵築大社だとする専門家も少なくない。こちらの見解に依りたいと思う。
もう一点、「修厳神之宮」を「厳しの神の宮を修らしむ」と読む専門家も多い。これに対し村井康彦は、「厳は、荘厳であり飾ることであるから、修厳とは、神宮の社殿を以前より立派なものに作り上げたということであろう」と論じている(村井『出雲と大和』p.205)。この見解に依りたい。また、こう読むことで、杵築大社はこの時創建されたのではなく、それ以前から存在していてこの時に修繕あるいは建て直されたことがはっきりする。
このときの修造の目的についても専門家の見解が分かれている。一説は、当時、百済=高句麗連合と新羅=唐連合との対立が緊迫化していたことから、王権から見て西極の守り神として杵築大社を修造したという説。もう一つの説は、前年に建王が亡くなったのを祟りと考え、大国主を鎮めようとしたという説。建王は中大兄皇子と遠智娘の子で、斉明天皇の孫に当たり、斉明が寵愛していた。あの本牟智和気皇子と同じく言語に障害があったので、その死を大国主の祟りと考え、垂仁天皇と同じく大社造営を命じたとする説だ。どちらだろうか。出雲国造に命じた以上、目的は国家的なものであったはずと考えれば、前者になると思うのだが、どうだろうか。
さて、ここで重要なのは、杵築大社の修造を、大和朝廷が自ら行ったのではなく、出雲国造に命じて行わせたことだと思う。「古事記」垂仁段では、天皇は、本牟智和気が出雲大神を拝んだ後言葉を発したとの報告を受け、「菟上王を返して神宮を造らしめた」とあり、この時は朝廷が自ら修造した。出雲を平定した王権に対する大国主の祟りを鎮めるためなのだから、当然だろう。それが今回は出雲国造に修造させた。杵築大社の修造は、既に、出雲国造の責任において行うべき職務と位置付けられるようになっていたからではないだろうか。その結果、朝廷としては大国主の祟りを鎮めなくてはいけないという切迫感は薄れてきたように思われる。
「書紀」にはこの一文の次に、
狐が於友郡(意宇郡)の役丁(人夫)のもっていた葛(材木を引くためのつる)の端をくい切って逃げた。また、犬が死人の腕をくいちぎり、言屋社(意宇郡の揖屋神社)に置き去りにした。
と不吉な文が続く。杵築大社の修造のために、出雲臣の本拠意宇郡の人達は、お金も人手も多大な負担を強いられたと考えられる。その不満の表れなのだろう。出雲臣としては、律令体制下でも国造として存置され、祭祀権を認められるという恩恵を受けたが、一方で財政負担も求められた。天武朝の頃までには、意宇郡全体が熊野大社及び杵築大社のための神郡とされ、意宇郡からの収入は両大社の祭祀や修繕の費用に充てられるようになったとされている。出雲臣からすれば、出雲国の財政収入の一部を言わば特定財源化され、自由に使える一般財源をその分だけ減らされたのだから、こたえたのではないか。
9 「記紀」編纂の時代
(1) 「記紀」の編纂
唐・新羅連合軍に白村江の戦い(663)で大敗した後、引き続く対外危機を天智政権はしのいだ。天智の死後、壬申の乱(672)を制して即位した天武天皇は、唐と新羅の対立によって日本の対外緊張がゆるんだのを機に、天武十年(681)満を持して、律令制定命令など諸改革開始のGOサインを出した。そのひとつが、後に「日本書紀」のタイトルが付けられる史書の編纂命令だ。「書紀」に、
令記定帝紀及上古諸事
とあり、命ぜられた川嶋皇子、忍壁皇子ら12人の皇族、重臣の名が列挙されている。「書紀」は朝廷内に編纂委員会が設けられ組織的に編纂された。「続日本紀」によると、それから39年後の720年に完成し、元正天皇に奏上された。まだ、ひらがな・カタカナは生まれていない。万葉仮名を用いて記された歌などを除き、基本的には正格漢文で書かれている。中国人が読めば中国語として読むし、日本人が読めば漢文訓読して日本語として読む。
「古事記」編纂については、「書紀」に全く記載がない。経緯は太安万侶が書いた「古事記」序文に、
天皇(天武)詔したまひしく「朕聞かくは、諸家のもたる帝紀と本辞と既に正実に違ひ、多くの虚偽を加ふといへり。(中略)故ここに帝紀を撰録し、旧辞を討覈して(調べて)、偽りを削り実を定め、後葉に流へむと欲ふ」と宣りたまひき。
とある。まるで天武天皇が「書紀」編纂を命じた朝廷会議に太安万侶も陪席していたかのようだが、そういうことではないだろう。ただ、「古事記」も「書紀」と同時に編纂が始まったと考えてよいと思われる。こちらは、舎人の稗田阿礼に「帝皇の日継と先代の旧辞とを誦み習はしめ」るという個人作業方式だ。
阿礼は、「目に度れば口に誦み、耳に払るれば心に勒す(目で見たものは口で読み伝え、耳で聞いたものはよく記憶する)」ことが出来た。橋爪大三郎によれば、帝紀・旧辞に漢字で書かれた記録類を、一般の人は漢文訓読方式で読むことしかできなかったが、阿礼には古言(漢字が入ってくる前の日本語)で読む能力があったということだ(橋爪『小林秀雄の悲哀』p.200,282)。安万侶は、その古言のかたちを書き留めようと、変格漢文で「古事記」を書いた。序文にこうある。
已に訓に因りて述ぶれば、詞は心に逮らず。全く音を以ちて連ぬれば、事の趣更に長し。ここを以ちて今或るは一句の中に、音と訓とを交へ用ゐ、或るは一事の内に、全く訓を以ちて録しぬ。(漢字を使って述べてみると、どうも心に思っていることが十分にあらわされていない。そこで、漢字の音だけを借りる方式で述べてみると、恐ろしく文章が長くなってしまう。困った挙句、この『古事記』は、表意文字としての漢字に、音だけを借りた漢字を交ぜて書くことにします。また、事柄によっては表意文字としての漢字を連ねて書きます。 : 山口仲美訳)
このため、それからおよそ1,100年後、本居宣長が「古事記伝」において「古事記」に残された古言を読み解くことになる。
序文によると、作業の中断を経て、和銅四年九月に元明天皇から安万侶に対し、「稗田阿礼が誦める勅語の旧辞を撰録して献上せよ」との命令があった。既に「書紀」は完成に近づいていたと思われる。元明天皇は「古事記」に「書紀」とは別の価値を認めていたのだろう。それから僅か4か月後の和銅五年(712)一月に安万侶から奏上された。如何に優秀な安万侶とて、とても4か月でまとめられる内容ではない。元明天皇の命令以前から、安万侶は阿礼と編纂作業を進めていただろうし、もしかしたら安万侶の側から元明天皇に編纂命令を出してもらうよう働きかけたのかも知れない。
元明からの命令も元明への奏上も、「続日本紀」に記載がない。中国文明の導入イコール日本の文明化と考えていた正史編纂チームの人達にとって、「古事記」編纂は重要事項ではなかったのだろうか。
「書紀」と「古事記」とでは、歴代天皇の名前と順序など基本的な認識はすり合わせがなされているが、編纂方針には違いがある。元資料の帝紀・旧辞に含まれていたと思われる相異なる伝承を、「書紀」は、神代の神話については本文の他に「一書」として、人代の史実については「一説には」とか「『百済記』によれば」といった形で併記あるいは注記している。だから神代を通読すると、前段の一書から後段の本文に話が繋がっていたりする。ギクシャクしているが、お陰で神話が変化した過程を推定することができる。これに対し「古事記」は、太安万侶が各段で一つの伝承を採用し、それらを巧みに繋ぎ合わせているので、全体として整合性のとれたストーリーに仕上っている。
天武天皇は「書紀」と「古事記」の二つのプロジェクトを同時にスタートさせた。前者は、中国皇帝に対し日本国の独自性を主張できる、国際的スタンダードに基づく史書を目指す。後者は、国際的スタンダードに合わせると埋もれてしまうであろう古言を用いて史書を書き、日本国民に残すことを目指したのだろう。両方を進める所に、天武天皇の思考の奥深さがあるように思う。元明も叔父天武の思考をよく理解したのだと思われる。元明はさらに、「古事記」奏上の翌年(713)、諸国に風土記の提出を命じている。日本古代の文化の諸相が現代に伝わったのは、元明の識見によるところが大きい。
(2) 太安万侶がまとめた国譲り神話
国譲り神話は時代とともに変化した。「書紀」はその各時代のバージョンを残したが、「古事記」の国譲り神話は、奏上された712年時点で太安万侶がこれだと考えた完成形といってよいだろう。国譲り神話③とする。次のとおりだ。
天照大御神が、「葦原瑞穂の国は我が子の天忍穂耳命が治めるべき国である」と言い、天から降らせた。天忍穂耳命が地上を見ると騒がしいので報告すると、思金神らの進言を受け、高御産巣日神と天照大御神は、天菩比神を平定のため降らせた。天菩比神は大国主神にへつらい復命しないので、次に天若日子を送った。天若日子は大国主神の女の下照姫を妻とし復命しなかった。そこで天若日子が留まっている理由を調べに雉を遣ったところ、雉は天若日子に射殺された。その矢が天上の高木神(高御産巣日神の別名)のもとに届いたので、衝き返したら天若日子に当り死んだ。
天照大御神は次に建御雷神に天鳥船神を副えて送った。この二神は出雲国の伊耶佐の小浜に降り、十掬剣を波の上に逆さに突き立て、その切っ先にあぐらをかいて、大国主神に「天照大御神と高木神の使いで来た。葦原中国は我が御子が治めるべき国であるとの命令があった。どう考えるか」と問うたところ、大国主神は「子の八重事代主神が返事申し上げるべきだ」と答えた。それで天鳥船神を遣わし八重事代主神を呼んで尋ねると、「この国は天神の御子に献上なさいませ」と答えて隠れてしまった。これを大国主神に伝え、他に申すべき子はいるか問うと、大国主神は、建御名方神がいると答えた。すると建御名方神が現れ、建御雷神に力比べを申し込んだ。建御雷神は建御名方神の手を掴みひしいで投げ飛ばした。逃げる建御名方神を追って、信濃国諏訪で殺そうとすると、建御名方神は降参した。これらを大国主神に報告すると、大国主神は、「葦原中国は仰せのとおり献上しましょう。ただ、私の住所を、天つ神の御子が帝位にお登りになる壮大な宮殿の如くに、底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりてお作りくださるなら、私は所々の隅に隠れておりましょう。多くの子神も八重事代主神を指導者にすれば背きはしません」と申した。それで出雲国の多藝志の小浜に天の御舎を作った。
私が着目する点は次のとおり。
- 大国主に国譲りを迫る主体が、天照大御神となっている。最も古いバージョンの国譲り神話①及び帝紀・旧辞時代の国譲り神話②では、主体は高皇産霊だった。大きな変化だ。葦原中国に使者を送る判断は高御産巣日と連名で行っているが、基本的には天照大御神を中心に話が組み立てられている。
- 天照大御神は、自分の子の天忍穂耳が葦原中国を治めるべきだと主張し、天忍穂耳を天降らせた。邇邇芸命はこの場面に出てこない(国譲りの後、改めて天忍穂耳を天降らせようとしたら邇邇芸命が生まれたので邇邇芸命を天降らせることになる)。国譲り神話①では高皇産霊が瓊瓊杵を可愛がり初めから瓊瓊杵を葦原中国に降臨させようとしたとあったが、この場面ではこちらの方が話の流れからすると自然だ。
- 高天原の神が葦原中国の邪神を平定するために次々に使者を送るが上手く行かない話は、国譲り神話①と同じ。違うのは第一に使者を送る主体が高御産巣日と天照大神の2人になっていること(国譲り神話①では高皇産霊1人だった)、第二に使者が天菩比、天若日子の2人であること(①では天穂日、武日照、天稚彦の3人)である。
- 天照大御神は最終的に建御雷神と天鳥船を地上に送った(国譲り神話①②では、高皇産霊が経津主と武甕槌を送った)。経津主が消えたのは、経津主が、崇仏廃仏論争の末用明天皇没後に排除された物部氏の祭神だったからと思われる。
- 国譲りに抗う神として、建御名方が描かれている。建御名方は信濃国諏訪(もと出雲の勢力圏だったと考えられる。)で降参した。国譲り神話①②にも服従しない神々は誅殺されたとあるが、建御名方は登場しない。実際の出雲平定において、一部に武力による抵抗がありヤマト王権によって鎮圧されたことを、太安万侶は国譲り神話の中にはっきり残しておこうとしたのだと思われる。
- 杵築大社の造営は、国譲りの条件として大国主が言い出したことになっている。国譲り神話②では、高皇産霊が交換条件として提示していた。国譲り神話②の6世紀中頃の時代に比べ、王権の立場が強くなっているのが窺われる。杵築大社の造営が出雲国造の職責に位置付けられ、大国主の祟りを鎮めることに対する王権の責任が弱まったことが、その背景にあると考えられる。
- 杵築大社が造営されたと記されている。これはヤマト王権による造営、出雲国造による修造が実際に行われたので、神話の中に国譲りの結果として書かれたものだ。
(3) 「書紀」最終形の国譲り神話
「古事記」奏上から8年後の養老四年(720)、舎人親王から元正天皇に「日本書紀」(「続日本紀」には、「日本紀」と記されている)が奏上される。その神代第九段一書第一に記された国譲り神話が、「書紀」における最終バージョン、「書紀」編纂時代の人々が考えていたものと思われる。これを国譲り神話④としよう。要約すると次のとおりだ。
天照大神が天稚彦に、「豊葦原中国は我が御子が君主たるべき国である。邪神たちがいるので平定せよ」と命じた。天稚彦は中国に降ったが、国神の女子をたくさん娶って復命しなかった。天照大神が思兼神の進言で、問責のため雉を派遣したところ、雉は天稚彦に射殺された。その矢が天神の元に達したので、天神が投げ返すと、天稚彦に当って死んだ。天照大神は天忍穂耳を降らせたが、天忍穂耳は天浮橋から国がまだ乱れているのを見て天上に返り、降れなかった状況を報告した。そこで天照大神は、武甕槌と経津主を派遣して、まず悪神たちを駆除した。次に二神は出雲に降り、大己貴神にこの国を天神に献上するか問うた。大己貴神は、「子の事代主神に尋ねてから返事する」と答えた。大己貴神が使者を送って事代主神にはかると、「天神の求めにどうして背きましょう」との答えだった。大己貴神はこれを二神に報告した。二神は天に上って「葦原中国は平定し終えた」と奏上した。
着目点は次のとおり。
- 大国主に国譲りを迫る主体が天照大神となっている。国譲り神話①②では主体は高皇産霊であったが、替わった。これは、天界の主宰神が替わったことを意味している。記紀神話の中核をなす天孫降臨神話に変更があったため、それに合わせて国譲り神話が修正されたと考えられる。この点については、今後、天孫降臨神話をテーマに取り上げるときに、改めて考えていきたい。
- 天照大神は葦原中国の邪神を平定するため、はじめに天稚彦を送る。国譲り神話①に登場した天穂日とその子武日照は出てこない。出雲臣の祖神を天穂日としたため、邪神平定に失敗する天穂日と武日照を描くのを控えたものと思われる。
- 復命してこない天稚彦を探るために派遣された雉を、天稚彦は射殺する。その矢が天界の天神の元に届く。天神が投げ返した矢が天稚彦に命中し、天稚彦は死ぬ。天神はこの場面にだけ登場する。主役ではなくなっている。
- 天照大神は、豊葦原中国はわが御子が君主たるべき国であるとして、天忍穂耳を天降らせる。この場面に瓊瓊杵は出てこない。「古事記」と同じである。国譲りを求める主体を高皇産霊から天照大神に変更した以上、国譲り神話①のように天降らせるのをはじめから孫の瓊瓊杵にするのは不自然なので、子の天忍穂耳をまず天降らせるように修正したものと思われる。(その結果、国譲りの後、改めて天忍穂耳を天降りさせようとすると、孫の瓊瓊杵が生まれたので瓊瓊杵を天降りさせることにするという、奇妙なストーリーの天孫降臨神話になってしまう。)
- 天照大神は、天忍穂耳から葦原中国が乱れていて降れなかったとの報告を受け、武甕槌と経津主を派遣して悪神を駆除する。武甕槌と経津主を送るところは国譲り神話①②と同じだが、送る主体が高皇産霊(天神)ではなく天照大神に替わっている。主宰神変更のためだ。
- 武甕槌と経津主は大国主に対し、この国を天神に献上するかと迫る。大国主から意見を聞かれた事代主は、天神の求めに背くことはできないと答える。この場面では、天界の最終的な責任者は、やはり天神高皇産霊とされている。世界を主宰するのは天照大神だが、その背後に最終的な責任者として高皇産霊が存在している、天界の布陣はそのように考えられているようだ。
- 大国主は、天神の求めに応じるとの事代主の意見を聞くと、その通りに武甕槌と経津主に返答し、出雲平定はあっさりと終わる。杵築大社造営の話は出てこず、国譲り神話①の形に戻っている。現実において杵築大社の修造が出雲国造によって行われるようになり、最早国譲り神話に残すまでもなくなったようだ。大国主の祟りを鎮める責任が王権に問われる状況ではなくなっていたものと思われる。
- 国を天神に献上した後に大国主がどうなったかも書かれていない。王権にとって、大国主の位置づけが、祟り神から変わったものと考えられる。どう変わったか、次に「出雲国造神賀詞」を見ることにする。
(参考文献)
・吉村武彦『大化改新を考える』岩波新書、2018
・橋爪大三郎『小林秀雄の悲哀』講談社選書メチエ、2019
・山口仲美『日本語の歴史』岩波新書、2006
(次回に続く)