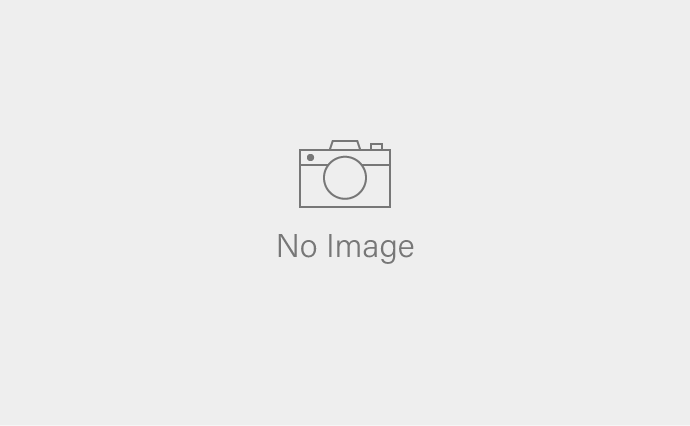2025年9月26日 直原裕naohara hiroshi
9 「記紀」編纂の時代
(4) 出雲国造による神賀詞の奏上
ア 神賀詞奏上とは
かつて井上光貞は次のように述べた。
「わたくしは、『旧辞』がつくられたはじめから、出雲平定の構想はふくまれており、そして、それはこのころより以前、あまり遠くないころに、出雲が大和朝廷にとって大きな敵対勢力であったためであると理解したいのである。
それなら、この大和と出雲との関係は、歴史的にはどんなものであったろうか。残念なことに、それを示す記録は一つも残されていないのだが、間接的な証拠として見逃してならないのは、おそくとも奈良時代に、出雲の国造だけがその就任のときごとに朝廷に参向して、一種の儀礼をおこない、いわば服属の誓詞ともいうべき賀詞を奉るならいのあったことである」(井上『神話から歴史へ』p.98)
「続日本紀」によると、「古事記」奏上(712年)と「書紀」奏上(720年)の間の霊亀二年(716年)に、出雲国造の出雲臣果安が、前年に即位した元正天皇に平城宮にて神賀詞を奏上した。国史(正史のほか、「類聚三代格」など)に記された出雲国造神賀詞奏上はこれが初となる。以後833年まで、8世紀中は天皇の即位や遷都の際に、9世紀になると出雲国造の就任儀礼として、計15回行われた記録が国史に残る。その後も行われたと考えられるが、位置付けが国造就任儀礼になったことで国史に記録されなくなったとされる(大日方克己「古代の出雲」p.173)。
神賀詞の内容は、「延喜式」(927年完成)に記され、現代に伝わった。「延喜式」に記された神賀詞がいつ奏上されたものであるかは明らかでないが、その中に言及されている出雲国の全官社数が186とされていることから、ある程度の推定は可能だ。山田孝雄によると、733年編纂の「出雲国風土記」では官社数184であること、「延喜式」では187であるが最後に天穂日命神社が官社に列せられたのが天安元年(857年)である(「文徳実録」による)ことから、その間ということになる。
ただし、山田孝雄は、
「すべて『延喜式』巻八に載する祝詞はいづれもその祭祀や神事の創始の時に奏した詞をいつまでも守るのが例であると思ふ」「かやうに祝詞は専ら古例を重んじたものであるから、この神賀詞奏上の事が行はれはじめてより後、その時代々々に時世の必要上一部の変更は止むを得ないであらうが、新に製することは無かったであらう」(山田孝雄『出雲国造神賀詞義解』p.281)
と論じ、官社数以外は基本的に創始の文面をそのまま残しているとしている。そうなのだろう。
奏上に至るプロセスと方式は、大津透によると、
ⅰ 太政官において、大臣が国造名簿を賜い、国守と任人(国造に任じられる出雲臣当人)が参入し、弁大夫が国造任命の宣命を宣する。神祇官に移り、負幸物(大刀)その他の品々を賜る。
ⅱ 国造は出雲に帰り潔斎一年、その間出雲の神々を祀る。その後国司は国造以下祝部(出雲国内全官社の神官約180人)・郡司・子弟を率いて入京する。神宝と御贄をたてまつり、大極殿に天皇が臨席し、国造が神賀詞を奏上する。
ⅲ 出雲に帰り、後の潔斎一年ののち再び入京し、神宝と御贄を捧げ、神賀詞を奏上する。
である(大津『古代の天皇制』p.66)。二年に及ぶ大掛かりな儀式だ。
イ 神賀詞に述べられていること
律令制完成時の大和朝廷と出雲の関係がここに表れているので、読んでみよう。山田孝雄による読み下し文を資料16に、同氏の現代口語訳に基づく要約を以下に掲げる。
(山田孝雄による口語訳から修飾、強調、決まり文句などを外し要約した。)
今日の良き日を選んで、出雲国造某が恐み申し上げます。
(第一段落)
明つ御神として大八嶋国を治める天皇陛下の御世が長久の御世でありますようにとお祈りし、熊野大神と大穴持命の二柱の神をはじめとする出雲国の186社に坐す皇神たちを、この国造某が一年間忌い静めてまいりまして、今日朝日の昇るこの時に、復命の神賀の祝い言葉を申し上げますと奏上いたします。
(第二段落)
高御魂命は、皇御孫命(瓊瓊杵尊)に大八嶋国の政事を寄託した際に、出雲臣の遠祖天穂比命を国の形勢の視察に遣わしました。天穂比命は、豊葦原瑞穂国は荒ぶる神が騒ぎまわり乱れているのを見て、これを鎮め平穏に治められるようにするため、子の天夷鳥命に布都努志命を副えて天降らせました。天夷鳥命は、暴威を振るう神どもを撥い帰順させ、国作りをした大穴持命をもなだめ鎮めて、現世の政事を譲らせました。
そのときに大穴持命の言うことには、大倭国は皇御孫命の静まり坐すべき国であると申して、自身の和魂を大物主櫛みか玉命の名で大三輪の神奈備に鎮まらせ、また、子の阿遅須伎高孫根命の御魂を葛木の鴨の神奈備に、事代主命の御魂を宇奈提(高市郡)に、賀夜奈流美命の御魂を飛鳥の神奈備に鎮まらせて、皇御孫命の近き守り神として貢り、自身は杵築の宮に鎮まりました。
このとき皇祖の男神女神は神勅で、天穂比命に、天皇陛下の長久の御世をお祝い申し上げ、栄えある御世として永く幸あるようにし奉れとお命じになりました。このご命令に随って、本日、一年間の潔斎を経て、朝日の昇るこの時に、神の奉り物、臣たる某の奉り物として、御禱の神宝を献じ奉りますと奏上いたします。
(第三段落)
ここに献上しました白玉、赤玉、青玉の連なりのように美しく整然と、この国をお治めする天皇陛下の長久の御世を、この横刀のように広らかに打ち堅めますように、
献りました白馬は、蹄を踏み立てて宮門の柱を根にしっかりと立て、その耳を高く振り立てて陛下がいよいよ隆盛に天下をお治めなさいますようにという志のためであります。
生きた御調の白鵠は陛下のお心を慰める玩物として、倭文(縞模様の織物)はその縞目の鮮やかなごとくに大御心が乱れることなく確かでありますように献ります。
潔斎で沐浴した古川岸(仁多郡三澤郷)のあちらこちらで、新たに水が湧いて淵が生じるがごとくに陛下が若やぎ、この後みそぎをする小門(川から海に出る小さな水門。意宇郡忌部神戸)の水が遡るように見えるがごとく益々若返りますように、
献りました真澄の鏡の面を拭い清めてご覧になるように、
明つ御神の大八嶋国を天地日月とともに安らかに平らかに治め給うであろうことの志のために、御禱の神宝をささげ持って、神の奉り物、臣たる某の奉り物として恐み慎んで、天津神の定められた次第のとおりに神賀の祝い言葉を申し上げますと奏上いたします。
神賀詞は三段落構成となっている。第一段落は導入に当たる部分で、明つ御神として大八嶋国を治める天皇の御世が長久であるようにお祈りして、熊野大社の大神と杵築大社の大穴持命の二柱の神をはじめとする出雲国全官社の神を奉斎し、出雲国造任命への復命の祝い言を申し上げると述べている。
「明御神と大八嶋ノ国知ろしめす天皇」の文言は、第三段落でも使われている。天皇を「明御神」と神扱いしている点は要注目だ。
なお、末尾が「奏し賜はくと奏す」となっている。これは、出雲の神々が天皇に奏し述べた言葉を、出雲国造がそのまま奏していることを表している。第二、第三段落の末尾も同様だ。
第二段落は、国譲りにおいて天穂比(「書紀」では天穂日、「古事記」では天菩比)、天夷鳥(「書紀」では武日照など、「古事記」では建比良鳥)親子が貢献したこと、大穴持とその御子神が皇御孫命を守ってきたことを主張し、皇祖神から天穂比に下された命令のままに御祷の神宝を献じると述べる。この段落については、この後詳しく見ていく。
第三段落は、献上物それぞれについて、その趣旨を説明した上で、出雲の神々からの奉り物、臣たる出雲国造からの奉り物を、天津神の定めた次第に従って奏上すると述べている。献上する神宝は、玉、横刀、白馬、白鵠、倭文、鏡である。大津透は、
「神宝を天皇に献ずることはいわば祭祀権をさし出すことであり、ここに服属儀礼の本質がある」 (大津、同書p.68)
としている。
第二段落は、国譲りの過程とその後を描いているが、それは「記紀」に描かれたものとは随分異なっている。次の点に着目したい。
- 主宰神は高御魂命
瓊瓊杵尊に大八嶋国の統治を寄託した主体を、天照大神ではなく高御魂命(「書紀」では高皇産霊尊、「古事記」では高御産巣日神)としている。瓊瓊杵尊を皇御孫命と呼んでおり、これは瓊瓊杵尊が天照大神の孫であることを示しているけれども、天照大神自身はこの神賀詞に登場しない。出雲国造果安が奏上した716年時点を考えると、まだ「書紀」は完成していないにしても、「古事記」は公表後だ。既に、草壁皇子が薨去した689年に、柿本人麻呂は草壁挽歌(万葉集巻2、167番歌)の中で、天界の主宰神を「天照らす日女の命」と呼んでいた。「記紀」編纂の時代には、高天原の主宰神が天照大神とされたことは広く知られていたはずだ。
奏上のとき果安に同道した出雲国守は忌部子首であった。出雲国守に任じられたのは「続日本紀」によると708年である。それまでは神祇氏族として朝廷内にいたのだからこのあたりの事情はよく知っていたに違いない。にも拘らず高御魂命を主宰神としていることからすると、この神賀詞の内容は主宰神が天照大神に変更する前に固まっていた可能性がある。
b. 国譲りの中で天穂比の果たした役割
天穂比が、高御魂命の命令で、天孫降臨の前に大八嶋国の視察のため遣わされた。天穂比は、国が乱れていることを確認して報告した。そして、皇御孫命が大八嶋国を安らかな国として統治できるようにすると申し上げ、子の天夷鳥を正使とし、布都怒志(「書紀」では経津主)を副使として天降した。天夷鳥は暴威を振るう神達を払い、大穴持命をなだめて国譲りに応じさせたとある。出雲臣の祖天穂比と子の天夷鳥が、国譲りにおいて決定的に重要な役割を果たしたとされている。
「書紀」の国譲り神話①では、天穂日も武日照も大己貴神に阿り復命しなかった。「古事記」の国譲り神話③では、天菩比は大国主神にへつらって復命しなかったとされている。神賀詞のこの描写は「記紀」と大きく異なる。ここには、出雲臣氏を継承し天神族の天穂比を祖神に頂いて杵築大社の祭祀を守ってきた意宇郡の族長としての矜持が見える。出雲臣の祖が瓊瓊杵尊の降臨に貢献したという物語を、自ら作ったのだと思われる。
神賀詞は、天皇に奏上する以上、その内容は事前に朝廷と十分に調整しているはずだ。つまり朝廷もこの物語を許容したことになる。朝廷にとっても全体として好都合な話と受け止めたからではないだろうか。
c. 皇御孫命の近き守り神
大穴持は、国譲りに応じた後、大倭国は皇御孫命が治めるべき国であると申して、A自分の和魂を大物主の名で大三輪の神奈備に、B子の阿遅須伎高孫根の御魂を葛城の鴨の神奈備に、C子の事代主の御魂を宇奈提に、D賀夜奈流美(文脈からすると大穴持の子と思われるが「記紀」に記載がなく不明。事代主の妹とする説がある。)の御魂を飛鳥の神奈備に、皇御孫命の「近き守り神」として鎮座させ、自身は杵築大社に鎮まった。
「書紀」の国譲り神話①では、事代主は国譲りを大己貴に進言して退去、大己貴も統治権のシンボルたる広矛を差し出して隠れただけだった。国譲り神話②では、大己貴は高皇産霊尊から統治領域の分担(大己貴は幽界の神事)と杵築大社の造営を国譲りの条件に提示され、これを受け入れて永久に隠れただけだ。ただし、大物主と事代主が天界に上って高皇産霊尊に忠誠を誓ったという点は、神賀詞と通じるところがある。この部分は、前回述べたように、神賀詞の内容を聞いた「書紀」編纂者が書き加えた可能性がある。「古事記」の国譲り神話③では、事代主は国譲りを進言して隠れ、大己貴は杵築大社の造営を条件に隠れただけだった。「書紀」の国譲り神話④では、大己貴が国譲りに応じた後の大己貴と事代主の動向には触れられていない。
結局、「記紀」の国譲り神話においては、国譲り神話②で大物主と事代主が高皇産霊尊に忠誠を誓ったとする部分を除き、出雲の神々が天孫に忠誠を誓い守護するというモチーフは見られない。国譲り神話は、もともとヤマト王権が行った出雲平定に対する祟りを鎮めるため、これを神代にあった国譲りということにすることで成立したと考えられる。国譲り神話を作った5世紀後半から7世紀後半の頃までのヤマト王権の人達には、大国主が天孫を守護するというストーリーは思いつかなかっただろう。
さて、神賀詞で大穴持が大倭国は皇御孫命が治めるべき国であると言ったときの皇御孫命とは、これは神代における話なのだから、瓊瓊杵尊であることは間違いない。国譲りの後、瓊瓊杵尊は日向に降り、木花之開耶姫を娶り、彦火火出見尊らの子を残して、日向で没した。ところが、神賀詞で大穴持が自身の和魂と三神の御魂を皇御孫命の「近き守り神」として鎮まらせた場所は大和である。つまりここに言う皇御孫命は、瓊瓊杵尊ではなく、人代において、神武東征後にヤマト王権を樹立し倭国を治めてきた大王、天皇のことだ。歴代大王、天皇は、もちろん天照大神の孫ではないけれども、瓊瓊杵尊と同じく天照大神の子孫であり、天照大神から瓊瓊杵尊に下された大八嶋国の統治命令を引き継ぐ正統な後継者として皇御孫命と呼ばれるのだろう。
皇御孫命とはここでは具体的には誰を指しているのだろうか。その近き守り神A~Dを地図に赤丸でプロットしてみる。地図12のとおりだ。A大三輪の神奈備とは三輪山、B葛城の鴨の神奈備とは高鴨神社、C宇奈提とは河俣神社と考えられている。D飛鳥の神奈備とは飛鳥坐神社の旧地と考えられているが、場所は諸説あって不明である。神奈備つまり山としていることから、ここでは祝戸地区説により飛鳥坐神社の南の祝戸地区にプロットした。この四か所は、少なくとも神賀詞ができた当時、出雲系の神が鎮座していると大和地域の人々に認識されていたと考えられる。
出雲臣果安が神賀詞を奏上した716年当時の王宮は平城宮である。地図から明らかなように、A~Dはその「近き守り神」にはなっていない。「近き守り神」になれるのは、藤原宮または飛鳥浄御原宮だろう。とすると、神賀詞において出雲の神々が守護している皇御孫命は、天武、持統、文武のいずれかの天皇ということになると思われる。
d. 天穂比の使命、出雲国造のアピール
皇祖の男神女神が、天穂比に、天皇の長久の御世をお祝いし、栄えある治世が永続するようにし奉れ、守護せよと命じたとしている。皇祖の男神女神とは、原文では神魯伎と神魯美である。祝詞で使われることの多い神の呼び名で、高皇産霊と神産霊または天照大神を指していることが多いが、固定しているわけではないと言われている。尾留川方孝は、高皇産霊などが具体的行為の主体にも客体にもならずただ命令して正当性を与える神として登場するときに使われる名前であると説明している(尾留川「神漏伎・神漏美および天神の性質と役割」)。大本の天つ神といった意味のようだ。その神々が天穂比に命じたということで、天穂比の使命が正当化されている。
その使命とは、大国主をはじめとする出雲の神々を挙げて天皇に忠誠を誓い天皇の治世を守護するようにすることだ。そのためにこうして神宝を献上するのだと述べている。大国主が国を天孫に譲った代わりに杵築大社を造営してもらい幽界に隠れるという国譲り神話②とは、随分と異なる話になっている。出雲臣(国造)は、神賀詞において神話を語りながら、国つ神を率いて参内し、天皇を皇御孫命と讃え、明御神と呼び、忠誠を誓い、その治世を守護するという宣言をすることによって、自分の存在をアピールし現実の政治的行為をなしているのだ。
ウ 神賀詞はいつできたのか
- 元正朝説について
村井康彦は次のように述べる。
「慶雲三年(706)、時の国造出雲臣〔果安〕が意宇郡の大領に補任された」「同じ年に〔ママ、正しくは708年〕出雲国守に忌部宿禰子首が任じられていた」「すべてはそこからの推測であるが、神賀詞奏上を含む一連の行動は、果安と子首との話し合いのなかで構想され、実現したものではなかったろうか。出雲国造による神賀詞奏上とは、国造果安が、中央の神祇氏族忌部子首が出雲守として赴任した機をとらえ、これに働きかけた結果実現したものと考える。しかしさらに大事な点は、忌部氏の理解と協力が得られたとしても、それだけでは実現しなかったことである。神賀詞奏上を、宮廷で行われる公的な行事に組み込み位置づけるには、神祇政策の中枢を担っていた中臣氏の理解と協力が不可欠だったからである」「神賀詞奏上は出雲国造家-忌部氏-中臣氏という神祇氏族のつながりのなかで実現された一大イベントだったのである」(村井『出雲と大和』p.180~188)
また、大日方克己は、「霊亀二年〔716年〕に出雲国造果安らの働きかけで出雲守忌部子首が協力して神賀詞奏上が創始され、九世紀前半の国造旅人・豊持の段階で、国造就任時の儀礼へと整備され、『延喜式』の形態になっていった」とする瀧音能之氏の見解、「『日本書紀』とのすり合わせも含めて忌部子首が主導して元正天皇の即位儀礼の一環としてはじめられた」とする榎本福寿氏の見解を紹介している(大日方「古代の出雲」p.172)。
果たしてそうだろうか。上記イa.で述べたように、神賀詞のなかで天界の主宰神を高御魂命としており、これは「記紀」の最終形において主宰神を天照大神としているのと齟齬がある。また、イC.で述べたように、出雲国造果安が奏上した時の王宮平城宮では、A~Dが「皇御孫命の近き守り神」にならない。神賀詞は、天界の主宰神が天照大神になる前、王宮が平城宮になる前に文面が固まっていたものと考えられる。
b. 垂仁朝説、舒明朝説について
山田孝雄は次のように述べている。
「この賀詞にはその神代の根本的事実を根本として、更にその後の出雲と朝廷との交渉によつて生じた事も加はつてあると思はるゝ点があるから、今の詞がそのまゝ太古のものとは見られないけれども、それは根本の賀詞を基として時代々々の新しく生じた事実によつて多少の添削を加へつゝ伝へたものと思はるゝもので、その大体はおそらく神社の数の変更の外は、奈良朝初期のまゝのものであらうかもしれぬ。或は溯つて真淵のいふ如く飛鳥時代のものでもあらう。或は又更に溯つた時代のものであらうかも知れぬ。極めて古く考ふれば垂仁天皇の御世まで遡りうるのでは無からうか。(中略)それがすこぶる古い時代から伝へられたものを基としてゐるものだらうことは信じて疑ふことは無い」(山田『出雲国造神賀詞義解』p.3)
どこまで遡るのだろうか。山田孝雄には、本居宣長ほどではないにしても、「記紀」に書かれたことをそのまま事実として受け取っているようなところが見られる。垂仁朝まで遡るのは行き過ぎだ。「古事記」垂仁天皇段に本牟智和気が出雲大神を拝んだ話が載っているけれども、実際の歴史では垂仁朝は4世紀前半であり、出雲平定の前、もちろん国譲り神話ができるずっと前だ。では「真淵のいふ飛鳥時代」はどうか。賀茂真淵は『祝詞考』(1768年)で次のように論じている。
「此詞式〔「延喜式」のこと〕に載たる祝詞どもの中にて、たぐひなく、古き文なるをおもふに、舒明天皇の、飛鳥岡本ノ宮の頃の文にやあらん、浄見原の宮までは下らじ」(p.1,823)
真淵はここで、神賀詞の文章の古さから見て、舒明朝のものではないかと述べている。確かに飛鳥岡本宮や、その後の皇極・斉明の飛鳥板葺宮・後岡本宮は、飛鳥浄御原宮と同じ場所にあったから、A~Dは「皇御孫命の近き守り神」に当てはまる。しかし仮に舒明朝や皇極・斉明朝の時代から神賀詞奏上が行われていたとしたら、その頃から出雲臣は朝廷に食い込んでいたことになる。そうであれば、壬申の乱において、普通に考えれば出雲臣は官軍側(大友皇子=弘文天皇方、近江方)に付いたはずだ(注1)。だが、実際には出雲臣は壬申の乱において反乱軍側(大海人皇子方)に付いた。「書紀」天武元年(672)七月二日条に、
「近江方は精兵を放って玉倉部邑(不破郡関ケ原町玉か)を急襲してきたが、出雲臣狛(注2)を遣わして撃退させた」
とある。また、同二十二日条に、
「羽田公矢国(近江方から投降して大海人方の将軍となった人物)と出雲臣狛とは、連合して三尾城(滋賀県高島郡)を攻め落とした」
とある。しかも、舒明~斉明の時代に、宮廷神話の整理が進んだとの記録は見られない。神賀詞を舒明朝のものとするのには無理があるのではないだろうか。
(注1)大友皇子は明治時代になって弘文天皇の諡号を与えられたが、実際に天皇に即位したかどうかは分からない。このとき23歳であり、天皇即位には当時の考え方からすると若過ぎたかも知れない。ただ、仮に即位しなかったとしても、父天智(斉明天皇の崩御(661年)から668年まで称制した)に倣い、称制をとったと思われる。天智政権の重臣であった蘇我赤兄左大臣、中臣金右大臣、及び蘇我果安・巨勢人・紀大人の御史大夫は、大友皇子太政大臣とともに、天智の病床で天智の詔に従うと誓ったし、壬申の乱で紀大人以外は大友皇子方で戦った。他方大海人皇子は、東宮であったものの、天智から「以後属汝(あとのことはおまえにまかせる)」(「書紀」天智十年(671)十月条)と言われたがこれを固辞し、出家していた。壬申の乱において大友皇子方が官軍であったのは間違いない。
(注2)「書紀」天武紀に「出雲臣狛」とあるが、「続日本紀」大宝二年(702)八月条に「出雲狛に従五位下を授けた」、同九月条に「出雲狛に臣の姓を賜った」とあるので、壬申の乱時点では出雲狛に姓はなかった。狛は当時大海人皇子に近いところで出仕していたと思われ、出雲臣氏の族長(国造)ではなかったはずだ。狛の壬申の乱での勲功によって、出雲臣(国造)の朝廷内での発言権が高まったものと思われる。なお、後年733年に「出雲国風土記」を奏上した国造兼意宇郡大領の出雲臣広島の位階は外正六位上である(「出雲国風土記」末尾に記載がある)から、狛への叙位は特別なものであったことが分かる。
c. 天武朝説について
石母田正は次のように述べている。
「これ〔神賀詞の成立の時期〕について古く真淵は『考』〔「祝詞考」のこと〕においては舒明天皇の時代まで引き上げたが、むしろ彼の『延喜式祝詞解』巻五の方の見解、すなわち文体からみて奈良まで下らず、おそらく『浄御原藤原両朝の比の作なるべし』という推定をとるべきであろう。もちろん出雲国造の神賀詞の奏上はそれ以前からおこなわれ、神賀詞の原型も同様であったとみられるが、それが記録にみえるような儀礼的なものとなり、それにともなって祝詞の詞章も現存のような形に完成されるのは天武朝の時期であるとみる見解にしたがいたい」(石母田『日本古代国家論』第二部p.86)
ここで石母田が引用している真淵の『延喜式祝詞解』は、1746年の作であり、次のように論じている。
「文体を按る〔しらべる〕に奈良に下たるものにあらず今少しく古時にて浄御原藤原両朝の比の作なるべし」(p.1,695)
石母田は、出雲と朝廷との交流または対抗関係の観点から、真淵の旧説を採用した。私も天武朝説に拠りたいと思う。その理由は、次のように推定されるからだ。壬申の乱で出雲狛が反乱軍側(大海人方)に加わり、戦局上重要な場面で勲功を挙げた。このため、出雲臣(国造)が天武朝において天武天皇から引き立てられた。出雲臣は、自らの祖神が国譲りで重要な役割を果たしたと主張して汚名を返上するとともに、天武を皇御孫命(瓊瓊杵尊)から続く正統な天皇と讃え、明御神と呼び、大国主をはじめとする出雲の神々ともども忠誠を誓い、天皇の治世を守護すると言上する神賀詞を創作した。そしてその奏上を天武に提案した。狛が仲立ちしたのだろう。武力で皇位を奪い取り、皇位継承の正統性に弱点を抱えていた天武天皇にとって、極めて有り難い提案だったはずだ。天武はこれを承認した。神賀詞が天武天皇に承認された時期は、壬申の乱672年の後、天界の主宰神が高皇産霊尊から天照大神に替わる前、史書編纂命令が出される681年の前のことであったと考えられる。だから、「記紀」編纂の過程で主宰神が変更し、「記紀」と神賀詞とで齟齬が生じても、天武天皇が承認した文面である以上、神賀詞の文面に手を加えることは誰にもできなかったのだろう。
神賀詞の文面は天武朝において完成し、天皇への奏上が行われたと考えられる。元正朝にて、出雲国造出雲臣果安と出雲守忌部子首が協力して中臣氏ら朝廷内を調整し、神賀詞奏上を宮廷儀式として制度化させたというのは確かなことであるように思われるが、それは、天武朝で行われた奏上を復活させたということだろう。
エ 神賀詞奏上の意味するところ
井上光貞は、冒頭に引用した文章のあと、さらに次のように述べている。
「奈良時代までつづいた国造のなかで、出雲国造だけが、その就任ごとに、右のような行事をおこなっていたことは見逃しがたいことである。それは、大和朝廷の国土統一、および国家形成の過程において、この出雲国造の勢力が大きな敵対勢力であって、これを服属させ、その祭祀権を中央に統合したことが、大和朝廷の国家形成上、重要な意味をもっていたためであろう。
そして、このことは、なにも八世紀の奈良時代や、大化改新のおこなわれた七世紀におこったことではなくて、「旧辞」のつくられた六世紀よりも、さらに以前のできごとであったであろう。日本の神話で、出雲平定が大きな意味をしめるのは、けっして偶然ではなく、それが日本の国家の成立上、いわば構造的に、重要な意味をもっていたからであろう」(井上『神話から歴史へ』p.99)
井上光貞の、出雲東部(意宇郡)の勢力が大和朝廷と結んで西部(出雲郡、神門郡)の勢力を滅ぼした説は、その後様々な批判を受けたけれども、井上の問題提起は今も貴重であるように思う。
上に述べた神賀詞天武朝成立説に基づき、神賀詞奏上の意味について考えてみる。
- 出雲臣と朝廷
出雲臣にとって神賀詞奏上とは何だったか。出雲東部意宇郡を本拠とする族長が、6世紀末頃に出雲臣を西部の族長から引き継ぎ、以後出雲国造として杵築大社で大国主祭祀を行ってきた。朝廷からは、天津神の天穂日を氏の祖神とすることが認められた。ところが朝廷の国譲り神話②では、天穂日は天神から地上に遣わされたにも拘らず、大国主に阿り、復命しない不名誉な神として描かれていた。出雲臣としては、神賀詞において祖神天穂比を国譲りで重要な役割を果たした神として描き、これを天皇に認めてもらうことにより、氏の汚名を返上することができた。さらに、出雲の全官社を率いて参内し、賀詞を天皇に奏上することにより、出雲臣=国造の出雲国内での政治上及び神祇上の統制力を高めることができたと考えられる。
天武朝廷としては、天武が武力で皇位を奪い取り、皇位継承の正統性に弱点を抱えていたが、多くの人民が信奉する国津神の頭領とも言うべき大国主神が、天武を皇位の正統な継承者である皇御孫命と讃え、明御神と呼び、忠誠を誓い、その治世を守護すると宣言する神賀詞の奏上により、この弱点を克服することができたと言えよう。さらに言えば、あからさまに上からの統治を見せるより、下から守護されているとした方が、体制の安定が確保できると考えたのではないだろうか。
b. 天皇即神思想の始まり
神賀詞において出雲臣は天皇を明御神と呼んだ。これは、天武天皇を、瓊瓊杵尊と同じく天照大神の子孫であり、瓊瓊杵尊に下された大八嶋国統治の命令を引き継ぐ皇御孫命と認めたことから来ていると思われる。だが、皇御孫命から直ちに明御神(天皇即神思想)が導かれるものではない。そこには飛躍があるように思われる。天皇即神思想は何時どのようにして生まれたのだろうか。
「書紀」で明御神等の語が出てくる個所は次の通りだ。
ⅰ 景行紀に、日本武尊が蝦夷討伐の際、蝦夷の長から名を尋ねられ、「吾是現人神之子也(私は現人神(天皇)の子である)」と答えたとある。日本武尊の物語は、帝紀・旧辞に記された伝承に「書紀」編纂時大きく手が加えられたと考えられる。このため、この「現人神」を景行朝の言葉と認めることはできない。「書紀」編纂時のものと思われる。
ⅱ 雄略四年(460?)条に、雄略天皇が葛城山に狩猟に行くと背の高い人物に会う。誰何すると「現人之神である」と答え、一事主神と名乗ったという逸話がある。「現人之神」という概念が当時あったと思われるが、ここでは天皇に対してそう呼んだのではない。
ⅲ 大化元年(645)七月条に、巨勢徳太臣が高麗の使人及び百済の使人に対し天皇の詔を「明神御宇日本天皇の詔」と述べたとある。まだ成立していない「日本」が使われている。律令制定後に原詔が書き改められたと考えられている。
ⅳ 大化二年二月条に、天皇が蘇我右大臣(倉山田石川麻呂)に読み上げさせた詔の中で、天皇を「明神御宇日本倭根子天皇」と称したとある。ⅲと同じく、原詔が書き改められたと考えられている。
ⅴ 大化二年三月条に、皇太子(中大兄)が孝徳天皇に奏請した文書の中で、天皇を「現為明神御八嶋国天皇」と称したとある。合理主義者でレアリストの中大兄皇子が、叔父の孝徳を「現為明神」と呼んだとは思えない。これも後世の書き改めだろう。
ⅵ 天武十二年(683)正月条の天武天皇の詔の中で、自らを「明神御大八洲倭根子天皇」と称している。「書紀」の中で、天皇を「明神」と呼んだ確実な記録としては、これが最初のものと考えられる。
神賀詞天武朝成立説では、神賀詞の文面は天武元年(672)から天武十年(681)の間に出来たと考える。とすると、ⅵ天武十二年の詔より早い。出雲国造神賀詞において我が国史上初めて天皇が明御神と称されたことになる。
出雲臣はなぜ天武天皇を皇御孫命に止まらず明御神と呼んだのだろうか。考えるにそれは、大国主はじめ出雲の神々が天皇を讃え忠誠を誓う以上、天皇も神でなくては釣り合いが取れないと考えたからではないだろうか。それが天皇即神思想の発端ではなかろうか。天武天皇はこの語を採用し、詔の中で使った。以降、天皇の即位の宣命などの中で使われ続けた。
c. 神賀詞に描かれた世界
神賀詞第二段落に書かれた内容を図示すると資料17のようになる。高御魂命は瓊瓊杵尊に大八嶋国の政事を寄託した。瓊瓊杵尊の子孫である歴代天皇は皇御孫命としてこれを引き継いでいる。出雲臣(国造)と大国主はじめ出雲の神々(国津神)がそれぞれ天皇=皇御孫命=明御神に忠誠を誓い、天皇の治世を守護すると宣言している。
国津神とは人民と言い換えてよいだろう。すると、天皇の御世は人民によって守護されていると言っていることになる。ここからは、天皇が人民を統治するという支配-被支配の関係は見えてこない。あたかも人民が天皇を明御神と崇め忠誠を誓い、その治世を守護する、安定した一君万民体制が実現しているように見える。
律令制に基づく統治体制の実態はどうだったろうか。大隅清陽は次のように述べている。
「律令国家の建設が進んだ天武朝に新たに生まれたのは、天皇が単なる神の子孫ではなく、生きながらにして神そのもの=現御神(明御神)であるとする天皇即神の思想である。(中略)これは、大和政権時代における王族や豪族たちの重層的で多元的な支配・従属関係が、中央官制と地方の国郡制の整備により官僚制的に一元化され、天皇がその頂点に位置づけられたことに対応している」(大隅「君臣秩序と儀礼」p.59)
これを図示すると資料18のようになる。ここで上級官人(天武十四年冠制では直位以上、大宝令制では五位以上の官人)は、大王を中心とする畿内豪族連合であった6世紀大和政権の時代の群臣を継承し、天皇と直接の君臣関係を結んでいると見なされた(同書p.52)。天皇の権力が特に強かった天武・持統朝においても、実際は君臣共治だった(注3)。
神賀詞の描く世界は虚像だった。虚像であることを天皇も上級官人も認識していた。大隅は次のように述べている。
「当時の人々が、天皇を実際に神と信じていたかは、当時の「神」観念のあり方を含めて、難しい問題である。(中略)天孫の集団としての畿内豪族連合の性格はまだ残っていたのであり、天皇即神といっても、天皇だけが臣民とは異なる絶対的な神である、という一神教的なあり方と異なることは確かである」(同書p.60)
上級官人らは、天皇を神扱いすることに同意し、即位式などの儀式において自らそう演技した。それが体制の安定に資すると考えたのだろう。その結果、後世、極端な一君万民思想が生まれる元になったと思われる。
出雲国造神賀詞は、出雲平定の歴史的事実と国譲り神話の形成の歴史があってはじめて作られたものであるけれども、そこに記された内容は、出雲平定からも国譲りからもかけ離れ、律令体制を擁護する物語になっていると言ってよいのではないだろうか。
(注3)「書紀」大化二年三月条に、孝徳天皇の東国国司に対する詔が記されている。その中に、「ここに集まった群卿大夫、および臣・連・国造・伴造、それにすべての百姓よ、みなよく承るがよい。天地の間に君として万民を治めることは、一人でよくなしうることではなく、臣の助けが必要である。それゆえ、代々のわが皇祖はおまえたち大夫の祖先とともに国を治めてきた。自分も神々の護りの力を身にうけ、おまえたち大夫とともに国を治めようと思う」とある。君臣共治の考え方とされている。のち、13世紀に慈円が「愚管抄」においてこの考え方を敷衍した。
(出典)
・「出雲国造神賀詞」、山田孝雄『出雲国造神賀詞義解』出雲大社教教務本庁、1960(国会図書館デジタルコレクションより)
(参考文献)
・井上光貞『神話から歴史へ』中公文庫、原著は1964
・大日方克己「古代の出雲」(吉村武彦他編『出雲・吉備・伊予』角川選書、2022)
・山田孝雄『出雲国造神賀詞義解』出雲大社教教務本庁、1960(国会図書館デジタルコレクションより)
・大津透『古代の天皇制』岩波書店、1999
・尾留川方孝「神漏伎・神漏美および天神の性質と役割」(『日本思想史学』第51号、2019(ネット)
・村井康彦『出雲と大和』岩波新書、2013
・賀茂真淵「延喜式祝詞解」1746、「祝詞考」1768(『賀茂真淵全集』第二、吉川弘文館、1903)(国会図書館デジタルコレクションより)
・石母田正『日本古代国家論』第二部、岩波書店、1973
・大隅清陽「君臣秩序と儀礼」(大津透ほか『古代天皇制を考える』講談社学術文庫、原著は2001)
(次回に続く)