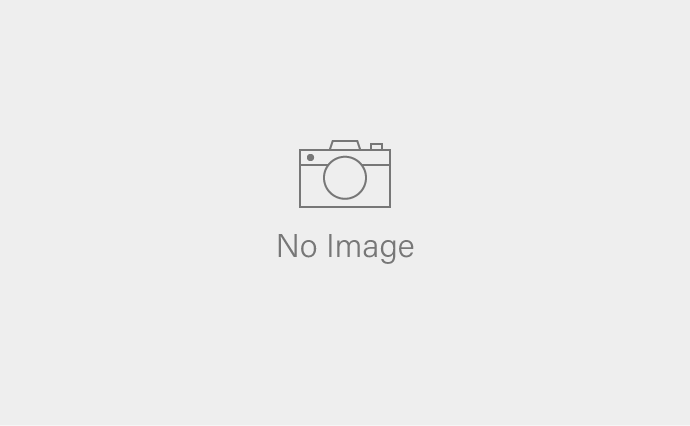2025年10月19日 直原裕naohara hiroshi
本ブログ第9回~第13回で、「なぜ神代における国譲りか」と題し、古代国家成立史における出雲の意味について考えてきました。これまでの流れを、見出しで辿ると次のとおりです。今回で一区切りとなります。
前回は、出雲国造が、壬申の乱を制して即位した天武天皇に対して行った神賀詞奏上を取り上げました。それは、国譲り神話を作り替え、出雲国造が大国主をはじめとする国津神とともに、天皇への忠誠とその治世の守護を誓うという内容に仕立てて演じる儀式でした。出雲国造が天武天皇の始めた新しい統治体制の中で重要な地歩を固めるための政治的パフォーマンスと言ってよいものでしたが、天皇を明御神と呼んだことを含め、その後の天皇制思想に与えた影響は少なくなかったように思います。
今回は、「記紀」の国譲り神話に話を戻し、これまでのまとめとして、国譲り神話がどのようにして形成され、また、変遷したかを整理します。
10 国譲り神話の形成と変遷
これまで取り上げた国譲り神話①~④の要旨を、資料19として一覧にまとめた。
国譲り神話①~④がどのような背景のもとに成立し変遷したかを示すため、資料20を作成した。これをご覧いただきたい。
資料20の前提、構成など
国譲り神話は、ヤマト王権が行った出雲平定という歴史的事実を、ヤマト王権の側から神話として描いたものであるという基本認識に基づき、この資料を作成している。また、「記紀」神話は天皇統治の正統性を弁証することにその核心があることから、国譲り神話は天孫降臨神話および神武東征神話(神武東征は人代の物語ではあるけれども、天孫降臨と一体のものと考えられるので、神話と呼ぶことにする。)とセットで成り立っていると予想される。そこで、国譲り神話①~④に対応する天孫降臨神話①~④および神武東征神話①~④が存在すると仮定している。
出雲と大和の史実を左右両端に、間にそれぞれの神話、伝承を時系列(3Cから8C初めまで)に記載した。個々の事項は、これまでに述べてきた中から主なものをピックアップしている。青線の矢印は因果あるいは影響関係を表している。
弥生時代については具体的年代が不確かなので、前史としてひとまとめにした。出雲では杵築大社(出雲大社は明治になるまで杵築大社と呼ばれていた。)を創建し国作りの指導者大国主を祭るとともに、大国主を主人公とする出雲神話が成立した。出雲神話は、弥生時代における地域間での活発な交流を考えると、大和の人たちにも知られていたはずだ。後に高天原神話として括られる様々な神話の原形は、大和を含め広範な地域で伝えられていたものと考えられる。三輪山での神奈備信仰は縄文時代に遡る可能性がある。これらの神話や伝承は、3世紀以降の人たちにとって所与のものだ。
国譲り神話の歴史
2世紀末に邪馬台国連合が成立し、3世紀前半には魏に朝貢する。出雲も邪馬台国連合に参加していた。邪馬台国連合は3世紀後半に崩壊するが、邪馬台国が創始した前方後円墳祭祀は、大和地方においてその後も残った。
4世紀初め、崇神がヤマト王権を樹立した。大王家は、もともと瓊瓊杵、彦火火出見の父子を始祖とする伝承を有していたと考えられる(そのように考えると辻褄が合うという意味だ。)ヤマト王権は前方後円墳祭祀を踏襲した。そして、四道将軍を派遣し勢力圏を拡大するとともに、傘下に入った証としてその地域の実力に見合った規模で前方後円墳を築造させた。しかし出雲はヤマト王権の傘下に入らなかった。世紀半ば以降、ヤマト王権はさらに熊襲、蝦夷を平定し、朝鮮への進出も開始した。世紀末頃に出雲平定を行った。
国作りの指導者として多くの民が敬愛し信仰する大国主の本拠である出雲を平定したことから、当時の人々は天変地異や疫病が発生するとこれを大国主の祟りと観念するようになった。このためヤマト王権は、4C末~5C初め頃に大国主の祟りを鎮めようと杵築大社で大国主祭祀を行った。三輪山でも祭祀を行った。
ヤマト王権は朝鮮経営を進めたが、5世紀初め、北方の大国高句麗と朝鮮権益をめぐって戦い、大敗した。ヤマト王権は対外・対内政策の見直しを図る。宋に朝貢し、倭国の朝鮮権益に対する認定を求めるとともに、先進文明の導入を進めた。また河内を開発し巨大古墳を築造した。
世紀後半には雄略が大王に権力を集中させ、「治天下大王」を名乗る。宋の冊法体制から離脱し、独自路線を歩むことになる。さらに、大王の卓越性を示すため、北方ユーラシアの天神神話を取り入れ、大王家の始祖瓊瓊杵を天神高皇産霊の子孫とする(天孫降臨神話①)。また、ヤマト王権の樹立を、彦火火出見による大和の武力制圧によるものとする(神武東征神話①)。伊勢神宮は、この頃に創建されたと考えられる。(注)
国譲り神話①は、大国主が瓊瓊杵に国を譲るよう高皇産霊から迫られ、応ずる話であり、瓊瓊杵が天降りすることを前提としている。つまり、国譲り神話①に先立って天孫降臨神話①が成立していたことになる。もともと天孫降臨神話①は、瓊瓊杵が降臨する話であり、神武東征神話①はその子の彦火火出見が大和を制圧して王権を樹立する話であって、どちらもそれだけで成立する。国譲りの話が入る必要はない。国譲り神話は別の必要から瓊瓊杵が降臨する前の話として後付けされたものだ。
また、国譲り神話①には杵築大社造営の話が出てこない。これは、国譲り神話①はヤマト王権が杵築大社を造営する以前に成立していたことを示している。ヤマト王権が大国主の祟りを鎮めるため大国主祭祀を行ったにも拘らず天変地異や疫病が収まらないことから、出雲平定を神代における国譲りであったことにするという国譲り神話①が作られたものと思われる。それは5世紀末頃のことであったろう。
6世紀前半、筑紫磐井の乱を鎮圧後、ヤマト王権は国造制・屯倉制・部民制による地方統治を本格化する。世紀中頃には欽明大王の下、帝紀・旧辞の編纂が行われ、皇統譜の整理と王権神話の体系化が始まった。
このとき天孫降臨神話②と神武東征神話②が成立したと考えられる。天孫降臨神話②において、日向神話が取り入れられ、瓊瓊杵は日向に降臨し木花之開耶姫を娶って彦火火出見が生まれたとされた。彦穂穂出見の出自がここで明確にされたわけだ。また、神武東征神話②において、彦火火出見が日向から東征して大和を制圧し神大和磐余彦を名乗ったとされた。
帝紀・旧辞編纂時に、国譲り神話②も成立したと考えられる。ここでは、高皇産霊が大国主に対し、国譲りの条件として天日隅宮の造営を提示したとされている。このことは、国譲り神話②が、杵築大社の造営が既に実際に行われたことを前提に成立したことを示していると考えてよいだろう。つまり、天変地異や疫病が続き、大国主の祟りを鎮めるため、5世紀末から6世紀初めの頃に、ヤマト王権によって杵築大社の造営が行われたと考えられる。多くの民が敬愛し信仰する大国主の祟りという観念は、ヤマト王権の為政者たちにとってそれだけ重く、何としてもぬぐい去りたかったのだろう。
また、この段階で、国譲りは出雲で行われたのに、瓊瓊杵が降臨したのは日向であり、彦火火出見は日向から東征に向かうという不整合が生じることになった。尤も、帝紀・旧辞編纂者にとっては、一方で出雲平定の祟りを鎮めるため大国主の国譲りという物語が必要であったし、他方で彦火火出見の出自を具体化するためには日向神話を取り入れる必要があった。見方によれば不整合になることは分かっていたのだろうが、どちらも必要なのだからこれでよいと考えたのだろう。
6世紀半ば以降国造制が定着し、出雲では西部神門郡の族長出雲臣が国造として大国主祭祀を行うようになったが、世紀末には衰退した。このため、7世紀には東部意宇郡の族長が出雲臣を引き継ぎ、国造として大国主祭祀を行うようになった。このとき大和朝廷から、祖神を、天神族に属する天穂日とすることが認められたと考えられる。
大和では6世紀末から7世紀初めにかけ聖徳太子による内政・外交改革が行われる。仏教文明の導入、遣隋使の開始、天皇を中心とする政治体制の構築が進められた。儒仏に違背する前方後円墳祭祀は終了した。太子の改革は中途で終わったが、天皇記・国記が残された。天皇記・国記において太子が仮構した歴史の枠組と、中国と異なる独自の統治の正統性原理の主張(本ブログ第1回および第5回)は、後年、「記紀」に引き継がれることになる。
大化改新後も出雲では国造が存置された。大国主祭祀を継続する必要があるからだ。出雲国造は朝廷から杵築大社の修造を命じられた。杵築大社の維持管理は出雲国造の職責となっており、朝廷にとって大国主の祟りへの恐れは既に薄れていたのだろう。
白村江の戦から続いた対外緊張が緩和されたのち、天武朝において律令制定と史書編纂がスタートする。天武天皇は史書編纂に当り、ヤマト王権の歴史つまり人代については聖徳太子が仮構した枠組を踏襲すること、そして人代の前に神代を置くことを命じた。天神から天皇家の始祖瓊瓊杵、彦火火出見父子に至る系譜を史書の中で具体的に示すためだ。このため、天界の主宰神を高皇産霊から天照大神に替え、伊勢神宮に祭った。史書編纂を命じられた編纂委員会と稗田阿礼は、相互に連絡を取りながら、天武の指示した基本方針に基づいて、それぞれ「日本書紀」編纂、「古事記」編纂の具体作業を開始した。
「記紀」編纂は一時期滞っていたようだが、8世紀初め遣唐使再開を機に、最終取りまとめがなされた。「書紀」はもともと中国皇帝に対して日本存立の独自性を主張することを目的に編纂されたからだ。国譲り神話については、天孫降臨神話において天界の主宰神が天照大神に替ったのに合わせ、「古事記」(国譲り神話③)、「書紀」(国譲り神話④)ともに大国主に国譲りを迫る主体は天照大神となった。また、朝廷にとって出雲平定に対する大国主の祟りの恐れが薄くなっていたことから、「古事記」では杵築大社の造営を条件提示するのは大国主となり(国譲り神話③)、「書紀」では杵築大社造営の話は抜け落ちた(国譲り神話④)。
国譲り神話はこのような変遷を辿って「記紀」に記されたと考えられる。国譲り神話の成立と変遷の過程は、出雲固有の歴史とともに、ヤマト王権の成立から国土平定、権力集中、地方統治、律令国家の形成までの歴史と密接に関わるものだった。また、国譲り神話に描かれた天界の主宰者(高皇産霊、天照大神)と、皇御孫命の瓊瓊杵、そして大国主(国津神の頭領)の関係は、出雲国造神賀詞とも相まって、天照大神と天皇、人民の関係についてのその後の天皇制思想の形成に、少なからぬ影響を及ぼしたと考えられる(資料21)。
(注)天孫降臨神話は、溝口睦子によると、もともと、天神の子が天降って地上の支配者になるという北方ユーラシアの支配者起源神話を5世紀に導入したものであり、タカミムスヒはその天の至高神であった(溝口『アマテラスの誕生』p.39,p.96、同『王権神話の二元構造』p.181)。また、伊勢神宮は、岡田精司によると、大王の専制体制を強化する宗教的裏付けとして、大王の守護霊=太陽神が氏の枠を超えた国家的祭祀の対象となるよう、伊勢の地で創始された。5世紀後半、雄略朝のこととされる(岡田『古代王権の祭祀と神話』p.349,p.368)。お二人の議論を繋げると、創建当時の伊勢神宮に祭られたのはタカミムスヒであったと考えると分かりやすいのだが、二人ともそうは言っていない。
(参考文献)
・溝口睦子『アマテラスの誕生』2009、岩波新書
・同『王権神話の二元構造』2000、吉川弘文館
・岡田精司『古代王権の祭祀と神話』1970、塙書房
(今回仮定として置いた天孫降臨神話と神武東征神話の①~④については、次回以降テーマとして取り上げ考えていきます。)