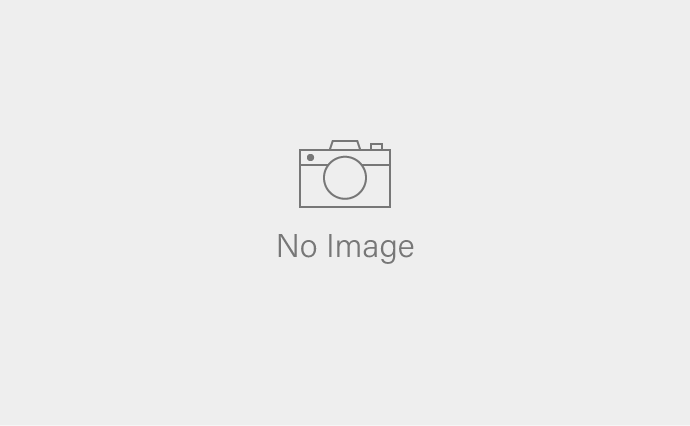2025年2月25日 直原裕naohara hiroshi
これまで5回にわたり、日本は神日本磐余彦(神武天皇)によって紀元前660年に建国されたという建国の枠組を、聖徳太子はなぜ作ったのか、その理由を考えてきました。太子は、死去する2年前の推古二十八年(620)に、「天皇記および国記」を編纂しました。この書物は乙巳の変(645)で焼失しましたが、そこに建国の枠組が記されていたはずです。「続日本紀」によると、それから丁度百年後の養老四年(720)に(天武天皇の編纂命令から数えると40年後ということになりますが)、「日本書紀」は完成します。「書紀」はこの建国の枠組に基づいて書かれています。言い換えれば、「書紀」編纂者は聖徳太子の作った建国の枠組を踏襲したということです。これから、「書紀」編纂者は、どのような編纂方針のもとに「書紀」を編纂したのか考えます。
大君は神にしませば
「書紀」は、神代の物語と、初代神武天皇から持統天皇まで歴代天皇の治世を記述している。巻末に当る持統天皇が即位したのは、持統四年(690)である。持統は大化元年(645)生まれなので、この時45歳。夫で前代の天武天皇が崩御してから3年余り経っていた。二人の間の嫡子、草壁皇子に皇位を継がせるためその時機を待つことにし、持統が称制を続けてきたのだ。しかしその草壁が27歳で薨御してしまう。このため草壁の嫡子珂瑠皇子(後の文武天皇)に皇位を繋ごうと、それまでの間、持統が自ら皇位に就くことになったとされている。持統は、天武の治世を同志のようにして支えてきたので、統治者としての能力も経験も自他ともに認めるところだったようだ。
持統の即位式は「書紀」に次のように記されている。
四年の春正月の戊寅の朔に、物部麻呂朝臣が大盾を立てた。
神祇伯中臣大嶋朝臣が天神寿詞を読んだ。それが終わって、忌部宿禰色夫知が神璽の剣と鏡とを皇后にたてまつり、皇后は皇位におつきになった。公卿・百寮は整列して一斉に拝礼し、手を拍った。
己卯(二日)に、公卿・百寮は、元日の儀式どおりに天皇に拝し、丹比嶋真人と布施御主人朝臣とが、即位を祝うことばを申し上げた。
(中公文庫、井上光貞監訳版)
大化改新までは、前天皇が崩御すると群臣が推挙して次の天皇を決めていた。それが今や、持統自身のイニシアティブで天皇に即位し、天神が祝福する。群臣はこれを見守り讃える。
このことについて、熊谷公男は次のように解説している。
持統の即位式でもうひとつ注目される記述がある。即位した新天皇に対して、群臣が拝礼のほかに拍手をしていることである。ここにいう拍手とは、いわゆる柏手のことで、いまに続く神拝の作法である。即位式の拝礼に、はじめて天皇を“神”に見立てる儀礼が取り入れられたのである。
(熊谷『大王から天皇へ』p.343)
天皇の神扱いは、天武天皇から始まっている。天武は自らを「明神御大八洲倭根子天皇」と称した(「書紀」天武十二年(683)正月条)。また、「万葉集」に次の歌がある。
○大君は神にしませば赤駒の腹這ふ田居を都と成しつ (巻19-4260 大伴御行)
○大君は神にしませば水鳥のすだく水沼を都と成しつ (巻19-4261 作者不詳)
○大君は神にしませば天雲の雷の上に廬りせるかも (巻3-235 柿本人麻呂)
○大君は神にしませば真木の立つ荒山中に海を成すかも (巻3-241 同)
○……高照らす日の皇子は飛鳥の清御の原に神ながら太敷きまして天皇の敷きします国と天の原石門を開き神上り上り座しぬ…… (巻2-167 同 草壁皇子挽歌より)
○……瑞穂の国を神ながら太敷き座すやすみしし我が大君の天の下奏したまへば万代に然しもあらむと…… (巻2-199 同 高市皇子挽歌より)
いずれも天武天皇を神としている。人麻呂の歌は持統朝で詠われたと考えられるが、初めの二首は、題辞に「壬申年之乱平定以後歌二首」とあることから、天武朝において詠われたと思われる。熊谷は、
(壬申の)乱後、天武は“神”とあがめられる存在になっていたのである。(同書p.334)
としている。天皇の神扱いは、天武朝に始まり持統朝で確立したと言えよう(写真6)。
確かに、壬申の乱によって武力で権力を掌握し、その後中央集権化を進めた天武に対して、多くの豪族が畏怖の念を抱いたであろうことは想像できる。しかしそれにしても持統の即位式は荒唐無稽で芝居掛かっていないだろうか。即位式に居並ぶ皇族や群臣は、持統を本当に神と崇めていたのだろうか。
ここで過去50年の皇位継承争いを振り返ってみよう。
・643 蘇我入鹿による山背大兄王(聖徳太子と蘇我刀自古郎女の子)とその一族の粛清
・645 中大兄皇子と中臣鎌足による入鹿誅殺(乙巳の変)。古人大兄皇子(舒明天皇と蘇我法提郎女の子)の粛清。
・653 中大兄皇子による孝徳天皇の排除(翌年天皇は病死)
・658 中大兄皇子による有間皇子(孝徳天皇の子)の粛清
・672 大海人皇子による弘文天皇(天智天皇の子、大友皇子)討伐(壬申の乱)
・686 持統皇后による大津皇子(天武天皇と、持統の同母姉である大田皇女との子)の粛清
策謀を伴う凄惨な皇位継承争いが続いた。その間には白村江の戦い(663)を頂点とする対外危機もあった。これらを同時代人として見てきた、あるいは関与してきた群臣らが、天武や持統を神と考えていたはずはない。大津皇子粛清はたかだか4年前のことだ(写真7)。群臣らは、天皇は神であるということにしたと考えるべきだろう。なぜ天皇を神扱いすることにしたのか、それをこれから考えていきたい。
「書紀」編纂上の疑問
天皇を神扱いしたことは、事実だろう。「書紀」「万葉集」に書いてある通りだと思う。一方、「書紀」を読むと、数々の編纂上の疑問が湧いてくる。
先ず気づくのは、長命の天皇が多いことだ。没年齢が百歳以上の天皇を列挙すると、神武127歳、孝昭113歳、孝安137歳、孝霊128歳、孝元116歳、開化111歳、崇神120歳、垂仁140歳、景行106歳、成務107歳、神功皇后100歳、応神110歳、仁徳126歳(注1)となっている。初代神武から仁徳まで、神功皇后を含めて17代中13代が100歳以上である。これが、聖徳太子の作った建国の枠組により、歴史が引き延ばされた結果であることは明らかだ。
「書紀」の記述に見られる空白期間は、引き延ばしの痕跡だろう。まず欠史八代と呼ばれる第2代綏靖から第9代開化までは、事績の記述がなく、すべてが空白期間。これは本ブログ第1回で述べた通りだ。他にも、神武四年から三十一年までと四十二年から七十六年までは事績の記述がなく空白だ。同様に、崇神十七年から六十年まで、垂仁三十九年から八十八年まで、景行二十八年から四十年まで、成務五年から四十八年まで、神功摂政十三年から三十九年まで、仁徳六十七年から八十七年までが空白だ。これらは引き延ばしの調整期間に他ならない(資料9)。
「書紀」編纂者は、本ブログ第1回資料2に記した聖徳太子の建国の枠組を踏襲し、この枠組の中に歴代天皇の在位を配置したと考えられる。それを図示すると、資料10のようになる。
次に、記述の内容に関して私が抱いた疑問を列挙しよう。
1 「書紀」編纂者が手本にしたであろう司馬遷「史記」は、黄帝から始まる。伝承の存在ではあるが神ではない、人間だ。これに対して「書紀」は神代から始まる。歴史書として書いたと思いきや、なぜだろう。
2 ヤマト王権が国土平定を進める過程で、独自の勢力を有していた出雲の平定も行ったはずだが、「書紀」編纂者はこれを神代の時代の国譲りとして描いている。なぜか。
3 「古事記」には因幡の白兎の話などたくさんの出雲神話が盛り込まれているが、「書紀」は、スサノオの八岐大蛇退治と大己貴神(オオクニヌシ)の国作りを記述するだけであり、出雲神話を殆ど載せていない。なぜだろうか。
4 神話の中味についても、
(1) 第五段(三貴子の誕生)一書第六で、イザナキが黄泉の国から戻った場所を出雲(注2)としているのに、そのあとイザナキはわざわざ日向まで往って、禊を行い、アマテラス・ツクヨミ・スサノオを生んだとしている。
(2) 第一段(天地開闢)本文では、タカミムスヒには触れず一書第四で言及するだけであるにも拘らず、第九段(葦原中国の平定と天孫降臨)本文にいきなりタカミムスヒを登場させ、葦原中国の平定を神々に命じたとしている。さらに、タカミムスヒはニニギに真床追衾をかぶせて地上に降臨させたとする。この場面にアマテラスを登場させていない。
(3) 第九段一書第一で、アマテラスは、初めは子のアメノオシホミミを葦原中国に降臨させようとしたが、アメノオシホミミに子ニニギが生まれたというそれだけの理由で、アマテラスから見て孫に当たるニニギを降臨させたとしている。
(4) 同じく第九段一書第一で、アマテラスはニニギの降臨に先立ち出雲の大己貴神に国譲りをさせたとしているが、ニニギが降臨した場所を日向としている。
(5) 第十一段(神日本磐余彦の誕生)一書の第二、第三、第四において、神日本磐余彦(神武天皇)の諱を、ニニギの子であり第十段(海幸・山幸と豊玉姫の物語)に登場する山幸の名と同じヒコホホデミとしている。なお、神武紀冒頭においても、神日本磐余彦天皇の諱をヒコホホデミと記している。
など、辻褄の合わないところがあるのはなぜだろうか。
5 神代の時代に国譲りがされたと書いたにもかかわらず、神武紀において、神日本磐余彦が日向から大和まで東征したとするのはなぜか。しかもそれを、ニニギの降臨から百七十九万二千四百七十余年後のこととしているのはなぜか。
6 神日本磐余彦の東征物語のうち、大和制圧の記述にはリアルな描写が含まれている。「書紀」編纂者は、ヤマト王権の始まりを武力制圧によるものと本当に考えていたのだろうか。
7 「書紀」編纂者は、神日本磐余彦(神武天皇)を始馭天下之天皇と呼び、御間城入彦五十瓊殖(崇神天皇)も御肇国天皇としている。なぜハツクニシラススメラミコトが二人いるのだろうか。崇神天皇がヤマト王権の実質初代の君主だとすると、「書紀」編纂者は、なぜ神日本磐余彦を造形したのだろう。
8 「書紀」編纂者は「魏志倭人伝」を読んでいたにもかかわらず、卑弥呼についても邪馬台国についても記述しないのはなぜだろうか。
9 「書紀」編纂者は、垂仁朝においてアマテラスを各地巡行の後伊勢に祭ったのが伊勢神宮の始まりとしているが、神代の巻の天孫降臨神話を見ると、タカミムスヒを最高神としているように読める。天孫降臨神話と伊勢神宮の起源について、どのように整理しているのだろうか。
10 「書紀」を通読すると、日本武尊の国土平定話と息長足姫尊の熊襲・新羅征討話は際立って物語調で書かれているのが分かる。「書紀」編纂者にとって、ヤマトタケルとオキナガタラシヒメはどのような位置付けなのだろうか。
11 5世紀に倭の五王が盛んに宋に朝貢し、皇帝から叙爵を得たことが「宋書」に書かれている。「書紀」編纂者はこれを読んでいたし、そもそも帝紀・旧辞にも書かれていたはずだ。なぜ「書紀」にその事実について記述しないのだろうか。
12 3世紀中頃から築造が始まった前方後円墳を、ヤマト王権はその勢力拡大とともに全土に普及させた。6世紀末まで王権も豪族も多大な労力をかけ、こぞって作り続けた。帝紀・旧辞にもたくさん書かれていたはずだ。なぜ「書紀」編纂者はその事実について記述しないのだろうか。
13 「天皇」号の成立時期に関しては、推古朝とするか天武朝するか二説あるが(私は前者を採る)、いずれにしろ7世紀だろう。「書紀」編纂者は、なぜ初代の神日本磐余彦から天皇と呼称するのだろうか。そしてなぜ「天皇」号の由来について記述しないのだろうか。
14 「書紀」編纂者は、書名に「日本」を使っているにもかかわらず、なぜ国号「日本」の由来について記述しないのだろうか。
15 神代を除く全編を通して、大多数の事績に暦日を付している。暦が入る5世紀半ば以前の事績では暦日の記録はありえなかったし、暦が入ってからでもそこまで詳細な記録が残っていたとは思えず、創作したと断ずるほかない。「書紀」編纂者の暦日への異様なこだわりはどこから来ているのだろうか。
次回以降、これら「書紀」編纂上の疑問について、先に挙げた天武・持統朝で実際に天皇を神扱いしていたことの理由とともに、考えていくことにする。
(注1)仁徳の没年齢は「書紀」に記載がない。「書紀」応神二年条に、応神が仲姫(「古事記」によると景行天皇の曽孫に当る。)を皇后に立て、その第2子として仁徳が生まれたとある。そこから仁徳は応神四年に出生したと仮定し、応神の在位年数41年、空位2年、仁徳の在位年数87年から没年齢を126歳と推計した。尤もこれは、あくまでも「書紀」上の年齢であって実年齢ではない。因みに「古事記」は仁徳の没年齢を83歳としているが、4世紀後半から5世紀前半の皇位継承を考えると、これも長すぎると思われる。
(注2)「書紀」には、イザナキが黄泉の国から戻った場所を泉津平坂としているものの、それがどこにあるか書いていない。しかし「古事記」は、黄泉比良坂を出雲の国の伊賦夜坂のことと説明している。
(参考文献)
・熊谷公男『大王から天皇へ』(講談社学術文庫、2008)