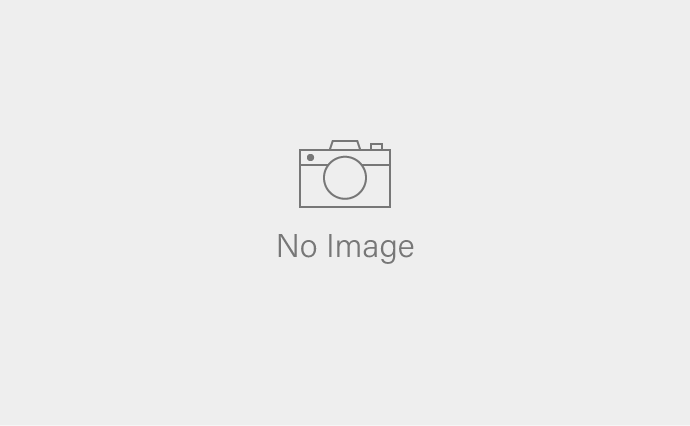2024年12月1日 naohara hiroshi
前回は、第1回遣隋使の屈辱をバネに聖徳太子が行った内政改革を見てきました。今回は、満を持して行った隋への2回目の遣使と、これへの隋の対応、そして太子はどうしたかを見ます。
1 「日出ずる処の天子」
「書紀」に、推古十五年(607)小野妹子を隋に遣わしたと記されている。しかし、隋での皇帝煬帝とのやりとりについて何ら記載はない。一方、「隋書」にはそれが残っている。600年第1回遣隋使は国書を持たず口頭でのやりとりだけだったようだが、今回は国書を携えていた。国書に書かれていた倭王多利思比孤の言葉が、有名な、
「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無きや云云」
である(資料6)。煬帝はこれを読み、
「蛮夷の書、無礼なる者あり。復た以って聞する(奏上する)勿かれ」
と鴻臚卿(外務大臣)に言ったとされる。
天子は、世界を治める天命を受けた中国皇帝ただ一人。それを蛮夷の倭王が自称したから、中国の「礼」に則っていない、つまり無礼ということになる。しかし妹子が携えたこの国書、太子のもとで綿密に練られたものだった。堀敏一によると、過去中国皇帝に対して周辺諸国から出された国書の構文をベースとし、そこで使われた文言を踏まえて作文されている。
第2回遣隋使が携えた国書にある倭王の言葉を漢文で書くと、
「日出処天子致書日没処天子恙無云云」
である。
その20余年前、584年に突厥のイシュバラ可汗(可汗は突厥の君主の称号)が隋の文帝に送った書状に、
「從天生大突厥天下賢聖天子伊利俱盧設莫何始波羅可汗致書大隋皇帝(天より生まれたる大突厥の天下聖賢 天子イリキュルシャドバガイシュバラ可汗、書を大隋皇帝に致す:堀敏一の訳)」
とあった。当時突厥は強大でその可汗は天子と自称し、対等の者として中国皇帝に書を致した。第2回遣隋使の国書はこの文言を引いている(地図5)。
また、遡るが「漢書」によると紀元前176年、強大で漢を脅かした匈奴の冒頓単于(単于は匈奴の君主の称号)が漢の文帝に送った書状に、
「天所立匈奴大單于敬問皇帝無恙(天の立つる所の匈奴大単于、敬みて皇帝に問う、恙無きや:堀訳)」
とあった。また、次代の単于の書状には、
「天地所生日月所置匈奴大單于敬問漢皇帝無恙(天地の生む所、日月の置く所の匈奴大単于、敬みて漢の皇帝 に問う、恙無きや:堀訳)」
とあった。遣隋使の国書の「恙無きや」はこれを引いている。
太子は、高句麗僧の慧慈先生と百済博士の覚哿先生から指導を受け、中国の史書や外交文書を学んだ。突厥イシュバラ可汗書状は慧慈ルートで知り、匈奴単于書状は覚哿から学んだのだろう。太子は、中国が対等の関係にあった国と交わした文書の文言を用いることで、倭国が隋と対等であることを主張したのだ。
煬帝はこれを読んで怒った。中国が軍事的に脅かされた時代に認めざるを得なかった文言を、他でもない隋から見て軍事的にとるに足らぬ蛮夷の王が使ったから。
太子が第2回遣隋使を送った目的について、「隋書」は使者(妹子)が語った言葉を載せている。
「聞く、海西の菩薩天子、重ねて仏法を興すと。故に遣わして朝拝せしめ、兼ねて沙門(僧)数十人来たりて仏法を 学ばしむ」
太子は、文帝、煬帝の二代にわたり仏教興隆政策をとってきた隋に学問僧を送り、学ばせ、太子の進める倭国の仏教振興に活かそうとした。太子としては、
倭国は国としては中国と対等であり、中国皇帝から冊封を受けることはしない。しかし仏教を興隆させてきた隋皇帝に敬意を表することにしよう。そして隋から先進仏教文明を学ばせてもらおう。
そういう思いだったのだと思う。
2 路線転換
煬帝は、「二度と奏上するな」と言ったにも拘わらず、文林郎(下級の秘書官)の裴世清を倭国に送ることにした。なぜか。
倭の国書に、20余年前の突厥イシュバラ可汗書状の文言が使われていることに煬帝は目をみはったはずだ。こう思ったのではないか。
匈奴単于の書状は「漢書」に書いてある。しかしイシュバラ可汗書状を倭国はどうして知っているのか。
「隋書」ができるのは勿論唐の時代になってからだから、イシュバラ可汗書状の文言はこのとき公刊書物には載っていない。
この年607年煬帝は北辺の異民族の従属を確認するため北辺巡幸を行っていた。その際、突厥の啓民可汗(イシュバラ可汗の子あるいは甥)に招かれた天幕にて、突厥を訪れた高句麗の使者と遭遇した。予てより高句麗征討を計画していた煬帝は、今は隋に服属しているがかつて隋を脅かした突厥が高句麗と通交していることを知って衝撃を受け、遂に高句麗征討の実行を決意したとされる。煬帝は、倭国の国書を見て、突厥情報が高句麗を通じて倭国に流れていることに気づいた。そして、高句麗の背後に位置する倭国に、高句麗との関係を絶たせなくてはいけないと考えたはずだ。
ではどうする。倭国は隋から冊封を受けることは拒否しているが、学問僧の受け入れを求めている。中華文明が倭国に必要なのだ。それなら、学問僧受け入れを条件に、高句麗との縁を切らせよう。
煬帝の裴世清派遣の意図、裴世清の使命は、これだったと考えられる。
「書紀」によると、裴世清は遣隋使小野妹子とともに百済を経由して608年4月、筑紫に到着した。妹子は直ちに大和に戻り、帰朝報告したことだろう。国書の「天子」号は煬帝の認めるところではなかったこと、そして煬帝の命を受け、裴世清が学問僧受け入れの条件として高句麗からの離反を求めに倭国に遣わされたことを、太子に報告したはずだ。
倭国は急いで難波に館(迎賓施設)を建造するとともに、その間に対応策を練った。まさか学問僧受け入れに高句麗からの離反が条件に付くとは思ってもみなかったのではないか。太子は、東アジアの政治に参入しようとしたところ、いきなり隋・高句麗対立に巻き込まれてしまった。太子は考えたろう。
条件を受け入れれば、推古帝は隋皇帝から冊封を受け臣下にならざるを得なくなるのではないか。倭国が維持してきた独立が失われてしまう。また、倭国を信頼し仏教振興に協力してきた高句麗と百済を裏切ることになってしまうだろう。
しかし拒絶できるのだろうか。皇帝からの信物の受け取りまで断れば、学問僧派遣を断念するだけでは済まないのではないか。隋に反旗を翻したとして、高句麗とともに征討を受けることになるやも知れぬ。高句麗軍がいくら強勢であるとはいえ、隋軍にかなうべくもない。
6月に館が完成し裴世清は難波に移るが、さらに2カ月留め置かれる。裴世清はいぶかったことだろう。「書紀」に、妹子は煬帝から授かった国書を帰国途中百済人に奪われてしまった、このため群臣は妹子を責め流刑に処したが、天皇が勅して妹子を赦したという訳の分からないエピソードが記されている。当時百済は、隋と高句麗の双方に通じるしたたかな外交をしていたので、倭に対して出された隋の国書を奪うといったこともあり得ないことではないのかも知れない。しかし、倭国の置かれた切羽詰まった状況を考えると、倭国の側の時間稼ぎのための芝居と言い訳というのが真相ではないだろうか。太子のもと倭国は、対応方針を固めるのに時間を要した。8月、裴世清は愈々大和川を遡上し、海石榴市から朝廷に向かう。(写真3)
「書紀」「隋書」ともに裴世清を迎えた倭国の朝廷の様子を描く。「書紀」は、皇子、諸王、諸臣が正装して居並ぶ中、裴世清が進み出て国書を天皇に奏上し、重臣が国書を天皇に取り継いだとしている。太子の姿が見えないのは、太子は推古帝とともに御簾の向こう側にいたからだろうか。「書紀」は、隋の国書の内容も記している。
他方「隋書」は、倭王が裴世清を迎えて相見えたとし、倭王の言葉と、裴世清の返答を記している。「隋書」に倭王は女性だったと書いていないから、会ったのは推古ではない。太子だろう。裴世清は、君主は姿を見せないという倭国の儀礼のしきたりから、推古に直接会うことができなかった。しかし裴世清としてはそれでは任を果たしたことにならないので、太子を倭王とみなして復命したのではないだろうか。
さて、隋の国書の内容だが、「書紀」によると、皇帝は天命を受けて地上に君臨し徳を広めていると自ら宣言した上、倭国が海の彼方から朝貢してきたことを評価する、それゆえ裴世清を遣わし、自分の気持を伝える(原文は「稍宣往意」)というものだった。
対する倭王、おそらくは太子の返答は、「隋書」によると、隋を礼義の国と聞き使者を遣わして朝貢した、自分は海隅にあって礼儀を知らない、隋から徳を学びたい旨の極めてへりくだった内容だった。
これを受け裴世清は、「隋書」によると、
「王、化[教化]を慕うを以って、故に行人[使者]を遣わし、此に来り、宣べ諭さしむ」
と述べ、その後館に戻ってから、
「朝命は既に達せり」
と言って、使者(妹子)を伴って隋に帰ったとされている。これが分からない。なぜ朝命を達したことになるのか。裴世清は皇帝の国書を伝えただけで使命を果たしたことになるのだろうか。
「隋書」の原文は、
「以王慕化故遣行人來此宣諭」
である。これを講談社学術文庫版は上のように読み下している。岩波文庫版もほぼ同様だ。しかし、ネットのサイト「隋書倭人伝をそのまま読む」は、この部分を
「以て王を慕化す。故に人を行か遣め、来れば此に宜しく諭さしむべし。([夷の]王は慕化します[感化されます]。故に、人を中国に行かせ、帰ったら国の人を諭すように計らうべきです。)」
と読み下し訳している。皇帝の徳に従い留学生を送れば、彼らが帰国後、国に貢献するでしょうという意味だろう。高句麗ではなく隋の側につけということを含意していると私は考える。これなら理解できる。太子率いる倭国が隋のこの提案を受け入れたから、裴世清は朝命を達したと言ったのだと思う。そうでなければ復命できない、「隋書」に載ることもなかった。
倭国は、隋から先進仏教文明を導入するため、親高句麗路線から親隋路線に転換した。
9月、裴世清は帰朝の途に就く。小野妹子、吉士雄成が、学生、学問僧合わせて8人を伴って随行した。第3回遣隋使となる。(このとき派遣された学生高向漢人玄理、学問僧新漢人日文(僧旻)らが、37年後の大化改新において、孝徳政権のブレーンとなって改新政策を進めることになる。太子の目的は達成されるのだ。)煬帝に送った天皇の挨拶文が、「書紀」に載っている。その冒頭の文が、
「東天皇敬白西皇帝(東の天皇が、つつしんで西の皇帝に申し上げます。)」
である。これを前年の国書の文と比較すると、
「日出処」→「東」
「天子」→「天皇」
「致書」→「敬白」
「日没処」→「西」
「天子」→「皇帝」
「恙無云云」→(削除)
と置き換えられている。
「日出処」「日没処」を「東」「西」に換えたのは、ニュアンスの違いはあるだろうが、基本的には言い換えと考えられる。中国と対等の関係にあった国が使った文言「天子」「致書」「恙無」を使わなくなったのは、親高句麗路線を止め、親隋路線に転換して隋への朝貢関係をはっきり認めたからだ。
それでも倭国の「天子」を「大王」に置き換えはしなかった。「王」は皇帝の臣下を意味することになってしまうから。隋側につき朝貢するとはいえ、冊封は受けず独立国を堅持するというのが、倭国の基本スタンスだからだ。そこで「天皇」という新しい称号をここで初めて使ったのだと思う。
「天皇」号の成立時期に関しては様々議論がある。天武朝説に立てば、ここで使われたはずはない、「大王」とあったのが「書紀」編纂時に書き換えられたということになる。しかしそれは結論ありきの決めつけではないだろうか。大体、仮に「天皇」ではなく「大王」だったとすると、「東大王」が「西皇帝」に敬白することになるが、それでは釣り合いが取れず、この文が成り立たない。実際、推古帝も太子も煬帝から何ら叙爵されていない。「天皇」号が広く使われるのは天武朝からのようだが、脈絡を考えると、ここで初めて使われたと考える方が、筋が通っている。
(参考文献)
・堀敏一『東アジアのなかの古代日本』(研文出版、1998)
(出典)
・魏徴「隋書」(本紀・列伝 636年)
・巻81列伝46(東夷、倭国) 藤堂明保他訳『倭国伝』(講談社学術文庫)
・巻84列伝64(北狄、突厥12) 『中國哲學書電子化計劃』(ネット)
・班固「漢書」(1C後半)
・伝64匈奴伝(匈奴伝上17、18) 『中國哲學書電子化計劃』(ネット)
(以下、次回)