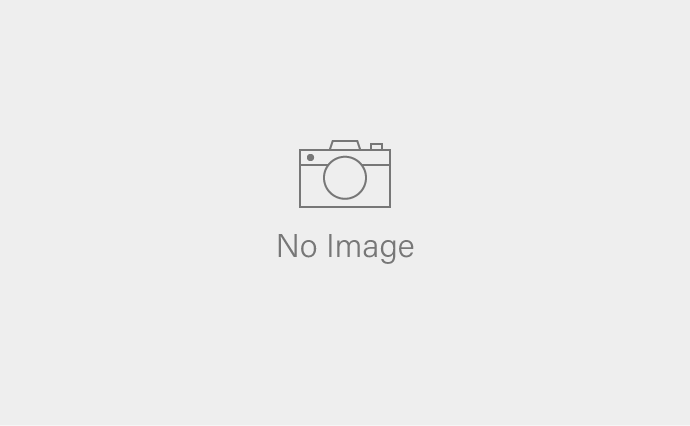2024年9月24日 naohara hiroshi
「古代史を考える」にようこそ。日本古代史の謎について考えています。/
まずはじめの謎、神武天皇の即位年について
「日本書紀」には、神代の時代の後、神日本磐余彦が日向から東征し、大和の橿原で初代天皇に即位したと書かれている。神武天皇だ。「書紀」には以後持統まで歴代40人(壬申の乱で敗れた弘文天皇(大友皇子)は「書紀」では認められていないので入っていない。)の天皇と神功皇后の治世が記され、持統が孫の珂瑠皇子(文武天皇)に譲位するところで終わる。持統の譲位は持統十一年で、この年は西暦697年に当る。
持統から遡って神武まで各天皇の在位年数が「書紀」に書かれている。途中いくつか空位年があるが、それも足し合わせると、1,357年になる。つまり神武即位は西暦紀元前660年となる。本にそう書いてある。「書紀」から各天皇の在位年数を拾って計算すると実際そうなった(資料1)。これは、卑弥呼の時代の900年も前だ。考古学の年代区分からすると、縄文時代の終わりから弥生時代初めの頃に当る。「書紀」の記述が非現実なのは明らかだ。/

なぜ「書紀」にはこのような非現実な話が書かれているのか。誰がそうしたのか。
古くは、江戸時代19世紀前半に国学者伴信友が、神武紀元は古代中国の星運説(干支の辛酉年に革命が、甲子年に革令が起きるとする予言の言説)に基づく後世の作為と論じた。「書紀」は神武の即位年を辛酉としただけではなく、東征進発の年を干支の始めとされる庚寅におき、大和平定(饒速日が長髄彦を殺して帰順)を戊午革運の年とし、即位四年甲子に至って初めて皇祖の天神に対する祭祀の記事を配するなど、明らかに中国の星運説に拠って日本の建国プロセスを記述していると指摘した。神武即位年だけなら偶然の可能性もありうるが、その前後の事績も星運説に合致しているとなると、これはもう偶然とは言えない。辛酉革命説によって神武即位年が決められたと言わざるを得ない。
19世紀末、東洋史学者那珂通世は、「書紀」の紀年は、推古九年(601)辛酉を起点とし、そこから一蔀1,260年遡った西暦紀元前660年に神武即位年を設定したものであると論じた。古代中国の前漢末から後漢の時代に、儒教の中に讖緯説という神秘的な予言思想が取り入れられ広まった。一蔀とは、この讖緯説に基づく時間の区切りであり、干支の一巡60年の21倍に当たる。讖緯説によれば、一蔀経ることで、革命が再び起こることになる。「書紀」は、推古九年辛酉に革命が起きたとし、この論理を裏返して、その一蔀前に神武が即位し日本が建国されたことにした。那珂通世はそう論じた。
那珂通世はさらに、これは「書紀」以前に、「書紀」に、推古二八年(620)、皇太子(聖徳太子)と嶋大臣(蘇我馬子)が協議して記録したと記された「天皇記及国記」の編纂において定められたと論じた。ただ、「天皇記」は乙巳の変(645)で焼失し、「国記」はそのとき残ったとされるが現存しないので、確証があるわけではない。
大津透先生(著作を通じて尊敬する専門家の皆様を、私は「先生」と敬称を付けてお呼びしたいのだが、以下では省略することをお許し願いたい。)は、この那珂通世説を引き、「書紀」編纂時に定められたとする異説に言及しつつ、「七世紀前半の推古朝において、神武即位、建国年次が決められたと考えられる」としている。
直木孝次郎は、「神武以後の1,260年を、各天皇にこまかに割りつけた年表のようなものが推古朝にできあがっていたかどうかは疑問だが、神武即位の年をきめるところまでは、聖徳太子によっておこなわれたと考えられる」としている。
様々な状況証拠から見て、聖徳太子が神武紀元を仮構したと考えてよいと思う。では太子はなぜ推古九年から一蔀1,260年前に初代天皇が即位したことにしたのだろうか。/

写真1 聖徳太子磯長墓(大阪府南河内郡太子町、叡福寺境内)/
聖徳太子の設計した歴史の枠組
その理由を探る前に、太子は歴代天皇の在位をどのように設定したのか考えてみよう。神武即位年を決めただけでは終わらない。当然、初代神武から(太子にとっての)現在まで、皇統がどう続いたか説明しなくてはならなくなるから。
「天皇記及国記」を編纂した推古二八年(620)の太子の前には、どのような史料があったろうか。まず、6世紀中頃、欽明朝の頃にまとめられたとされる帝紀と旧辞。大王家や諸豪族から集めた各々の系譜や伝承を記した文書群、あるいはその断片を集積したものと考えられる。
第二に中国の史書。140年ほど前、478年に倭王武(雄略天皇)が南朝宋の皇帝に上表文を奉じた。「宋書」にその全文が載っている。冨谷至によると、この上表文は、様々な中国の古典から成語・熟語を引用し、それらを巧みに用いた正統漢文で書かれている。当時倭国には、「論語」、「礼記」、「詩経」、「尚書」、「春秋左氏伝」「三国志」等々が存在した。その後倭国は中国の冊封体制から離脱したので、中国文明の新たな流入は閉ざされたが、書物は残っていたはずだ。太子は、「史記」のほか、倭国への言及がある「漢書」「後漢書」「三国志(魏志倭人伝)」「宋書」を読んだだろう。
第三に朝鮮の史書(残念ながら現存しない)。倭国よりいち早く中国の律令を導入した朝鮮三国は、それぞれ史書を編纂していた。新羅では6世紀半ばに国史編纂が始まっており、高句麗では600年に史書が撰述されている。百済でも、後に「書紀」に「百済記」などが引用されるのだから、その元となる史書が当時存在したと考えられる。
これらを太子は、当代最高の学識を有した、師である高句麗僧慧慈と百済の博士覚哿から学んだ。
慧慈と覚哿から学ぶことで太子は、東アジア史の中で倭国の歴史を捉えるようになっただろう。その際、通史のある中国史を基軸に置かざるをえなかったはずだ。太子の立場になってみると、こうだったのではないか。/

(1) 中国の歴史(資料2「太子の歴史構想」-(1)参照)
推古二八年(620)の直近の辛酉年が推古九年(601)。この年を起点にして[当時、座標軸になる、西暦のような 通しの紀年はなかった。]10年前(589)に隋が中国を統一。160年前(439)に北魏が華北を統一し、南北朝時代が始まった。320年前(280)に三国時代が終わり、晋が中国を統一。400年前(220)に後漢が滅びた。800年前(紀元前206)に、20年続いた秦が滅び、漢が興った。1075年前(紀元前476)に戦国時代が始まった(「史記」で六国表が始まる年)。その少し前に(紀元前479)孔子が没した。周が都を洛邑に移し春秋時代が始まったのは1,370年前(紀元前770)である。[太子はこうした時間軸を認識しただろう。]
(2)倭国の歴史 (資料2-(2)参照)
それに対して倭国の歴史はどうか。暦(元嘉暦)が入 ったのは150年前(5世紀半ば)、おそらく安康朝。それ以降の帝紀・旧辞は暦を含むので概ね確かなものと考えられる。帝紀・旧辞に記されたそれ以前の事象は暦を伴わない伝承となるが、朝鮮の史書と照らし合わせると、現皇統に直接つながる応神の即位は220年前頃(380頃)と見てよい。[「古事記」に記された分注崩年干支(注1)に関する那珂通世の考証によると、仲哀の没年が西暦362年、応神の没年が394年とされており、矛盾はない。]
それ以前となると茫漠としているが、ヤマト王権の初代大王(天皇)と伝わり、御肇国天皇と称される崇神の即位はいつか。「魏志倭人伝」によると、400年ほど前(200頃)に卑弥呼の邪馬台国を中心に倭国がまとまり、350年前(248)に卑弥呼が没して再び国が乱れたとされる。崇神が即位しヤマト王権が成立するのはそのすぐ後、350年前頃(250頃)と考えてよかろう。ヤマト王権の歴史はたかだか350年にすぎない。[太子は倭国の歴史をこのように認識したと思われる。「古事記」分注崩年干支によると崇神の没年が258年とされており、矛盾はない。なお、「書紀」神功皇后六六年に、晋起居注(注2)から引用した倭女王(卑弥呼の宗女・台与とされる)の朝貢記事がある。この年、266年にはまだ邪馬台国は存在した、つまりヤマト王権は成立していなかったということだ。ヤマト王権の歴史は本当は300年くらいにすぎない。「晋書」の成立は648年であり、太子はこの史実を知り得なかった。]
(3) 仮構の歴史(資料2-(3)参照)
[中国王朝に比べヤマト王権の歴史の浅さを知り、太子はどう考えたのだろうか。太子の考えたプロセスはこれから究明していかなくてはならないが、考えた結論はヤマト王権も中国王朝に匹敵する歴史を持つべきだということだった。それが、直近の辛酉年である推古九年(601)から一蔀1,260年前の神武即位だった。太子は1,260年前に始まるヤマト王権の歴史を仮構した。]
この仮構の歴史と、現実の[と太子が考えた]ヤマト王権の歴史とをどうすり合わせるか。史書を書くには、記す内実がなくてはならない。それには現実の歴史を引き延ばす必要がある。それでも2倍が限度だ。崇神即位を350年前の2倍、350×2=700年前としよう。[西暦紀元前100年となる。これは、「書紀」の崇神即位年をそのまま西暦に直した紀元前97年にほぼ一致する。]
一方150年前に暦が入ってからは変えようがない。間の応神即位を220年前の1.5倍、220×1.5=330年前としよう。[西暦271年となる。これは、「書紀」の応神即位をそのまま西暦に直した270年とほぼ一致する。]
ただ、崇神即位以前、700年前から1,260年前までは、創作せざるを得ない。この間の560年は、天皇一代60年として9代、神武を除くと8代の内実を伴わない天皇を創作することにする。[これが、第2代綏靖から第9代開化までの、いわゆる「欠史八代」に当たる。]
太子はこのようにして、起点から1,260年前の神武即位に始まるヤマト王権の歴史の枠組を設計したのだと思われる。太子は、帝紀・旧辞に記された様々な事象を、この枠組に落とし込み「天皇記及国記」を編纂した。それは「書紀」の原型とも言えるものだったろう。
次は、なぜ太子はこうした枠組を作ったのか、なぜ初代天皇の即位は中国王朝の歴史に匹敵する1,260年も前でなくてはならないのか、そうする意図はどこにあったのかを考えたい。それには、太子の生涯を追い、太子が直面した状況を理解しなければならない。
(注1) 分注崩年干支とは、現存最古の「古事記」写本である真福寺本(1371年頃)の本文中に分注として記載された、崇神~推古24代中15代の天皇の没年の干支。那珂通世がこれらを考証し、西暦に換算した。大津透は分注崩年干支を、「後世の押しあてで、『日本書紀』に先行するある時期の紀年構成の試みなのだろう」としている(大津『神話から歴史へ』p.125)。
(注2) 起居注とは、側近が記録した皇帝の言行録。後年、史書編纂の資料となる。晋の起居注(現存しない)が、「書紀」編纂時の日本に存在した。
(参考文献)
・伴信友「日本紀年暦考」(『比古婆衣』1847所収、国立国会図書館デジタルコレクション)
・鎌田元一『律令国家史の研究』(塙書房、2008)
・那珂通世『増補 上世年紀考』(養徳社、1948、国立国会図書館デジタルコレクション)
・大津透『神話から歴史へ』(講談社、2010)
・直木孝次郎『古代国家の成立』(中公文庫、1973)
・冨谷至『漢倭奴国王から日本国天皇へ』(臨川書店、2018)
(以下、次回)