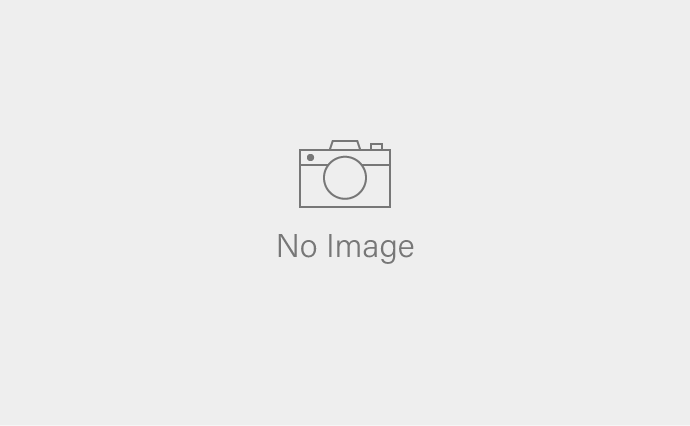2024年11月19日 naohara hiroshi
前回第2回で、聖徳太子は600年に初めて遣隋使を送り東アジアの国際政治に参入した、しかし倭国の政治の様子を聞いた隋の文帝から倭国は文明国として認められなかったと書きました。今回は、その遣隋使の帰朝報告を受けて、太子はどうしたかを辿ります。
1 冠位十二階
「書紀」推古八年(600)条を見ると、前回述べたように遣隋使の記述はない。あるのは、任那救援のため新羅に派兵し攻略したという話。目的は高句麗・百済の側に立って新羅を威嚇・牽制することであり、実際の派兵はなかったと思われる。続いて十年、十一年に、それぞれ皇子(太子の同母弟と異母弟)を将軍として新羅征討軍を編成し筑紫に駐屯させたとある。太子による朝鮮情勢への積極的関与は、続いていた。
内政記事を見ると、九年に斑鳩への宮殿建設開始、十年に百済僧観勒が来朝し暦・天文地理・遁甲(占星術)・方術(占い)を伝えた、十一年に小墾田宮に遷宮した、秦造河勝により蜂岡寺(広隆寺)が造営された、儀仗用の大楯・靫・旗を整備したとの記述がある。
太子は後年国政から身を遠ざけ斑鳩に隠棲するようになるが、政治の陣頭指揮をとっているこの時点で斑鳩宮の造営を始めた。隠棲するために斑鳩に拠点を設けたのではないということだ。斑鳩の地は、大和川が多くの支流を集め生駒山系と葛城山系の間を通って河内に抜ける根元に位置する。大和の都と河内を水運で繋ぐ要衝の地だ。そして明日香から離れている。直線で約18km。太子はここを自分の拠点に選んだ(地図4)。
これと推古帝の小墾田遷宮とはセットで考えるべきだと思う。小墾田宮の位置は確定していないが、明日香の雷近くとするのが通説である。しかしそれではなぜそれまでの豊浦宮から宮を移したのか理解できない。豊浦宮は飛鳥川を遡った同じ明日香にある。そこは、欽明帝と蘇我堅塩媛との皇女炊屋姫(推古)が育った場所、蘇我氏の拠点だ。近くにわざわざ宮を移すだろうか。太子は、それまでの大王の代毎にその住まいを宮とする方式を改め、600年遣隋使の報告に基づいて中国に倣い、国の恒久的な統治拠点としての宮を整備しようとしたのではないか。そう考えると、飛鳥川上流の奥まったところに新宮を置くとは考え難い。大和盆地の水系を考えて自身の拠点を斑鳩に構えた太子なら、新宮は大和川本流に近い所に置くだろう。実際、「書紀」によると、後年(608)隋使の裴世清は、難波津から舟で大和に向かい、磯城の海石榴市で上陸した。宮は海石榴市から遠くないところにあったはずだ。ここは梅原猛説に従い、小墾田宮は桜井の大福に置かれたとするのが妥当であるように思う(地図4、写真2)。
観勒からの暦や遁甲の習得、蜂岡寺造営による仏教の普及、儀仗の礼制の定め、これらはいずれもこの時期に先進文明の導入努力が盛んに続けられたことを物語っている。
こうした内政改革の一環として、推古十一年(603)12月から施行されたのが冠位十二階だ。「書紀」によると翌十二年(この年は讖緯説では革令が起こるとされる甲子に当る。太子はこのことを意識し、これからやろうとしていることが倭国の体制を変える大きな一歩になると認識していたのではないだろうか。)正月朔に、はじめて冠位を群臣(諸臣、群卿、大夫とも書く。)にそれぞれ賜ったとされる。朝廷の組織整備と言えよう。
それまでヤマト王権の朝廷は、継体~欽明朝に成立した氏姓制に基づき、有力な氏の代表者によって構成されていた。冠位十二階によって、考え方としては、姓によって限定されることなく、また、各氏一人に限らず個人として大王から位が与えられ、群臣として朝廷に参加できることになる。昇進もできる。豪族連合から大王中心の朝廷への大きな変化だ。秦河勝も小野妹子も出身氏からすると、これまでなら群臣になれなかったが、太子によって引き立てられた。有能さを太子に認められたのだろう。もう一つ、中国との外交交渉に参加するには位が必要だった。氏と姓では、中国的礼の秩序に通用しない。位がないとカウンターパートも決まらない。この点も600年遣隋使の報告によるのだろう。
尤も蘇我氏は別だった。馬子は冠位を与える側だった。太子は、本当は馬子にも冠位を与え、蘇我氏が牛耳る朝廷から、真に大王に権力が集中した朝廷に変えたかったのだろうが、馬子との力関係からそこまでは出来なかったのだと思われる。
十二階とは、上から、徳・仁・礼・信・義・智、この6つにそれぞれ大小があって12階となる。徳目を冠位一つひとつの名称としている。ただし儒教の徳目である「五常」、すなわち仁・義・礼・智・信と異なっている。徳を最上位に加えるとともに、義より礼と信を、智より信を上に置いた。
この点について、中国古代宗教思想史の泰斗である福永光司は、道教の影響によると指摘している。儒教の五常の上に「徳」を置き、順番を徳・仁・礼・信・義・智としたのは、5C頃に成立した道教の経典「太霄琅書」だそうである。当時、老荘道家の哲学と儒教思想は折衷していた。602年に百済僧観勒が倭国に遁甲方術を伝えたときに、これと密接に関係する道教をもたらし、それを太子が学んだと福永は推定している。
確かに、太子が初代天皇の即位年設定の根拠とした讖緯説も、道教哲学と深く関係しているようだ。冠位の名称の由来も、太子と道教との関わりも、今のところはっきりしてしない。ただ、太子の考える道徳秩序が徳・仁・礼・信・義・智の順番であったことは間違いないだろう。
第1回遣隋使の報告を受けて、太子は倭国の未熟さを思い知らされた。大王を中心とした集権的国家機構の整備、これが命題だった。これを、朝廷を構成する群臣の位階制度として形にしたものが冠位十二階だった。
2 憲法十七条
冠位十二階は、これまで群臣として朝廷を運営してきた有力な氏にとって、自らの朝廷における基盤を揺るがすことになるのではないかと、警戒されたかも知れない。馬子も、蘇我氏は冠位を与える側にいたとしても、その考え方が根本において氏を超えた国家像を内包していることに気づいていたはずだ。それでも馬子は許容した。新宮が明日香の地から離れるのを許容したように。馬子は、太子の内政改革を見守った。馬子が認める以上、各氏も従うほかなかった。
太子は、冠位十二階に基づき朝廷をどのように運営していくか、その心構えを担い手である群臣と百寮(各官司の役人。百官とも書く。)に理解させる必要があった。憲法十七条はその説明文、今で言えば閣僚と官僚の規範を定めた文書だったと考えられる。冠位下賜から3か月後の推古十二年(604)4月、太子はこれを定めた。
各条文を読むと、そこに太子の人間観、社会観が表われているのが分かる(資料5)。上に述べた徳目の順番に関しては、第4条で、「礼」が民を治める基本であるとしている。また、第9条において、「信」(まごころ)が「義」(為すべきことをすること)の根本であるとしている。
太子が国家運営をどのように考えていたかという観点から興味深いのは、第2条と第3条だ。第2条で、「あつく仏教を信仰せよ」と述べる。仏教興隆の詔から10年経ち、今や仏教は群臣・百官の規範となった。「仏教はあらゆる生きものの最後に帰するところ、すべての国々の仰ぐ究極のよりどころである」とする。太子は儒教を学び、中国流の律令国家への道を歩み始めたが、太子にとって究極のよりどころは儒教ではなく仏教だった。「あらゆる生きもの(四生)」、「すべての国々(万国)」と言っているように、仏教の教えに普遍性を認めている。
第3条は、「大王(天皇)の命令を受けたら、かならずそれに従え」に始まる。他の条文は基本的に群臣及び百官の間の関係について述べ、そこでは相互の信頼を求めている。これに対し、大王と群臣・百官の間は、命令と服従の関係だ。倭国をこれまでの豪族連合から脱却させ、大王中心の集権国家に転換することを宣言するとともに、大王への忠誠を強く求めたものと言えよう。
「書紀」は、「皇太子は、みずからはじめて憲法十七条をおつくりになった」と記す。冠位十二階は誰が作ったかを明記していない。冠位十二階も太子が作ったのだろうが、大王推古の名において発せられたので、太子の名は書かれなかったのだと思われる。しかし憲法十七条は、摂政の権限で太子の名において発せられた。
日本の歴史を振り返って、太子以外に、為政者自らその統治の思想と信念を文書にまとめた人はいたろうか。なかなか思い浮かばない。十七条憲法偽作説がかつてあったが、それはありえない。こうしたものを書くことを考えついた人が他にいたとは到底思えないから。候補者が見当たらない。朝廷の位階制度に関してみれば、その後、孝徳、天智、天武、文武と改正されるが、誰もそのようなことはしていない。太子は、自分の考えを文章にまとめ、発しないではいられない人だった。
憲法十七条の後も太子の内政改革は続く。「書紀」によると、同年9月には朝廷における拝礼の規定を定める。
翌推古十三年(605)、銅及び繍の仏像の製作を推古帝の名において命じる。梅原猛説によれば、慧慈の伝えた北朝系仏教の教えである、「皇帝こそ仏であり、仏こそが皇帝である」という思想に基づき、前者は太子を、後者は推古帝を模して造形されたとされる。高句麗から黄金三百両の財政支援を受けてこれらを完成させ、翌年法興寺に納める。法興寺は馬子が心血を注ぎ蘇我氏の寺として創建されたのだが、ここで国家の寺となった。馬子はこれも見守った。
太子は、十三年から斑鳩に居を移した。十四年、推古帝の招きで「勝鬘経」を、ついで「法華経」を講じた。太子の仏教研究はライフワークとして続けられていた。推古帝は太子に播磨国の水田を与え、太子はそれを斑鳩寺(法隆寺)に施入したとある。
仏教一辺倒ではなかった。「書紀」によると、推古十五年(607)、推古帝は神祇祭祀の詔を発し、太子と大臣(馬子)は百寮を率いて神祇を祭拝した。大王は天津神の子孫であるとする、大王家に代々受け継がれてきた観念は、仏教に帰依した後も護持しなければならなかった。バランス感覚から?いや、大王統治の正統性の根拠として必要だったのだと思われる。
内政改革はなされた。満を持して、太子は再び隋に遣使する。
(参考文献)
・梅原猛『聖徳太子1~4』(集英社文庫、1993)
・福永光司『道教と日本文化』(人文書院、1982)
(以下、次回)