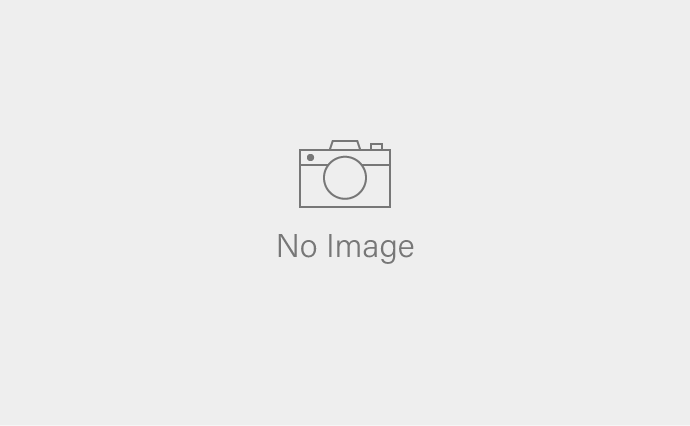2025年1月12日 直原裕 naohara hiroshi
前回、倭国が、隋から先進仏教文明を導入するため、それまでの親高句麗から親隋に路線変更することになった経緯を見ました。今回はその結末です。第1回から持ち越した疑問、聖徳太子が建国の枠組をつくった理由について考えます。
隋-高句麗戦争
裴世清を倭国に送り、倭国を高句麗から離反させることに成功した煬帝は、この年608年に永済渠の開鑿を命じた。高句麗戦の前線基地となる幽州琢郡(現在の北京市を含む地域)と黄河を繋ぐ運河だ。これが完成すると文帝時代から開鑿を進めてきた運河と繋いで、長江から淮水、黄河を通り前線基地に輜重を輸送することが可能になる。人民百余万人がそのために動員されたとされる(資料7、地図6)。
翌609年、煬帝は青海・甘粛に親征し、吐谷渾(当時青海一帯を支配した鮮卑系の国)を征討する(第2回の地図3、第4回の地図5をご覧ください。)。高句麗戦の前に西方の反乱要因を排除した。煬帝は高句麗との戦争準備を周到に、着々と進めていた。
妹子はこうした隋の臨戦状況を見てこの年倭国に帰国し、太子に報告した。それは、太子の思い描いてきた「海西の菩薩天子、重ねて仏法を興す」(第2回遣隋使の国書の言葉)とはかけ離れた隋の実態だっただろう。太子は、隋に学問僧らを送り倭国に先進仏教文明を導入するとした自分の判断が、東アジア政治の中では戦争への一階梯でしかない現実に打ちのめされたのではないだろうか。しかも、隋から冊封は受けない、倭国は独立国だと主張しても、隋に朝貢した以上、これから起こる戦争に関し倭国はアクターになりえない。傍観するしかなく、身動きが取れない状態になってしまった。この後、太子の姿は「書紀」に見えなくなる。
「書紀」によると翌610年、高句麗から僧の曇徴と法定が来朝した。曇徴は絵具と紙・墨を倭国に伝えた。法定は碾磑(水車による臼)を伝えた。高句麗は、倭国を自陣営に引き留めることを諦めず、倭国が欲する技術者を送ったのだった。
他方、新羅の使が、任那の使を伴って来朝し朝貢した。任那は50年も前に新羅に併合され、実体はなくなっているにもかかわらずだ。新羅からの朝貢使は敏達朝以来となる。新羅に対し、倭国が長年「任那の調」を奉るよう求めてきたことへの阿りだろう。新羅はおそらく隋から要請されて、こちらも倭国を自陣営に留め置くため朝貢してきたものと思われる。朝貢使を迎えた朝廷の儀式に太子の姿はない。応対したのは馬子である。
その翌年611年にも、新羅使は任那使を伴って倭国に朝貢する。そしてこの年、「隋書」によると、新羅と百済は、それぞれ隋に朝貢した。対高句麗戦において隋陣営に属することを約束したのだろう。尤も、百済は同時に高句麗とも連絡をとっていた。そしてこのことも「隋書」に書いてある。百済の二股外交は、隋に見抜かれていた。
この頃には永済渠が完成したものと思われる。準備は整った。煬帝は高句麗討伐の詔を発した。
612年、戦端が開かれた。113万にも及ぶ隋の大軍が高句麗領に進軍した。しかし隋軍は大敗したのである。高句麗軍は守城戦をしたたかに戦い、隋軍を翻弄し補給不足に追い込んだのだ。翌年にも隋軍は進攻。しかし今度は隋政権内に反乱が起き、その鎮圧のため退却を余儀なくされる。
さて、この頃太子は何をしていたのだろうか。「書紀」613年条に、所謂片岡山飢人説話が載っている。太子が片岡山(斑鳩から竜田山に向かう途中か)を遊行していたところ、道端に飢人が倒れていたので、水と食べ物を与え、着ていた衣服を脱いで掛けてあげた。翌日飢人は亡くなっていたとの報告を受け、その場に埋葬させた。数日後、使人が見に行くと屍骨はなくなっており、太子の与えた衣服が畳んで棺の上に置いてあった。太子はその衣服を取って来させ、元のとおりそれを身に着けた。人々はたいそう奇異に思い、「聖が聖を知るとは本当だ」と言ったという話だ。後の世の(と言っても「書紀」編纂の前だが)太子像から生まれた物語と思われるが、この頃の太子の実像をなにがしか含んでいるのだろう。太子は現実の政治の世界から離れた所にいた。
太子が「三経義疏」を執筆したのはこの頃と思われる。奈良時代末から平安時代初期頃に作成された「上宮聖徳太子伝補闕記」では、太子は、609-611に「勝鬘経疏」を、612-613に「維摩経疏」を、614-615に「法華経疏」をつくったとされている(写真4)。その信憑性については諸説ある。
「三経義疏」は、3つの経に関してそれぞれ中国で書かれた本義(注釈書)をベースとして、さらに自己の解釈を展開した書物である。慧慈と慧聡(百済から来朝し、慧慈とともに倭国仏教の棟梁となった僧)の見解も入っているだろうが、最終的には太子の理解した仏教の教えを書き記したものと言ってよいと思われる。この間太子は政治の世界での失意から、仏教研究を通して、真理の探究に没頭していた。
隋-高句麗戦争に話を戻すと、614年隋は三度目となる高句麗進攻を実施した。しかしこの時には中国各地で、重税と土木工事・戦争への動員によって疲弊した人民の反乱が勃発した。戦闘自体はこちらも疲弊した高句麗が和議を申し出ることによって終結したが、人民の反乱は収まらなかった。「書紀」に、この614年犬上君御田鍬らが第4回遣隋使として派遣され、翌年百済使を伴って帰国したと記されている。「隋書」には記載がない。隋は朝貢に応対できる状況になかったものと思われる。
615年帰国した御田鍬から、倭国の朝廷は、隋-高句麗戦争の結末と隋国内の混乱状況について報告を受けたはずだ。太子と慧慈もその報告を聞いただろう。
この年慧慈は高句麗に帰国する。慧慈は、倭国を高句麗側につけるという国家の使命を負い、595年倭国の若き指導者である太子の師として派遣された。高句麗としては、倭国を繋ぎとめることはできなかったものの隋との戦闘が終了し、潮時と考えたのだろう。
太子と慧慈の有名なエピソードが「上宮聖徳法王帝説」にある。「三経義疏」執筆の時のものと思われる。
「太子が質問した点で先生がわからないところがあると、太子は夜、金色の人が現れて、理解できなかった意味を 教えてくれる夢を見た。目覚めてから太子はその点を解釈することができ、そこで先生に伝えると、先生もまたそれによって理解することが出来た」(田村晃祐の訳。中公クラシックス『聖徳太子』p.168)
慧慈と太子は、政治的な思惑を超え、師弟の関係をも超えた、ともに真理を探究する者同士の敬愛の関係にあったと考えられる。慧慈は帰国後7年して、太子の死を聞き、1年後自分も死んで浄土で太子に会うと言い、1年後その通り亡くなったという逸話が、「帝説」と「書紀」に載っている。
太子の考えたこと
615年、御田鍬の帰朝報告の時点に話を戻す。報告を聞き、太子は再び現実の世界に向き合うことになる。政治指導者としてではなく政治思想家として。
1 天子と天皇
先進仏教文明を導入するために、それまでの親高句麗路線を止め、朝貢することにした隋帝国が崩壊しつつある現実を知り、太子は自分の下した選択をもう一度顧みたのではないだろうか。
第3回遣隋使に持たせた国書において、倭国の君主を「天子」(資料8-(1))ではなく「天皇」(資料8-(2))と称した。第2回遣隋使で使った倭国君主の「日出ずる処の天子」が中国の「天子」と意味が違うことは承知していたはずだ。倭国君主の「天子」は天神の子であり、かつて北方の突厥イシュバラ可汗が使った「從天生大突厥天下賢聖天子」の天子と同じ意味だ。大王家では、幼武大王(雄略天皇)以来、代々大王は天神の子孫であると伝えられてきた。これに対し中国の「天子」は、天から徳を認められ、天命により地上の統治を命ぜられた者である。太子は違いを承知の上で、倭国の君主と隋の君主は対等な関係にあるという主張を込めて、ともに「天子」と呼んだのだと思われる(注1)。しかし仏教より儒教を根幹に据える煬帝からすれば、蛮夷の弱小国の王が「天子」と称することは認められるはずもなかった。太子は、学問僧受け入れを実現するため、「天子」に代え「天皇」と称した。
なぜ煬帝は倭国君主が「天子」を自称するのをそこまで拒絶するのか。太子はこう考えたのではないだろうか。
天が地上世界の統治を命じるのは一人しかいないから。天子が二人いたら、天の思想が成り立たなくなってしまう、皇帝による中国の統治の正統性が崩れてしまうからだろう。この原理に立てば、周辺国の君主は、中国皇帝の臣下たる「王」でしかありえなくなる。強力な思想だ。それが中華思想だ(資料8-(3))。
しかしこの天の思想、中華思想は、中国皇帝にとってのみ都合の良い原理ではないか。天子には徳がなくてはならない、それは立派な考え方だ。儒教に基づく国家統治の諸制度は確かに優れている。でも、根本的には中国でしか通用しない原理ではないのか。儒教思想の根幹にある「天」の存在は証明されていない。仮構だ。
それなら「天皇」は天神の子孫というのも同等だ、仮構だ。天の思想を否定することはしないが、同等に、天神の子孫である天皇が倭国を統治するという正統性の原理だって成り立つだろう。中国と倭国はやはり対等なのだ。
太子の立場になってみると、こうだったろう。仏教という普遍思想を最終的な拠り所とする太子だからこそ、儒教の天の思想も、大王家で継承されてきた天神の子孫説も、共に相対化する視点を持てたのではないかと思われる。
2 未来のため歴史を作る
616年中国では各地で反乱軍が割拠し、煬帝はとうとう江都(揚州)に移る(地図6)。以後この地で遊興に明け暮れる生活を送ったという。618年煬帝は弑逆され隋は滅びる。2か月後李淵が皇帝位につき唐を建国する。「書紀」によるとこの年、高句麗から倭国に使節が送られた。倭国との関係再構築のためだろう。使節は隋軍撃退を伝えたと記されている。この時、隋滅亡と唐建国も倭国に伝わったと考えられる。
東アジア世界を一変させた隋帝国が、中国統一から僅か30年で消滅した。妃の橘大郎女が聞いた太子晩年の言葉が、「天寿国繍帳」に記され、それが「上宮聖徳法王帝説」に引用されて残っている。
「世間虚仮唯仏是真(世間は虚仮であり、ただ仏のみ真実である:田村訳)」
この頃に発せられた言葉だと思う。
この世界は虚仮であろうと、それでも太子は再び現実の世界に立ち向かった。こう考えたのではないだろうか。
煬帝は、隋の版図拡大のため、人民に過酷な負担を強い、それがために起こった人民反乱の中で自滅した。天の思想のとおり、皇帝が徳を失って王朝は滅び、天命は移った。中国は太古からこうした王朝交代の歴史を重ねてきた(資料8-(4))。しかし倭国はそれと同じでよいのか。否、倭国は天皇が統治する国として未来永劫存続する国であってほしい。
それにはどうする。倭国が未来永劫存続することを支える思想を構築しなくてはならない。天皇は天神の子孫、これなら天命と関係ないのだから、天命が移る(革命)ということは起こりようがない。しかしそれだけでは足りない。証明しなくてはいけない。これまでも、太古から、天神の子孫である天皇が倭国を治めてきたのだと。そうすることによって、だからこれから先も未来永劫、天皇が治める国として倭国は存続できると言い得るのではないか。
天皇が倭国を治め始めたのはいつからとするか。倭国の建国は、中国王朝に匹敵する太古でなくてはならない。統治の正統性の原理は異なるが、対等の関係にあるのだから。その時から代々の天皇が天神の子孫の血を繋いできた。万世一系でなくてはならない。この歴史を構想するのだ(資料2、第1回資料の再掲)。
太子はこのように考えて倭国の歴史を仮構したのではないか。誰に向かってか。これからまた倭国の前に立ち現れるであろう想像上の中国に向かって。そして倭国人の自己定義のために。
倭国は、私(太子)が内政改革を始めた推古九年辛酉(601)から一蔀1,260年前に建国され(注2)、以後歴代天皇が天神の血を繋いで統治してきた。だからこれからも天皇が統治する国として未来永劫存続するのだ。倭国はそういう国なのだ。
太子がこのように考えて「天皇記及び国記」を書いたとき、現在につながる天皇制思想の重要な一歩が刻まれたのだと思う。
太子と馬子がこの歴史書をまとめた2年後の622年、太子は没し磯長陵に葬られた(写真5)。太子の構想、ビジョンは、後年、天武天皇に引き継がれる。
(注1)太子の進めた対等外交の思想的根拠について、仏教学者の田村晃祐は、それはすべての者が仏になれるという一乗思想にあるとした。太子は、この人間平等説の考え方を国家にまで拡大して、対等外交を展開する根拠にしたと論じている(田村「聖徳太子の人となり」、中公クラシックス『聖徳太子』所収)。
ただ、倭国の中華帝国からの独立方針は、5世紀後半に幼武大王(雄略天皇)が宋の冊封体制からの離脱を決めた時に確立し、それが以後踏襲されてきたものと考えられる。とするなら、いくら太子が仏教に帰依していたからといって、太子の対等外交の思想的根拠を仏教に求めることが妥当なのかどうかは、さらに検討が必要であるように思う。
(注2)天の思想を仮構と見た太子も、讖緯思想は受け入れたようだ。「書紀」に、602年百済から来朝した僧観勒が、暦、天文とともに遁甲(占星)・方術(易占)を伝えたとある。その時に讖緯思想ももたらしたのだろう。現在の目からすると非科学的な神秘思想だが、当時は自然の摂理と受け止められたものと思われる。
(参考文献)
・氣賀澤保規『絢爛たる世界帝国』(講談社学術文庫、2020)
・橋爪大三郎、大澤真幸、宮台真司『おどろきの中国』(講談社現代新書、2013)
(出典)
・「上宮聖徳法王帝説」
・東野治之校注『上宮聖徳法王帝説』(岩波文庫、2013)
・瀧藤尊教、田村晃祐、早島鏡正訳『聖徳太子』(中公クラシックス、2007)
・「上宮聖徳太子傳補闕記」国立国会図書館デジタルコレクション